経営戦略は、企業が目標を達成するための計画や方針を指します。これは、企業のビジョンや目標を達成するために必要な方向性を提供するものであり、競争優位を築くための戦略的な枠組みを提供します。今回は中小企業に合った経営戦略の基本的な立て方について分かりやすく解説します。
Contents
そもそも「経営戦略」とは何か

経営戦略」とは、企業が長期的な目標を達成し、競争力を維持・強化するための計画や方針を指します。経営戦略は、経営者や経営陣が企業の方向性を定める際に重要な役割を果たします。そのため、経営戦略の策定は企業の存続や成長において不可欠です。
目的
経営戦略の目的は、企業のビジョンや目標を達成することです。経営戦略は、企業が直面する外部環境や市場の変化を踏まえ、自社の強みや弱みを考慮して策定されます。その結果、企業は競争優位を構築し、市場での存在感を高めるための方針を明確化します。
経営戦略の策定のプロセス
経営戦略の策定プロセスは、企業が長期的な目標を達成し、競争力を維持・強化するための計画や方針を明確化するための重要なプロセスです。以下に、経営戦略の策定プロセスの一般的な手順を説明します。
環境分析
経営戦略の策定プロセスは、まず外部環境と内部状況を評価することから始まります。外部環境分析では、市場の動向、競合他社の戦略、技術の進化などを評価します。一方、内部状況分析では、企業の強みや弱み、リソース、能力などを評価します。
ビジョンと目標の設定
次に、企業のビジョンや目標を明確化します。ビジョンは、企業が将来の姿をどのように捉えるかを示すものであり、目標はそのビジョンを実現するための具体的な目標や目標を示します。
戦略の選択
外部環境と内部状況の分析を踏まえて、戦略を選択します。競争戦略、成長戦略、リスク管理戦略など、企業が目指す方向性に合わせて適切な戦略を選択します。
戦略の策定
選択した戦略を具体化し、戦略を策定します。戦略は、目標の達成に向けて取るべき方向性や行動計画を示すものであり、企業のビジョンや目標と整合性がある必要があります。
戦略の実行
策定した戦略を実行します。戦略の実行には、リソースの配分、組織の改革、プロセスの最適化などが含まれます。戦略を実行するための計画やプロセスを明確にし、従業員や関係者を巻き込んで実行に移します。
モニタリングと評価
戦略の実行と成果を定期的にモニタリングし、評価します。目標の達成状況や戦略の効果を定量的・定性的に評価し、必要に応じて戦略を修正・調整します。
経営戦略の策定プロセスは、環境の変化や市場の変化に柔軟に対応しながら、定期的に見直される必要があります。また、経営者や経営陣が全体の方向性を示すだけでなく、従業員や関係者を巻き込んで戦略の策定と実行を行うことが重要です。経営戦略の策定プロセスを通じて、企業が持続的な競争優位を確立し、成長を実現するための方針を明確にすることが目指されます。
経営戦略の例

経営戦略は、企業が目標を達成し、競争優位を確立するための計画や方針です。以下に、いくつかの経営戦略の具体的な例を挙げます。
市場シェアの拡大戦略
企業が市場シェアを拡大するために採用する戦略です。新規市場への進出や既存市場でのシェア拡大を目指し、マーケティング活動や製品開発などの戦略を展開します。例えば、新しい地域や顧客層に進出し、競合他社との競争を激化させることで市場シェアを拡大する戦略が考えられます。
製品やサービスの差別化戦略
企業が独自の製品やサービスを提供することで競合他社との差別化を図る戦略です。顧客に付加価値を提供し、競合他社との競争を差別化によって回避します。例えば、高品質や特許技術を活用した製品を開発し、ブランドイメージや顧客満足度を高めることで差別化を図る戦略があります。
コストリーダーシップ戦略
企業が低価格戦略を展開し、市場での競争力を高める戦略です。生産効率の向上やコスト削減を重視し、低価格で製品やサービスを提供することで、顧客の支持を得ます。例えば、大量生産や効率的な物流システムを導入することで、コストを削減し、競合他社よりも低価格で商品を提供する戦略があります。
市場ニーズの特化戦略
企業が特定の市場ニーズに焦点を当て、それに特化した製品やサービスを提供する戦略です。ニッチ市場や特定の顧客セグメントに特化することで、競合他社との競争を回避し、高い収益性を実現します。例えば、特定の地域や産業、特定の顧客層に特化した製品やサービスを提供することで、競合他社との競争を回避し、市場での地位を確立する戦略があります。
成長戦略
企業が事業領域を拡大し、成長を促進するための戦略です。新規事業の開発や既存事業の拡大、M&Aなどの手段を活用して事業を拡大し、収益性を向上させます。成長戦略は、企業の将来の成長を支援し、競争力を維持・強化するための重要な戦略の一つです。
これらの経営戦略の例は、企業が市場での競争優位を確立し、成長を実現するために採用できる様々なアプローチを示しています。企業は、自社のビジョンや目標に合わせて適切な戦略を選択し、戦略の実行に努めることで、競争力を強化し、持続的な成長を実現することが求められます。
経営戦略の種類

経営戦略は、企業が目標を達成し、競争力を確立するための計画や方針を指します。企業の状況や目標に応じて様々な種類の経営戦略があります。以下に、経営戦略の主要な種類をいくつか紹介します。
市場進出戦略
市場進出戦略は、企業が新しい市場に参入するための戦略です。これには、新規市場への進出や既存市場でのシェア拡大などが含まれます。市場進出戦略には、以下のようなタイプがあります。
市場開拓戦略
新規市場への進出を促進するための戦略。新しい地域や顧客セグメントへの展開を目指します。
市場開発戦略
既存市場での販売を拡大するための戦略。既存の製品やサービスを新たな顧客層にアピールすることを目指します。
競合排除戦略
既存市場での競合他社を排除し、市場シェアを拡大するための戦略。価格競争や顧客サービスの向上などが含まれます。
成長戦略
成長戦略は、企業が事業を拡大し、収益性を向上させるための戦略です。成長戦略には、以下のようなタイプがあります。
市場浸透戦略
既存市場でのシェアを増やすための戦略。既存の製品やサービスを既存顧客に販売することを重視します。
製品多様化戦略
新しい製品やサービスを開発し、既存顧客や新規顧客に提供するための戦略。
地域拡大戦略
新しい地域や国に事業を拡大するための戦略。国際市場への進出や海外展開が含まれます。
競争戦略
競争戦略は、企業が競合他社との競争を管理し、競争優位を確立するための戦略です。競争戦略には、以下のようなタイプがあります。
コストリーダーシップ戦略
低価格戦略を採用し、コスト競争力を強化する戦略。
差別化戦略
独自の製品やサービスを提供し、顧客に付加価値を提供することで競争優位を確立する戦略。
集中戦略
特定の市場セグメントや地域に焦点を当て、その分野でのリーダーシップを目指す戦略。
存続戦略
存続戦略は、企業が経済的な困難や市場の変化に対処し、事業の存続を確保するための戦略です。
再構築戦略
事業の再構築や改革を通じて、経済的な困難や経営課題に対処する戦略。
撤退戦略
不採算事業や低収益事業からの撤退を含む、事業ポートフォリオの見直しを行う戦略。
イノベーション戦略
イノベーション戦略は、企業が新しい製品やサービスを開発し、競争力を強化するための戦略です。
技術革新戦略
新しい技術やイノベーションを活用し、市場での競争優位を築くための戦略。
市場革新戦略
新しい市場を開拓し、既存市場での競争を回避するための戦略。
これらの経営戦略の種類は、企業が目標や状況に応じて柔軟に選択し、実行することで競争力を確立し、持続的な成長を実現するための手段となります。企業は、自社のビジョンや目標に合わせて適切な戦略を策定し、戦略を実行することで、市場での存在感を高め、成果を上げることが求められます。
企業における他の戦略との違い

企業における経営戦略と他の戦略との違いは、それぞれの目的や範囲、対象となる領域によって異なります。以下では、経営戦略と他の戦略(マーケティング戦略、オペレーション戦略、人事戦略、財務戦略)の違いについて詳しく説明します。
経営戦略
目的
経営戦略は、企業の全体的な方向性や長期的な目標を設定し、競争力を強化するための戦略です。経営戦略は、企業のビジョンや目標に基づいて策定され、経営者や経営陣によって立案されます。
範囲
経営戦略は企業全体を対象としており、事業戦略や機能戦略などのサブ戦略を含みます。経営戦略は、外部環境や内部状況を踏まえて企業の方向性を定めるため、全体的な視点が求められます。
マーケティング戦略
目的
マーケティング戦略は、顧客に対する価値提供や市場シェアの拡大を目指して策定される戦略です。マーケティング戦略は、製品やサービスの価値を最大化し、顧客ニーズに合致する市場展開を実現します。
範囲
マーケティング戦略は、主に製品やサービスの販売促進や顧客獲得、ブランド戦略などに焦点を当てます。マーケティング戦略は、市場分析や顧客セグメンテーションなどの手法を用いて、市場における競争優位を確立します。
オペレーション戦略
目的
オペレーション戦略は、企業の生産や業務プロセスの効率化や改善を目指す戦略です。オペレーション戦略は、生産性の向上やコスト削減、品質管理などの目標を達成するために策定されます。
範囲
オペレーション戦略は、主に製造業やサービス業における生産プロセスや供給チェーンに関連する戦略です。オペレーション戦略は、生産計画や在庫管理、生産技術の選択などの活動を組織的に管理し、企業の業績向上に寄与します。
人事戦略
目的
人事戦略は、人材の獲得、育成、配置などを通じて組織の人材資源を最大限に活用し、企業の成長や競争力を支援するための戦略です。人事戦略は、組織文化の形成や従業員の満足度向上などの目標を達成します。
範囲
人事戦略は、組織内の人材に関するあらゆる側面に影響します。採用戦略、トレーニングプログラム、キャリア開発、給与制度などの活動を通じて、組織の人材戦略を実行します。
財務戦略
目的
財務戦略は、企業の資金調達、投資、資本構造などの財務活動を最適化し、企業価値の最大化を目指す戦略です。財務戦略は、企業の収益性や資金効率を向上させるために策定されます。
範囲
財務戦略は、企業の資金管理や財務リスク管理、財務報告などの活動に関連します。資金調達の方法や運用方針、資本予算などの意思決定を通じて、財務戦略を実行します。
これらの戦略は、企業の異なる側面に影響し、それぞれの目標や重点に応じて異なる役割を果たします。経営戦略は企業の全体的な方向性を決定し、他の戦略と連携して組織全体の成果を最大化するための枠組みを提供します。一方で、他の戦略は経営戦略の実現に向けて具体的な活動を実行し、組織の様々な側面を効果的に管理します。
経営戦略の立て方とポイント

経営戦略を立てる際の方法やポイントについて解説します。経営戦略の策定は企業の将来の方向性や目標を決定する重要なプロセスであり、以下のステップやポイントに従うことで効果的な経営戦略を策定することができます。
現状の分析
経営戦略を策定する最初のステップは、現在の状況を詳細に分析することです。内部環境と外部環境の両方を考慮し、企業の強みや弱み、機会や脅威を把握します。これには、SWOT分析(Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats)やPESTLE分析(Political、Economic、Social、Technological、Legal、Environmental)などのツールを使用します。
ビジョンと目標の設定
次に、企業のビジョンや目標を明確に定義します。ビジョンは企業が長期的に達成したい状態を示し、目標はそのビジョンに向かって進むための具体的な目標を設定します。これらのビジョンや目標は、経営戦略の基盤となります。
市場分析
競合状況や顧客のニーズ、市場動向などの情報を収集し、市場分析を行います。競合他社の戦略や顧客の行動パターンを理解し、市場での競争力を評価します。また、市場の成長性や変化にも注目し、戦略の柔軟性を確保します。
戦略の選択
現状の分析と市場分析を踏まえて、適切な戦略を選択します。市場シェアの拡大、製品やサービスの差別化、コストリーダーシップ、成長戦略など、企業のビジョンや目標に合った戦略を選択します。また、複数の戦略を組み合わせることも考慮します。
戦略の実行計画の策定
戦略を実行するための具体的な計画を策定します。目標の設定、タイムラインの決定、責任者の割り当て、リソースの確保など、戦略を実行するために必要なすべての要素を明確にします。また、戦略の実行計画は定期的に見直し、調整することが重要です。
組織の関与とコミュニケーション
経営戦略の策定には、組織全体の関与とコミュニケーションが不可欠です。経営者や経営陣だけでなく、組織内の関係者や従業員とも意見交換を行い、戦略に対する理解と共感を得ます。透明性とオープンなコミュニケーションが戦略の成功に不可欠です。
リスク管理と変更管理
戦略の実行中にはさまざまなリスクが発生する可能性があります。リスクを事前に予測し、適切な対策を講じることが重要です。また、市場や競争環境の変化に対応するために、戦略を柔軟に調整し、適宜変更を行うことも必要です。
成果のモニタリングと評価
戦略の実行中は、定期的に進捗状況をモニタリングし、成果を評価します。定量的な指標やKPI(Key Performance Indicators)を使用して、目標達成度や戦略の効果を評価し、必要に応じて修正を行います。
持続可能性と成長戦略
経営戦略は持続可能な成長を実現するための枠組みであるべきです。戦略の実行が一時的なものではなく、長期的な成果を生み出すことが重要です。また、成長戦略の適用を通じて、市場や競合状況の変化に適応し、競争力を維持することも考慮します。
学習と改善
経営戦略の策定や実行から得られた教訓を反映し、戦略の改善を行います。過去の経験や失敗から学び、次の戦略の策定や実行に生かすことで、持続的な改善と成長を促進します。
これらのステップとポイントに従うことで、経営戦略の策定と実行を効果的に行うことができます。経営者や経営陣は、組織全体のビジョンや目標を明確にし、関係者との協力やコミュニケーションを通じて戦略を成功させることが求められます。
押さえておきたいフレームワーク

経営戦略を構築する上で押さえておきたいフレームワークには、いくつかの重要な概念やモデルがあります。これらのフレームワークを理解し、活用することで、経営戦略の策定や実行をより効果的に行うことができます。以下では、押さえておきたい主要なフレームワークについて解説します。
SWOT分析
SWOT分析は、企業の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を評価するためのフレームワークです。組織の内外環境を分析し、戦略策定に役立つ情報を提供します。強みと弱みは内部要因であり、機会と脅威は外部要因です。
PESTLE分析
PESTLE分析は、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)、法的(Legal)、環境(Environmental)の6つの要因を評価するツールです。経営環境の変化や影響を理解し、戦略策定に適した方針を立てるのに役立ちます。
5つの競争フォース(Porterの競争戦略)
マイケル・ポーターによる競争戦略のフレームワークでは、競争の激しさを5つの力で分析します。これには、業界内の競争、新規参入の脅威、代替品の脅威、顧客の交渉力、サプライヤーの交渉力が含まれます。このフレームワークを使用して、競争優位性を確立するための戦略を策定します。
コアコンピタンスとコアリジッドネス
コアコンピタンスは、企業が他社との競争上の優位性を持つために必要な独自の能力やリソースです。一方、コアリジッドネスは、過度に固定化されたコアコンピタンスが企業の成長や変化を妨げる状態を指します。経営戦略を策定する際には、コアコンピタンスを活用し、コアリジッドネスを回避することが重要です。
成長戦略(アンソフの成長マトリックス)
アンソフの成長マトリックスは、企業の成長戦略を4つのカテゴリーに分類します。市場浸透、市場開発、製品開発、多角化です。このモデルを使用して、企業の成長戦略を理解し、戦略的な選択を行います。
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業の価値創造プロセスを理解し、活動をプライマリとサポートに分類します。プライマリ活動は、製品の生産や販売などの直接的な価値創造に関わる活動です。サポート活動は、プライマリ活動を支える裏方の活動です。バリューチェーン分析を通じて、企業の競争優位性を特定し、戦略を改善します。
BCGマトリックス
BCGマトリックスは、企業の製品ポートフォリオを成長率と市場シェアの観点から分析します。製品を「成長率」「市場シェア」の2つの軸に沿って四つのセルに分類し、各製品の戦略を決定します。これにより、製品のポジショニングや資源配分を最適化し、成長を促進します。
バリュープロポジション(価値提案)
バリュープロポジションは、顧客に提供する価値や利点を明確に定義することを指します。顧客ニーズや要求を理解し、製品やサービスの独自性や価値を示すことで、競争優位性を獲得します。バリュープロポジションを明確にすることで、顧客の満足度やロイヤルティを高めることができます。
ブルーオーシャン戦略
ブルーオーシャン戦略は、競争の激しい「赤い海」ではなく、新しい市場や産業を創造する「青い海」を探求する戦略です。競合他社との差別化や新しい市場領域の発見に焦点を当て、市場に革新的な価値を提供します。これにより、競争を回避し、成長と利益を実現します。
リーダーシップと文化
経営戦略を策定し実行する際には、リーダーシップと組織文化が重要です。リーダーシップは、ビジョンや方針を明確にし、組織のメンバーを統率し、目標達成に向けて方向を示す役割を果たします。また、組織文化は、組織の価値観や行動規範に基づいて行動するための枠組みを提供し、経営戦略の実行をサポートします。
これらのフレームワークを活用することで、経営戦略の策定や実行に関する理解を深め、企業の競争力や持続可能な成長を実現することができます。経営者や経営陣は、これらの概念やモデルを組織内に導入し、戦略的な意思決定を行うための有用なツールとして活用すべきです。
経営戦略の企業事例

経営戦略の成功事例として、アメリカのテクノロジー企業であるApple Inc.(アップル)を取り上げます。アップルは、創業者のスティーブ・ジョブズを中心に、革新的な製品や顧客中心のアプローチ、強力なブランド戦略を展開し、世界的な成功を収めています。
製品の差別化と革新
アップルは、製品のデザイン、機能、ユーザーエクスペリエンスにおいて常に革新を追求してきました。最初の成功製品であるApple IIやMacintoshから始まり、後にiPod、iPhone、iPadなどの製品を開発・発売しました。これらの製品は、使いやすさ、デザイン性、革新性において他社の追随を許さないものであり、顧客に高い価値を提供しています。
エコシステムの構築
アップルは、製品やサービスのエコシステムを構築することで顧客のロックインを図っています。iTunes、App Store、iCloudなどのサービスを提供し、複数の製品をシームレスに連携させることで、顧客がアップルの製品を利用する際の利便性や価値を高めています。このエコシステムは、顧客の忠誠心を高め、新たな収益源を生み出す役割を果たしています。
顧客中心のアプローチ
アップルは、顧客のニーズや要求に常に耳を傾け、製品やサービスの開発に反映させることで顧客満足度を高めています。例えば、iPhoneの開発においては、多くの市場調査や顧客フィードバックを元に、使いやすさや機能性を追求しました。顧客の声に真摯に対応する姿勢は、顧客との信頼関係を築く上で重要な要素です。
ブランド戦略の構築
アップルは、強力なブランドイメージを構築し、顧客の心に深く根付いています。製品の品質、デザイン、革新性に加えて、マーケティング戦略や広告活動においても独自のアプローチを取り、ブランド価値を高めています。アップル製品は、単なる技術の一部ではなく、ライフスタイルやアイデンティティの一部として捉えられています。
グローバル展開
アップルは、世界中の多くの国や地域で製品を販売し、グローバルな市場に進出しています。地域ごとの需要や文化に合わせて製品ラインナップやマーケティング戦略を調整し、地域ごとの顧客ニーズに最適な製品を提供しています。グローバル展開は、アップルの収益の多様化や成長の源泉となっています。
以上の要因により、アップルは産業のリーダーとしての地位を確立し、顧客からの支持を獲得しています。アップルの経営戦略の成功は、製品の革新性と品質、顧客中心のアプローチ、強力なブランド戦略、グローバル展開などの要因に起因しています。経営戦略の実行においてこれらの要素を総合的に活用することが、企業の成長と競争力の向上に不可欠であることを示しています。
今から経営戦略を学ぶ方におすすめの書籍
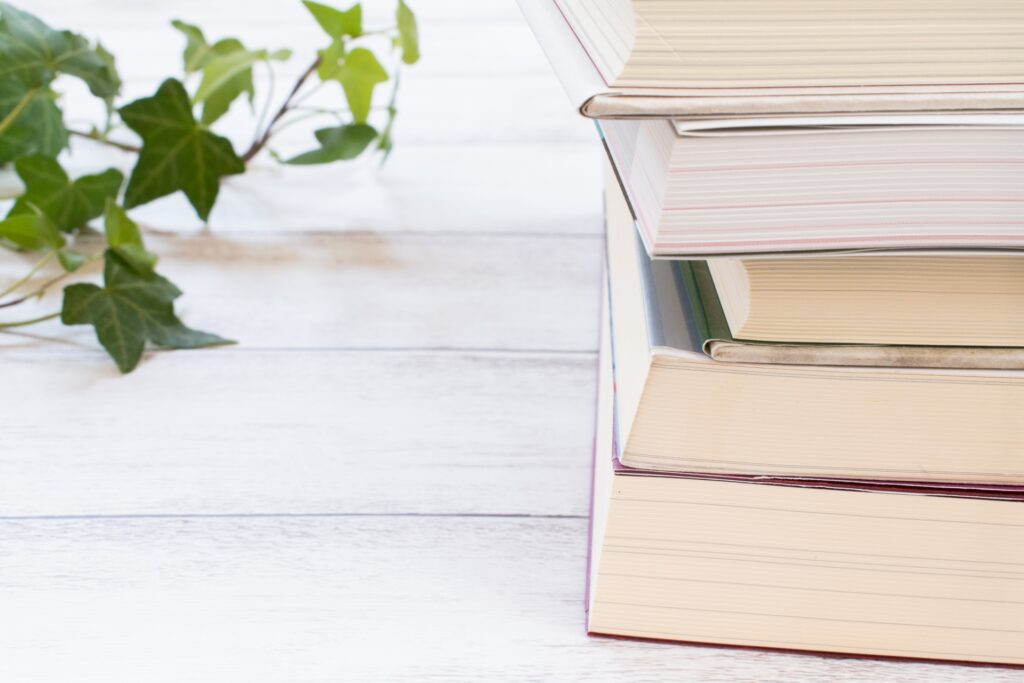
経営戦略を学ぶための書籍は、幅広いトピックをカバーしており、初心者から上級者までさまざまなニーズに対応しています。以下は、経営戦略を学ぶ方におすすめの書籍を紹介します。
『競争戦略』(マイケル・ポーター著)
マイケル・ポーターによる不朽の名著であり、競争優位を築くための基本的な枠組みを提供しています。産業の構造や競争力、戦略的位置付けについて詳しく解説しています。
『経営戦略入門』(ジョン・A・ピーティ著)
経営戦略の基本的な概念や理論を分かりやすく解説した入門書です。初学者にとって理解しやすい内容であり、経営戦略の基礎を学ぶのに最適です。
『経営戦略の原則』(ピーター・ドラッカー著)
ピーター・ドラッカーの著作であり、経営学の基本的な原則や実践的なアドバイスが豊富に含まれています。経営者やビジネスリーダーにとって、必読の書とされています。
『ビジネスモデル新論』(アレクサンダー・オスターワルダー著)
ビジネスモデルの設計と革新に焦点を当てた書籍であり、ビジネスモデルの理解と設計に関する革新的なアプローチを提供しています。
『経営戦略の論理』(C・K・プラハラド、ガリ・ハムル著)
経営戦略の新たな視点やアプローチを提供する書籍であり、ビジネスの未来を考える上で重要な知識を提供しています。
『ブルーオーシャン戦略』(W・チャン・キム、レネ・ボルグボー著)
新しい市場を開拓し、競合他社との直接的な競争を回避するための戦略であるブルーオーシャン戦略に焦点を当てた書籍です。
『イノベーションと経営戦略』(クライトン・クリステンセン著)
クライトン・クリステンセンによるイノベーションと経営戦略の関連性について解説した書籍です。イノベーションを経営戦略に組み込む方法について学ぶことができます。
『ストーリーでわかるビジネスモデル』(ティム・クラーク著)
ストーリーテリングの手法を用いて、ビジネスモデルの概念や実践的な活用方法を解説した書籍です。
『戦略の論理』(リチャード・P・ランブル著)
戦略的思考の重要性や戦略の論理について深く掘り下げた書籍であり、戦略的な意思決定に役立つ考え方が提供されています。
『デジタル戦略』(マーティン・レイヴンズタイン著)
デジタルテクノロジーの進化が企業経営に与える影響や、デジタル戦略の設計や実行について解説した書籍です。
これらの書籍は、経営戦略を学ぶ上で非常に有益な情報を提供しています。それぞれの書籍が異なる視点やアプローチを提供しており、経営戦略の理解と実践に役立つことでしょう。
まとめ
経営戦略は、企業が長期的な目標を達成し、競争力を維持・強化するための計画や方針を指します。経営戦略の策定には、企業のビジョンや目標を明確化し、外部環境や市場の動向を分析し、自社の強みや弱みを把握するプロセスが含まれます。経営戦略は、競合他社との差別化や市場での優位性を確保するための戦略を含み、企業の成功と成長に不可欠です。経営戦略は簡単にできるものではありませんので、途中で諦めず何度もトライするうちに自社に合った戦略が見えてくるはずです
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 組織マネジメント2024年6月26日データドリブン経営とは?そのメリットと 実現する方法や注意点を解説
組織マネジメント2024年6月26日データドリブン経営とは?そのメリットと 実現する方法や注意点を解説 組織マネジメント2024年6月25日社内に求められるデータ分析の役割や活用法、便利なツールについて解説
組織マネジメント2024年6月25日社内に求められるデータ分析の役割や活用法、便利なツールについて解説 組織マネジメント2024年6月24日2024年の人事トレンド!企業が取り組むべき人事対策について解説
組織マネジメント2024年6月24日2024年の人事トレンド!企業が取り組むべき人事対策について解説 組織マネジメント2024年6月23日組織開発とは?組織開発のメリットや役立つ手法やフレームワークについて解説
組織マネジメント2024年6月23日組織開発とは?組織開発のメリットや役立つ手法やフレームワークについて解説
コメント