多くの企業が直面する「思ったように組織が動かない」という課題。その背景には、マネジメントやコントロールの理解不足が潜んでいるかもしれません。本コラムでは、「マネジメントとは何か?」という基本から始め、組織を適切にコントロールするための具体的手法やメリット・デメリットをわかりやすく解説しています。
< このコラムでわかる3つのポイント >
1.組織運営におけるマネジメントコントロールの考え方と実践方法
2.状況に応じたマネジメントコントロール手法の種類と特徴
3.マネジメントコントロールがもたらす組織全体への波及効果
Contents
マネジメントコントロールとは
「マネジメントコントロール」という言葉を耳にすることが増えてきましたが、その意味を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。単なる業務の監視や報告体制とは異なり、組織の目的達成に向けて「人・プロセス・成果」を意図的に動かす仕組みのことを指します。言い換えれば、経営者や管理職が“組織を正しい方向に導くための操縦装置”とも言える存在です。
マネジメントとコントロールの違いとは?
まず整理しておきたいのが、「マネジメント」と「コントロール」の違いです。マネジメントは計画・実行・評価・改善といった一連のプロセスを指し、全体を管理・運営していく枠組みです。一方でコントロールは、その中の「評価・改善」の領域にフォーカスされます。具体的には、KPIの達成度や業務プロセスの進捗、メンバーの行動のズレを検知し、必要な修正を加えるプロセスが該当します。
つまり、マネジメントは「大局的な指揮」、コントロールは「軌道修正と是正処置」と捉えるとわかりやすいでしょう。マネジメントが戦略・設計図だとすれば、コントロールはその通りに進んでいるかをモニタリングし、道から外れたら戻すための舵取り役です。
なぜマネジメントコントロールが重要なのか?
経営計画や戦略を立てることは比較的多くの企業が行っていますが、それを現場レベルまで浸透させ、継続的に実行し、成果へとつなげるには「マネジメントコントロール」が欠かせません。なぜなら、戦略が現場で形骸化してしまうケースが非常に多いからです。たとえば、売上目標は明示されているが、それを日々の業務や社員の行動レベルでどう実現するかが明確でない。そのギャップを埋めるのがコントロールの役割です。
このように、マネジメントコントロールは「戦略と行動をつなぐ橋渡し」として機能します。プロジェクト単位でも、全社的な業務運営でも、適切に設計・運用されることで組織全体の一体感や成果の再現性を高めることが可能です。
実務におけるマネジメントコントロールの構成要素
実際の現場では、以下のような構成でマネジメントコントロールが設計されます。これらを有機的に組み合わせ、定期的に見直すことで、持続的かつ柔軟なマネジメントが可能となります。
- 目標の明確化(目的)
- 評価指標の設定(KPI/KGI)
- モニタリング手段(システムや会議体)
- フィードバック体制(レポート・1on1など)
- 是正処置(改善提案・組織変更)
マネジメントコントロールのメリット

マネジメントコントロールを導入することで、組織運営にどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。以下では、その代表的な利点を整理していきます。
組織全体の行動が成果に直結する
マネジメントコントロールの最大の利点は、「行動と成果が結びつきやすくなる」という点です。多くの企業が戦略を立てながらも、現場での実行が伴わないという問題を抱えています。これを改善するには、行動の先にある成果指標を設定し、進捗を継続的にモニタリングする仕組みが欠かせません。個々の業務が組織目標とどのようにつながっているかを見える化することで、従業員一人ひとりのモチベーション向上にもつながります。
経営層と現場の情報ギャップを埋める
部門間の連携不足や、上司・部下間の認識のズレは、日常的に発生します。マネジメントコントロールでは、定期的なモニタリングやフィードバックを通じて、こうした情報のギャップを最小限に抑えることができます。経営の意思がスムーズに現場へ届き、逆に現場の声も適切に経営に反映される環境が整うのです。情報共有をベースにした信頼関係が築かれ、組織全体の心理的安全性にも好影響をもたらします。
属人的な判断を排除し、再現性のある業務遂行が可能に
従来の業務運営では、優秀な個人に頼る場面が多くありました。しかし、マネジメントコントロールによって明確なルール・プロセスが設けられることで、誰が担当しても一定の成果を上げやすい状態がつくられます。これは「成果の再現性」を高め、組織としてのパフォーマンスを安定させる要因となります。また、属人化を排除することは、業務の引き継ぎや人材育成の円滑化にも直結します。
改善のPDCAサイクルが自然と回る
評価・モニタリング・フィードバック・是正というコントロールの要素は、PDCAサイクルを自然に回す土台になります。特に、定量的なデータに基づくフィードバックが中心となるため、感覚に頼らず、論理的・客観的に改善が行える点がメリットです。数字に基づく管理は、感情的なトラブルを回避する効果もあり、組織運営をより理性的なものにします。
このように、マネジメントコントロールは企業の規模や業種を問わず導入効果の高い仕組みです。業務の属人化、現場との乖離、改善の停滞といったよくある課題に対して、構造的なアプローチで解決を図ることができます。導入初期は負担に感じられることもあるかもしれませんが、長期的には安定性・効率性・信頼性を兼ね備えた組織運営の基盤となるでしょう。
マネジメントコントロールのデメリット
マネジメントコントロールには多くのメリットがある一方で、導入や運用の仕方によっては、いくつかのデメリットが生じる可能性もあります。以下では、その代表的な注意点を解説します。
組織に硬直性が生まれる可能性
マネジメントコントロールは、業務プロセスや行動を標準化・明確化することによって成果を高める仕組みです。しかしそれが過度になると、従業員の創造性や柔軟性を抑制してしまうことがあります。すべての行動がルール化されることで、現場が「指示待ち」や「ルール重視」に偏り、機転の利いた対応ができなくなるリスクがあるのです。
モチベーション低下の引き金になり得る
厳格なコントロールのもとで日々の業務が評価され続けると、「監視されている」「信用されていない」と感じる従業員も出てきます。特に、定量的なKPIばかりを重視すると、数値に追われるストレスが溜まり、働きがいを失ってしまうケースも見受けられます。管理職は、評価だけでなく、信頼と裁量を与えるマネジメントとのバランスを取る必要があります。
課題解決志向が高く、目的から逆算できる人
日常の業務に流されず、常に「目的は何か」「今やっていることは目的達成にどのようにつながるのか」を考えられる人は、マネジメントに向いています。課題の本質を捉え、的確な改善策を提示できる人材は、組織にとって不可欠な存在です。また、問題発生時に感情的にならず、「どうすれば改善できるか」に目を向ける姿勢は、部下にも前向きな影響を与えます。目的志向・改善志向の高さは、成果に直結する重要な資質です。
現場の負担増加による反発
マネジメントコントロールを機能させるためには、進捗報告やデータの入力・確認、定期的なフィードバックの実施など、多くの管理業務が伴います。これにより、現場スタッフや管理職の「本来業務以外の負担」が増えることになり、制度に対する反発が生じることがあります。特に、導入初期や改善フェーズでは、定着までに時間と労力が必要です。
指標が実態を表さないリスク
KPIや数値目標は可視化に有効なツールですが、設定方法を誤ると、現場の実態とズレた評価が行われてしまうこともあります。例えば、営業件数だけを追いすぎると顧客満足度が下がる、効率性を重視しすぎて品質が落ちる、などの問題が発生します。数字だけに依存せず、「なぜこの指標が必要なのか?」を常に問い直す姿勢が重要です。
デメリットを最小限に抑えるには
マネジメントコントロールの効果を最大化しつつ、これらのデメリットを最小限に抑えるには、目的や組織文化に合った運用ルールの設計が不可欠です。また、導入にあたっては、現場の声を取り入れることや、説明責任を果たすことが、抵抗感を減らすカギとなります。トップダウン型の導入だけでなく、現場との合意形成を重視したプロセスを取り入れることが成功のポイントです。
マネジメントコントロールの3つの手法

マネジメントコントロールは、単なる業務監視や報告制度ではなく、組織の目的達成に向けて「行動」と「成果」を結びつけるための戦略的手段です。その中でも代表的な3つの手法として、「成果コントロール」「行動コントロール」「人材(文化)コントロール」が知られています。これらは互いに補完関係にあり、組織の状況に応じて組み合わせて活用することが推奨されます。
1. 成果コントロール(Results Control)
成果コントロールは、最も一般的で導入しやすい手法のひとつです。具体的には、KPIやKGIの設定、予算・売上・利益といった定量的な成果指標に基づいて、個人や部門の業績を評価・管理します。
この手法の特徴は、プロセスよりも「結果」に注目することです。したがって、個人にある程度の裁量を与え、成果だけで判断するというマネジメントスタイルにも適しています。営業職やマーケティング部門など、成果が明確に測定できる領域で特に有効です。ただし、数値だけを追うあまり、短期的な結果を重視しすぎると、顧客満足や品質向上といった中長期的な価値が軽視される恐れがあるため注意が必要です。
2. 行動コントロール(Action Control)
行動コントロールは、従業員がどのように仕事を進めるかという「プロセス」そのものを管理・監督する手法です。業務マニュアル、業務フロー、チェックリスト、ルールの明文化、定例会議などを通じて、特定の行動を推奨または禁止する仕組みが該当します。
この手法の利点は、業務の品質や安全性を確保しやすくなることです。例えば、製造業や医療、インフラ関連など、ミスが致命的になる分野では、行動コントロールが重視されます。ただし、過度なルール化や手順の強制は、従業員の創造性や主体性を阻害する原因にもなり得ます。そのため、行動の自由度とルールのバランスを適切に保つことが求められます。
3. 人材(文化)コントロール(Personnel/Cultural Control)
人材コントロールは、従業員の自律性や価値観に働きかける方法で、組織文化や職場風土を通じて望ましい行動を引き出すことを目的とします。新人研修やOJT、ミッション・ビジョンの浸透、社内表彰制度などが代表例です。
この手法は、成果や行動を数値で管理しにくい部門や、イノベーションが求められる環境で効果を発揮します。例えば、企画開発職やデザイン部門など、数値化できない価値創出が中心となる業務では非常に有効です。人材コントロールは、信頼と共感を基盤にするため、従業員のエンゲージメントを高めやすい点も特徴です。一方で、成果が出るまでに時間がかかることや、評価が曖昧になりやすいという課題もあるため、他の手法との組み合わせが推奨されます。
3つの手法の使い分けと組み合わせ
この3つの手法は、組織の成熟度や目的、部署の性質に応じて使い分けることが重要です。例えば、新人が多いチームでは「行動コントロール」を強めにし、ある程度経験を積んだメンバーには「成果コントロール」へと移行する。あるいは、企業文化を強化したいフェーズでは「人材コントロール」を重視する、といった具合です。
また、1つの手法に偏るとリスクが高まるため、複数の手法を柔軟に組み合わせるハイブリッド型のマネジメントが理想的です。例えば、「成果に至るプロセスをマニュアル化(行動コントロール)しつつ、最終的な業績も評価(成果コントロール)する」といった運用が現実的です。
自社の現状や課題に応じて、どの手法をどの程度採用するかを見極め、戦略的にマネジメントコントロールを設計することが成功の鍵となります。
マネジメントコントロールにおける情報共有の重要性
マネジメントコントロールを有効に機能させるためには、制度や評価基準の整備と同じくらい、「情報共有の質と量」が極めて重要です。どれだけ優れた仕組みや目標を設計しても、それが現場に伝わらず、各人の理解や行動に結びついていなければ、成果にはつながりません。
この章では、情報共有がマネジメントコントロールの成功を左右する理由と、実践のポイントについて解説します。
情報の非対称性がもたらす弊害
組織内には、立場や役割によってアクセスできる情報に偏りがあります。これを情報の非対称性と呼び、マネジメントにおける大きな障害となります。例えば、経営層は戦略的な全体像を把握していても、現場にはその意図が伝わっていない。一方で、現場の課題や顧客のリアルな声は、上層部まで届いていない。こうした情報の断絶が続くと、組織は誤った前提で動き、無駄な作業や的外れな施策が増加します。
マネジメントコントロールにおいては、「何を目指しているのか」「どう評価されるのか」「どのように行動すべきか」を、組織の全メンバーが同じ前提で理解している状態が理想です。その実現の鍵が、適切な情報共有の仕組みなのです。
情報共有の3つの目的
マネジメントコントロールにおける情報共有には、主に以下の3つの目的があります。これらを意識した情報共有ができていれば、マネジメントコントロールの精度は飛躍的に高まります。
- 目標と方針の共通認識化
組織として何を達成すべきか、どのような基準で評価されるのかを明確に伝えること。 - 進捗と結果の可視化
行動の結果がどう評価され、どこに改善の余地があるのかを示し、軌道修正を促すこと。 - 双方向のコミュニケーションによる信頼醸成
トップダウンの情報だけでなく、現場からのフィードバックを収集・反映することで、制度への納得感と協力体制をつくること。
情報共有の質を高める具体策
マネジメントコントロールに必要な情報共有を実現するには、日常業務の中に組み込むことが鍵です。以下に実践的な取り組みを紹介します。情報共有はツールや仕組みで補完できる部分が多くありますが、最終的には「誰に、何を、どう伝えるか」という意識の統一が必要不可欠です。
- 定例会議・進捗報告の見直し
会議の頻度や形式を見直し、ただの報告会に終わらせず、課題発見と対話の場にする工夫が必要です。 - OKRやKPIの可視化ツールを活用する
目標と進捗を「見える化」することで、誰がどこまで進んでいるのかが一目で分かるようになり、行動のズレを早期に修正できます。 - 社内チャットやナレッジ共有ツールの活用
日常的なやり取りをオープンにすることで、横断的な情報連携や気づきが生まれやすくなります。 - 1on1やフィードバック面談の定期化
数字だけでなく、「どう感じているか」「何に困っているか」といった現場の声を拾い上げる時間を確保しましょう。
情報共有が文化になると、コントロールは強化ではなく“自走”へ

自律的な組織を生み出す「情報の共有文化」
マネジメントコントロールというと、「監視」「評価」といったネガティブなイメージを持たれることがあります。しかし、情報共有が活発で、目的や行動指針が浸透している組織では、管理されなくても個々が正しい行動を選択する“自律的な組織”が形成されます。
この状態こそが、マネジメントコントロールが最終的に目指す理想像です。つまり、強制的にコントロールするのではなく、自然と成果につながる行動がとれる状態をつくること。
そのためには、ルールや数値だけでなく、「情報」が共通財産として全員に行き渡っている必要があります。
双方向の仕組みが組織の推進力になる
マネジメントコントロールを強化するうえで、情報共有の質と量を高めることは避けて通れないテーマです。 一方的な報告や指示だけでは不十分で、組織の全員が同じ方向を見て動ける状態をいかに構築できるかが鍵となります。そのためには、「伝える」「受け取る」「返す」までを含んだ双方向のコミュニケーション設計が不可欠です。
情報が正しく循環していれば、現場で起きている変化や課題にも迅速に対応でき、結果としてコントロールは“管理”から“信頼と連携”へと進化します。
まとめ
マネジメントとコントロールは、組織運営を成功に導くための中核的な考え方です。どれほど優れた戦略があっても、現場が動かなければ成果にはつながりません。だからこそ、個人やチームの行動をどうマネジメントし、どうコントロールしていくかが非常に重要になります。
本コラムでは、具体的な手法や考え方、実践上の注意点までを幅広くご紹介しました。重要なのは、画一的な管理ではなく、組織や状況に合わせて柔軟に対応することです。今一度、自社のマネジメント体制を見直し、よりよい組織づくりに向けた一歩を踏み出すきっかけとして、本内容が少しでもお役に立てば幸いです。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

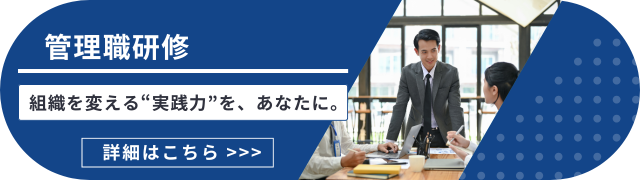


コメント