現代の職場では、業績や専門性だけではなく、人間関係を円滑に保つ力=コミュニケーション能力が管理職に強く求められています。
本コラムでは、管理職とは何かという基本から始まり、役割、求められるスキル、よくある失敗例、そしてコミュニケーション力を高める具体的な方法までを体系的に解説します。「話す力」だけでなく「聴く力」「伝わる力」「共感力」を備えた管理職が、これからの組織の信頼と成果をつくります。実践的なヒントも多数紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
< このコラムを読むことでわかる3つのポイント >
1.管理職に求められるコミュニケーションの本質
2.職場で活きる管理職のための実践的なコミュニケーション技法
3.部下との信頼関係を築くための対話の工夫と心がけ
Contents
管理職の定義とは
企業組織において「管理職」という役職は多く存在しますが、その明確な定義を理解している人は意外に少ないかもしれません。一般的に管理職とは、一定の権限と責任を持ち、部下を指導・統括しながら、組織全体の目標達成に貢献するポジションを指します。しかし、単に「部下を持っている人」「役職がついている人」という表面的な理解では、その本質を捉えきれません。
管理職の基本的な役割
管理職は大きく分けて、次のような役割を担っています。これらの業務は、一般社員と比べて「自律性」「判断力」「影響力」が強く求められるため、管理職は「企業運営の中核」として位置づけられます。
- 業務管理:部署やチームの目標達成に向けた戦略立案、進捗管理、成果の評価など
- 人材マネジメント:部下の指導・育成、モチベーションの維持、評価や処遇の判断
- 組織間調整:他部署や上層部との連携、情報共有、トラブル対応
- 業績責任:自部門の成果に対する責任を負い、結果にコミットする姿勢が求められる
管理職と一般職の違い
管理職と一般職の最も大きな違いは「成果の出し方」にあります。一般職は自身の業務遂行によって成果を出しますが、管理職は「チームや部門を通じて成果を上げる」ことが使命です。そのためには、単に指示を出すだけでなく、メンバーの特性を理解し、適切に動機づけ、成長を促す必要があります。
また、企業によっては、一定の役職(課長以上など)になると、労働基準法上の「管理監督者」として扱われ、残業代の支給対象外となるケースもあります。こうした法律面での扱いも、管理職の定義の一部として理解しておくことが重要です。
管理職の定義が曖昧になりやすい背景
近年、フラットな組織構造やプロジェクト型の働き方が広がる中で、役職と実態が一致しないケースも増えています。肩書き上は「マネージャー」でも、部下を持たずプレイヤー業務に専念している人もいれば、正式な役職はないが実質的にチームを取りまとめている人もいます。こうした状況が、管理職の定義を曖昧にする要因となっています。したがって、形式的なポジションではなく、「組織における役割」や「果たしている機能」で判断する姿勢が求められます。
管理職の定義とコミュニケーションスキルの関係
定義を踏まえると、管理職には「人を動かす」「組織の意思を伝える」「多様な人間関係を調整する」といった能力が不可欠です。これらはすべて、コミュニケーションスキルに密接に関わるものです。
つまり、管理職の本質は「人と組織をつなぐハブ」であることであり、その要となるのがコミュニケーション能力だと言えるでしょう。
管理職の役割

管理職は、単に「部下を持つ人」や「業務を取りまとめる人」ではありません。組織における管理職の役割は、会社の方針と現場の実行をつなぐ「要」として、非常に多岐にわたります。本章では、管理職に求められる主な役割について解説しながら、その重要性を明確にしていきます。
組織目標の実現に向けたマネジメント
管理職の第一の役割は、所属部署やチームの目標達成に向けたマネジメントです。経営層から提示される組織のビジョンや戦略を、自部門の業務に落とし込み、日々の業務の中で具体的な成果につなげていく必要があります。特に、部門間で利害がぶつかるような場面においては、冷静かつ論理的な判断力と交渉力が求められます。管理職には、以下のようなタスクが求められます。
- 業務計画の策定
- 進捗状況の確認と軌道修正
- 部門横断的な調整
- KPI(重要業績評価指標)の管理
人材育成とチームビルディング
人を育てることは、管理職の最も重要な役割の一つです。単なるOJTや指示命令ではなく、部下の成長を見据えた育成計画やフィードバック、キャリア支援を通じて、個々のポテンシャルを引き出す姿勢が必要です。
また、成果を出すためには、個人ではなく「チーム」として機能させることが不可欠です。多様な背景・価値観を持ったメンバーをまとめ、一体感あるチームを作り上げる力、すなわちチームビルディング能力が問われます。その際、以下のような取り組みが効果的です。
- 定期的な1on1ミーティングの実施
- メンバーの強みや関心に基づいた業務配分
- 成果だけでなくプロセスも評価する風土づくり
コミュニケーションのハブとしての機能
管理職は、上司と部下、他部門、経営層、顧客など、様々なステークホルダーと日常的にやり取りをします。このような多様な立場の間を取り持つには、情報の「受け取り方」「伝え方」「フィードバックの仕方」に関する高度なコミュニケーションスキルが不可欠です。
ここで重要なのは、一方的な伝達ではなく、「双方向の対話」をベースにしたコミュニケーションを実践することです。具体的には、以下のようなシーンでその力が試されます。
- 経営陣からの意図を現場に適切に伝える
- 部下の意見や不満を吸い上げ、必要に応じて上層部へ報告する
- トラブルやクレームの初動対応・調整
- 多様な価値観の中での意思決定
モチベーション管理と心理的安全性の確保
部下のパフォーマンスを最大限に引き出すには、単に目標を与えるだけでは不十分です。モチベーションの源泉は人によって異なるため、管理職には一人ひとりの性格や価値観を理解したうえでの「個別対応」が求められます。
また、近年では心理的安全性の重要性が注目されています。失敗や意見表明を恐れず、安心して仕事に取り組める環境を作ることは、イノベーションや主体性を生む土台となります。
管理職自身が感情的にならず、冷静であること、ミスを責めずに次への改善を促す姿勢を示すことが、その環境づくりには不可欠です。
現場課題の可視化と経営への提言
最後に、管理職は現場に最も近い視点を持つ存在でありながら、経営層との接点も多いという特性を活かし、「現場課題を経営課題として翻訳し、提言する」役割も担っています。
これは、経営と現場を橋渡しする立場としての重要な役割であり、組織全体の持続的な成長に貢献するために不可欠な視点です。
管理職のコミュニケーションが重要な理由

企業活動のあらゆる場面において、コミュニケーションは必要不可欠な要素です。中でも、組織の中核を担う管理職にとって、コミュニケーションは「仕事の手段」ではなく「成果を生み出す根幹」となるスキルです。
管理職にとってコミュニケーションスキルは、単なる能力の一つではなく、組織を動かすための最も根本的な資質です。それは、情報の伝達、信頼関係の構築、問題の予防、個別対応、文化形成といった多面的な影響を持ち、業績にも直結する極めて重要な要素と言えるでしょう。
ここでは、なぜ管理職にとってコミュニケーションがこれほど重要視されるのか、その理由を多角的に解説します。
組織の方向性を浸透させるため
企業には、ビジョン、ミッション、戦略、目標など、全体として進むべき方向性があります。しかし、それが現場の一人ひとりにまで正しく理解・共有されていなければ、組織はまとまらず、成果にもつながりません。ここで鍵を握るのが、管理職による「伝達力」です。経営層から伝えられた方針や目標を、自部署に合わせた言葉に変換し、メンバーに納得感を持たせながら説明できるかが求められます。
この「翻訳能力」ともいえる役割は、単なる情報の伝達ではなく、意味づけと動機づけをセットで行うコミュニケーションである必要があります。
部下との信頼関係を築くため
管理職にとって、部下との信頼関係はマネジメントの土台です。信頼がなければ、指示が形だけになり、報連相も滞り、チームとしての機能が低下します。では、どうすれば信頼関係を築けるのでしょうか?
そのカギは「日常的なコミュニケーションの質」にあります。以下の積み重ねが、心理的な安全性を育み、信頼関係の構築につながります。
- 日々の声かけや1on1ミーティングを通じて、部下の関心や悩みを把握する。
- 業務指示だけでなく、成果へのフィードバックや感謝の言葉を伝える。
- 説教や命令ではなく、「対話」で部下の考えを引き出す。
問題の早期発見と対応
現場で起こる課題やトラブルは、必ずしも上司の目に見える形で表面化してくるとは限りません。部下が自発的に問題を報告できる環境があってこそ、早期発見と適切な対応が可能になります。
そのためには、部下が「相談しても大丈夫」「報告しても否定されない」と思える関係性が不可欠です。これは、普段から傾聴と受容の姿勢を持ち、どんな内容にも冷静に向き合う管理職の姿勢によって築かれます。つまり、トラブルを未然に防ぐリスクマネジメントの観点からも、管理職のコミュニケーション力は極めて重要です。
多様な価値観をまとめるリーダーシップ
現代の職場は、世代、性別、国籍、働き方など、価値観が多様化しています。その中で、ひとつの方向にチームをまとめていくには、一律の指示命令型では機能しなくなってきているのが実情です。管理職は、それぞれのメンバーの違いを理解し、適切な距離感とアプローチで関わる必要があります。
たとえば、若手社員には共感とフィードバックを重視し、中堅社員には裁量と信頼をもって任せる、といったように、「伝え方を変える」柔軟性が求められます。これは「個別最適化されたコミュニケーション」とも言え、まさにマネジメント力そのものです。
組織文化をつくる影響力
管理職は、組織文化の“体現者”でもあります。言葉遣い、態度、意思決定の仕方、部下への対応 などが、周囲に大きな影響を及ぼします。
たとえば、上司が他部署との連携を軽視すれば、部下も閉鎖的な行動を取るようになりかねません。逆に、オープンで誠実なコミュニケーションを重んじる上司がいれば、チーム全体にその姿勢が浸透していきます。つまり、管理職のコミュニケーションは、「何を言うか」以上に「どう言い、どう接するか」が組織全体の風土を左右するのです。
管理職に求められるコミュニケーション能力

管理職にとって、コミュニケーション能力は単なる「話し上手」や「聞き上手」だけではありません。チームを統率し、目標を達成に導くうえで不可欠な「戦略的なスキル」として求められます。ここでは、管理職に必要なコミュニケーション能力の種類と、それぞれの実践方法について解説します。
傾聴力(アクティブリスニング)
まず最も基本かつ重要なのが「傾聴力」です。部下との信頼関係を構築するうえで、相手の話をしっかり「聞く」ことは大前提です。しかし、ただ黙って聞いているだけでは不十分で、「理解しようとする姿勢を示す」ことが重要です。たとえば、以下のような対応が求められます。
- 相づちや表情で、興味を持って聞いていることを示す。
- 相手の発言を要約して確認する。(例:「つまり〜ということですね?」)
- 評価や結論を急がず、まずは受け止める。
説明力・意図伝達力
組織内には、抽象的な方針や複雑な情報が多く存在します。管理職は、それらを現場レベルで「わかりやすく翻訳し、行動に落とし込む力」が求められます。これらにより、部下の納得感やモチベーションが高まります。たとえば、以下のようなケースです。
- 経営方針を自部署の業務にどう関連づけるか。
- 戦略変更時に、なぜその方針になったのかを部下に説明する。
- 日々の業務指示において、目的や背景も合わせて伝える。
フィードバック力
管理職には、部下の行動や成果に対して適切なフィードバックを行う力も欠かせません。評価や注意をするだけでなく、「成長を促すコミュニケーション」としてのフィードバックが重要です。効果的なフィードバックのポイントは、以下の通りです。
- 行動に基づいた具体的な内容にする。(例:「先週のプレゼンで、資料構成が明確だった点が良かった」)
- タイミングを逃さず、リアルタイムで伝える。
- 改善点がある場合も、感情的にならず冷静かつ建設的に伝える。
調整力・交渉力
管理職は、自部署内だけでなく、他部署や経営層、外部パートナーとの連携・交渉も日常的に行います。その際、相手の立場や状況を理解し、意見の食い違いを円滑に調整する「交渉型コミュニケーション力」が問われます。特に、部署間の対立や予算配分、納期調整といった場面では、このスキルが成果を大きく左右します。このスキルでは、以下の点が重要になります。
- 相手の意図や背景を丁寧にヒアリングする。
- 自部署の状況を説明し、相互理解を図る。
- 妥協点や落としどころを見つける。
感情のコントロールと共感力
人を動かすマネジメントにおいては、論理だけでなく「感情」の扱いも非常に重要です。特に、感情的な対応を避け、冷静で安定した態度を保つことは、部下に安心感を与えます。人間的な対応が、信頼とエンゲージメントの向上につながります。同時に、部下の感情にも配慮し、共感を示す以下の様な姿勢が求められます。
- 「それは大変だったね」といった共感の言葉を添える。
- 感情的な反応に対して、否定せずにまず受け止める。
- 緊張や不安が強い場面での声かけやサポートを行う。
デジタルコミュニケーションへの適応
リモートワークやハイブリッド勤務が一般化する中で、チャットやWeb会議など、非対面コミュニケーションの比重が増しています。これらの環境下でも、情報の伝達精度や信頼構築が損なわれないようにする工夫が必要です。特に、文章では感情が伝わりづらいため、以下の様な意識的な配慮と工夫が求められます。
- 曖昧な表現を避け、明確な文章で伝える。
- チャットでのトーンやニュアンスに注意する。
- オンラインでも1on1やチームミーティングを定期的に行う。
管理職のコミュニケーションでよくある問題点
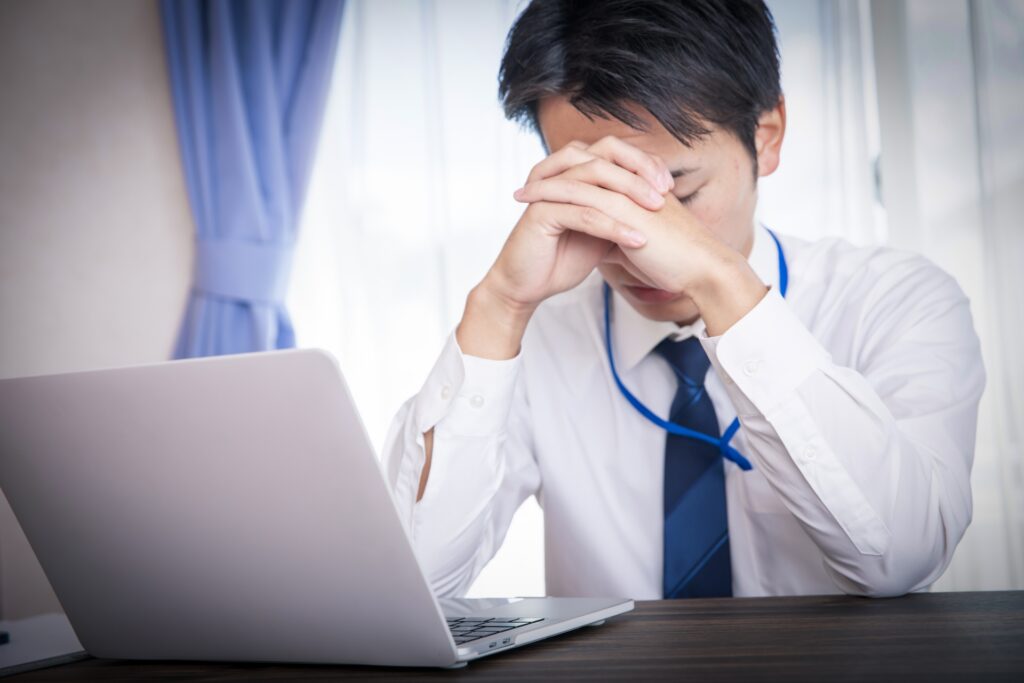
管理職にとってコミュニケーションは、業務遂行の「潤滑油」であると同時に、「信頼構築」や「モチベーション向上」に直結する極めて重要なスキルです。しかし、現場ではこのコミュニケーションがうまく機能していない例も少なくありません。
ここでは、管理職によく見られるコミュニケーション上の問題点と、その背景、改善のヒントについて解説します。
一方通行のコミュニケーション
最も典型的な問題は、「伝えること」に偏った一方通行のコミュニケーションです。このような状態では、部下は自分の声が届いていないと感じ、次第に報告や提案を控えるようになります。その結果、現場の課題が上層に届かず、意思決定の質が低下します。具体的には、次のような行動が該当します。
- 指示や命令ばかりで、部下の意見を聞かない。
- 業務内容や進捗のみを確認し、感情や背景に関心を示さない。
- 会話が「報告・連絡・相談」に終始し、双方向の対話がない。
フィードバックの不足
「ほめられたことがない」「何が悪かったのか具体的に言ってもらえない」といった声は、部下からよく聞かれる不満のひとつです。管理職の中には、部下の行動に対するフィードバックを行う習慣が乏しい人もいます。また、以下のような偏ったフィードバックも問題です。
- 成果が出たときだけ評価し、プロセスや努力を見ない。
- ミスを厳しく叱るが、成功には無反応となる。
- 個人の人格に踏み込むような指摘をしてしまう。
タイミングや状況を無視したコミュニケーション
コミュニケーションは「内容」だけでなく、「タイミング」「場所」「状況配慮」が極めて重要です。部下の状況を見極め、相手の立場に立って対応する視点が欠かせません。良かれと思って発言した内容でも、タイミングや状況が悪ければ、逆効果になることがあります。たとえば、以下のようなケースです。
- 忙しい時間帯に長々と話しかける。
- チームの前で個人の失敗を取り上げる。
- 感情が高ぶった状態で叱責する。
過剰な干渉やマイクロマネジメント
細かすぎる指示や過度のチェックは、部下にストレスを与えるだけでなく、主体性や創造性を奪ってしまいます。マイクロマネジメントに陥ってしまう管理職の特徴には、次の様なものがあります。
- 任せた仕事に対して、逐一細かく確認する。
- 自分のやり方を押しつける。
- 失敗を極度に恐れて、判断の自由を与えない。
無関心・放置型マネジメント
反対に、コミュニケーション不足が招くのが「放置型マネジメント」です。仕事を任せたまま進捗確認や声かけをしない管理職は、忙しさを理由に部下との関わりを後回しにしがちです。このタイプの管理職の下では、部下が孤立しやすく、早期退職やメンタル不調のリスクが高まります。こうした管理職に見られる行動は、以下の通りです。
- 「何かあれば言ってくるだろう」と自己判断に任せる。
- 1on1や面談の場を設けない。
- 日常的な声かけや雑談が極端に少ない。
誤解を招く曖昧な表現
「言ったつもり」「伝えたはず」が、実際には伝わっていないというのも、管理職のコミュニケーションで多く見られる問題です。こうした曖昧さは、ミスコミュニケーションを生み、業務ミスやトラブルの原因になります。
- 抽象的な指示(例:「しっかりやっておいて」「いい感じにまとめて」)
- 主語がない、結論が曖昧
- トーンや表情に一貫性がない
オンラインでの非言語情報の欠落
リモートワークの普及により、オンラインでのコミュニケーションが一般的になった一方で、「表情」「空気感」「間」などの非言語情報が伝わりづらくなっています。そのため、次の様な問題が起きがちで、オンライン上でも適度な表情の表現、声のトーン、こまめな確認が必要です。
- 言葉だけでは感情が伝わらず、冷たい印象を与える。
- 雑談や偶発的な会話が減り、関係構築が難しくなる。
- チャットでの指示が命令的に受け取られてしまう。
管理職が行うコミュニケーションのポイント

管理職にとってコミュニケーションは、単なる会話や情報伝達の手段ではなく、「人と組織を動かす」ための戦略的行動です。適切なタイミングで、正確かつ意図を持って伝える力が、部下のモチベーションやチーム全体の成果に直結します。
ここでは、管理職が意識すべきコミュニケーションの実践ポイントを具体的に解説します。
目的を持って話す・聞く
管理職のコミュニケーションは、「何のためにその会話をするのか」という目的意識を持つことが重要です。何となく雑談的に話すのではなく、「目的に沿った対話」を心がけることで、短時間でも効果的なコミュニケーションが実現します。
- 部下の状況を把握するために聞く。
- 方針を浸透させるために話す。
- 課題を共有し、協力を仰ぐために会話する。
「聴く姿勢」で信頼を得る
傾聴は信頼の第一歩です。管理職が「話す」ことよりも、「聞く」ことに価値を置くと、部下は「理解されている」「気にかけてもらっている」と感じます。こうした姿勢が、1on1やミーティングでの信頼関係を築きます。以下のポイントを押さえると、聴く力が高まります。
- 相手の話を途中で遮らず、最後まで聞く。
- スマホやパソコンから目を離し、視線を合わせる。
- 「なるほど」「それは大変だったね」などの共感を示す。
- 話の要点を自分の言葉で、繰り返して確認する。(リフレクション)
日常的な声かけを大切にする
管理職として部下と深い信頼関係を築くためには、日常の小さな声かけが非常に重要です。これらの何気ない一言が、心理的安全性の醸成に大きく寄与します。また、こうした声かけの中で、部下の変化や異変にも気づきやすくなります。
- 朝の「おはよう」や帰り際の「お疲れさま」
- 業務の合間の「調子はどう?」という一言
- 成果に対しての「ありがとう」「助かったよ」
「伝えた」ではなく「伝わった」かを確認する
コミュニケーションでしばしば起こるのが、「言ったつもり/聞いたつもり」のズレです。管理職は、「自分が伝えたか」ではなく、「相手にどう伝わったか」に責任を持つべき立場です。そのためには、以下の様な確認が効果的で、こうした手法で「伝達の精度」を高めていくことが重要です。
- 「ここまででわからない点はある?」と相手に確認する。
- 要点を簡潔に繰り返す。(サマリー)
- 相手に説明を求める。(例:「じゃあ、これをどう進めればいいか説明してもらえる?」)
定期的な1on1ミーティングの活用
最近では、多くの企業が1on1ミーティングを制度化しています。これは管理職と部下が定期的に向き合って対話する場であり、業務だけでなくキャリアや心理面にも踏み込んだコミュニケーションが可能です。継続することで信頼関係が深まり、離職の抑止やエンゲージメントの向上にもつながります。効果的な1on1のポイントは、以下の通りです。
- 月1〜週1など、一定の頻度で継続的に実施する。
- 業務の進捗だけでなく、悩みや不安にも耳を傾ける。
- 上司が主導するのではなく、部下に話してもらう時間を重視する。
- 議事録やメモを取り、次回に活かす。
チーム全体への情報共有も丁寧に
個別対応だけでなく、チーム全体への情報共有も管理職の重要な役割です。情報の透明性が低いと、噂や不信感が生まれ、組織の風通しが悪くなります。特に変化が多い時期や方針転換の場面では、「説明責任」を果たす意識を持つことが重要になります。
- 週次ミーティングや朝礼での方針共有
- メールやチャットでの要点まとめ
- 誰が見ても理解できる「見える化」
「場に応じた伝え方」を選ぶ
対面、電話、チャット、メール、オンライン会議など、伝達手段が多様化している今、場に合った方法を選ぶ判断力も管理職に求められます。適切な手段を選ぶことで、誤解や行き違いを減らし、効率的なやりとりが可能になります。
- 感情や空気感が必要な内容は対面やオンライン会議で
- 正確さが求められる指示は文書やメールで
- 簡易な確認や相談はチャットで
感情をコントロールし、冷静に対処する
感情的な対応は、信頼を損ねる最大のリスクです。どれだけ忙しくても、どれだけトラブルが起きても、管理職は「冷静さ」を保つことが求められます。「上司が落ち着いている」という事実だけで、部下は安心し、自信を持って行動できます。
- 感情が高ぶった時は、即答を避ける。
- 否定的なフィードバックでも、敬意と配慮をもって伝える。
- トラブル時こそ、落ち着いた言葉選びを行う。
管理職がしてはいけないコミュニケーションの例

管理職は「伝える力」「聴く力」などのコミュニケーションスキルを発揮することが求められますが、無意識に行っている”NGなコミュニケーション”が部下との信頼関係やチーム全体のパフォーマンスを損なうことも少なくありません。
ここでは、管理職が陥りがちな「してはいけない」コミュニケーション例とその影響、改善のヒントについて具体的に解説します。
公の場で部下を叱責する
たとえ部下の行動に問題があったとしても、他のメンバーの前で強く叱責することは絶対に避けるべきです。
「こんな簡単なこともできないのか」、「またミスか?何度言えばわかるんだ」などの言葉を人前で発すると、叱責された本人はもちろん、周囲のメンバーの士気にも悪影響を与えます。結果として、「上司は感情的」「あそこには相談できない」と思われ、報連相が滞りがちになります。
改善ポイント
注意や指導が必要な場面では、個別に呼び出し、冷静に状況確認と改善点を伝えるようにしましょう。
過度に曖昧な指示を出す
「とりあえずやってみて」、「例の件、適当に進めといて」など目的・方法・期待値が明確でない指示は、部下を混乱させ、ミスや時間の浪費を招きます。特に、経験の浅い若手社員ほど、「何をどうすればよいか」が具体的にわからないと動けません。
改善ポイント
目的(何のために)、方法(どうやって)、期限(いつまでに)を明示し、質問を促すことで伝達の確実性が増します。
感情的・否定的な発言を繰り返す
イライラしてつい感情的に言葉をぶつけてしまう管理職もいますが、それはチームの信頼を一瞬で壊す行為です。「君には期待してない」、「何回同じことを言わせるの?」など否定的な発言は、部下の自己肯定感を著しく傷つけ、「自分は認められていない」と感じさせます。
改善ポイント
事実と行動にフォーカスし、感情をコントロールした冷静な言葉選びを意識しましょう。以下の様な態度の違いは「不公平感」を生み、チーム全体のモチベーションや連帯感を損ないます。
人によって態度を変える
お気に入りの部下にはフランクで親しげだったり、男性部下と女性部下で対応が異なるなど、部下によって話し方や態度が極端に変わる管理職は、周囲からの信頼を失います。
改善ポイント
誰に対しても一貫性のある対応を心がけ、信頼される「公平なリーダー像」を確立しましょう。
部下の話を遮る・結論を急ぐ
部下が話を始めた途端に遮ったり、途中で「それは違う」「こうすればいい」と決めつけたりするのも、コミュニケーションを阻害する典型例です。これにより、部下は「どうせ聞いてもらえない」と感じ、発言を控えるようになります。
改善ポイント
最後まで話を聞く、問いかける、部下の意図を汲み取ることで、対話の質が高まり、部下の主体性も育ちます。
表情・態度が一貫しない
言葉では褒めていても、無表情だったり、目も合わせなかったりすることで、言葉が空虚に響く場合があります。非言語的な要素(表情、声のトーン、うなずきなど)も、コミュニケーションの重要な構成要素です。
改善ポイント
相手に安心感を与えるような「共感的な表情」「うなずき」「アイコンタクト」を意識しましょう。
成果を自分の手柄にする
部下が挙げた成果を、上司が自分の手柄として報告するような行為は、信頼を大きく損ねます。また、逆にトラブルや失敗だけを部下の責任にする「責任転嫁型」の管理職も敬遠されがちです。
改善ポイント
成果はチームのものとして讃え、失敗は一緒に振り返って改善を図る姿勢が、信頼を築きます。
雑談を全くしない/逆に馴れ合いになる
業務外の雑談を全くしない管理職は、部下にとって「話しかけづらい存在」となりがちです。一方で、プライベートに過度に踏み込んだり、距離感を間違えると、逆に信頼ではなく不快感を与えることもあります。
改善ポイント
節度を保ちつつ、軽い雑談や挨拶などで自然な距離感を保つと、日常の関係性がスムーズになります。
管理職のコミュニケーション能力を高める方法

管理職の役割が高度化・多様化する現代において、「人を動かす力」としてのコミュニケーション能力はますます重要性を増しています。しかし、これは先天的な才能ではなく、後天的に意識と実践の積み重ねで向上できるスキルです。
ここでは、管理職がコミュニケーション能力を高めるための具体的な方法を段階的にご紹介します。
1.自己認識を深める(メタ認知)
第一歩は、「自分のコミュニケーションスタイルを客観視すること」です。普段、自分がどう話しているのか、どのように受け止められているのかを認識することなしに、改善はあり得ません。自分のクセや思い込みに気づくことで、改善すべきポイントが明確になります。
実践ポイント
- 1on1や会議後に、部下や同僚からフィードバックをもらう。
- 自分の話し方を録音・録画して見直す。
- 自己評価と他者評価のギャップに気づく。
2.傾聴力をトレーニングする
「聞く力」はすべてのコミュニケーションの土台です。傾聴力を高めることで、部下との信頼関係を築き、意見や提案を引き出しやすくなります。これにより、表面的な会話から、信頼に基づく対話へと質が変わっていきます。
トレーニング方法
- 週1回の1on1で「質問→傾聴→要約」のプロセスを意識的に実施する。
- 「なぜそう思ったのか?」と掘り下げる質問を増やす。
- 相手の感情に焦点を当てたフィードバックを試みる。(例:「それは悔しかったですね」)
3.フィードバックの習慣化
管理職の中には、「褒めるのが苦手」「注意するときに気を遣いすぎる」といった悩みを持つ方も少なくありません。そこで有効なのが、「日常的なフィードバックの仕組み化」です。頻度を高め、気軽に実施することが、質の向上にもつながります。
実践方法
- 毎日の終業時に「今日の良かった点」を1つ言葉にする。
- 週次で簡単な振り返りコメントを個別に送る。
- 「事実→感想→期待」の順でフィードバックする。(例:「○○の資料、締切より早く完成していて良かった。丁寧な仕上がりで安心しました。今後もその調子でお願いします」)
4.コーチング・対話技法を学ぶ
近年注目されているのが、部下の内省や成長を促す「コーチング型コミュニケーション」です。これを学ぶことで、指示型から支援型へとマネジメントスタイルを転換できます。社内研修や外部のビジネスコーチング講座などを活用すると、理論と実践の両面で学べます。
おすすめのスキル
- オープンクエスチョン(例:「あなたはどうしたいですか?」)
- サンドイッチ型フィードバック(良い点 → 改善点 → 応援メッセージ)
- サイレント間(沈黙)を活かす技術
5.デジタル時代に対応したスキルを身につける
リモートワークの普及により、オンライン上でのコミュニケーション能力も不可欠になりました。対面では伝わる「空気感」「表情」「間」がない中で、いかに伝えるかが課題です。非対面でも「関係性を築く」視点を忘れないことが重要です。
意識すべき点
- 曖昧な表現を避け、明確・簡潔な文面を心がける。
- 表情・声のトーンに変化をつけて、相手の注意を引く。
- 雑談の機会を意図的に設ける。(例:オンライン朝会、週1の雑談タイム)
6.部下ごとにアプローチを変える
すべての部下に同じ接し方をしていては、信頼関係は築けません。個々の性格・価値観・仕事観に合わせたアプローチが求められます。個別最適化されたコミュニケーションが、チームのポテンシャルを最大化します。
具体例
- 自信のない部下には、成功体験を積ませてから次の課題へ進ませる。
- 自立志向の強い部下には、裁量を多めに与える。
- 話し下手な部下には、書面やチャットでの報告を認める。
7.自らの学びと振り返りを習慣にする
最後に最も大切なのは、「学び続ける姿勢」です。優れた管理職ほど、自分のコミュニケーションを定期的に見直し、改善を続けています。「自分はまだ成長できる」と思える人が、チームにも成長をもたらします。
習慣化のポイント
- 月1回の自己評価シートを活用する。(例:今月一番よかった会話は?反省点は?)
- 書籍・コラム・研修を通じて継続的にインプットする。
- 管理職同士で事例共有やロールプレイを行う場を持つ。
まとめ
管理職にとって、コミュニケーションは単なる情報伝達手段ではなく、部下との信頼関係を築き、組織全体の力を引き出すための重要なマネジメントスキルです。本コラムで紹介した基本のポイントを押さえ、日々のやり取りに丁寧さと誠実さを意識することで、部下の主体性を高め、チームの生産性や職場の風通しも格段に向上します。
まずは一つでも実践しやすいことから取り入れ、「伝える力」と「聴く力」の両面を意識した対話を積み重ねていきましょう。変化は、必ずあなたの職場に現れます。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

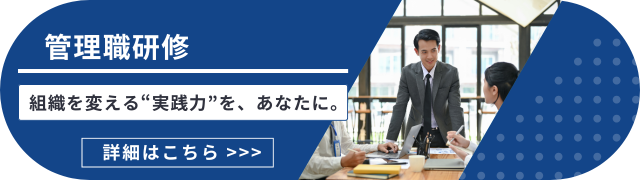


コメント