企業の管理職が直面するマネジメントの課題は多岐にわたります。
このコラムでは、人や業務、組織体制などについての具体的な悩みを整理し、解決方法を解説します。課題を明確にし、適切な管理能力を身につけることで、より良い組織運営を実現しましょう。
Contents
マネジメントの課題は何に起因している?

マネジメントの役割は、組織の目標を達成するために、人・業務・組織を適切に管理し、成果を最大化することです。しかし、実際には思うように機能しない場面が多く、マネジメントにはさまざまな課題が生じます。
では、マネジメントの課題は一体何に起因しているのでしょうか?
大きく分けると、マネジメントの課題は 「人」「業務」「組織体制」「自身」 の4つの要素から発生すると考えられます。
1.人に関する課題
マネジメントの最も大きな要素は「人」です。上司と部下の関係性や、部下のモチベーション管理、適切な人材配置、チームワークの形成など、人に関する課題は尽きません。たとえば、「部下が思うように動いてくれない」「チーム内のコミュニケーションが不足している」といった悩みは、多くの管理職が直面する問題です。
2.業務に関する課題
業務の進め方や、効率化、タスクの優先順位付けなども重要なポイントです。たとえば、「業務の割り振りが適切でない」「ムダな会議が多く、業務が停滞している」など、日々の業務運営の中で生じる問題は、マネジメントの質に直結します。
3.組織体制に関する課題
個々の努力だけでは解決できない問題として、「組織の仕組み」自体に起因する課題もあります。たとえば、役割分担が不明確で業務が属人化している、意思決定のスピードが遅い、評価制度が適切でないため人材が定着しないといった問題です。組織の仕組みが適切でないと、個々の能力を十分に発揮できず、チーム全体の成果や生産性が下がってしまいます。
4.自分に関する課題
最後に、マネージャー自身のスキルや姿勢が課題になるケースもあります。「部下に適切な指導ができていない」「リーダーシップが発揮できていない」「自身の業務が忙しすぎて、マネジメントに手が回らない」など、自分自身のマネジメント能力の不足が問題になることも少なくありません。
マネジメントの課題を解決するためには、これら4つの要素について深く理解し、それぞれに適切な対策を講じる必要があります。このあとの節では、「人」「業務」「組織体制」「自分」 の課題について、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。
関連コンテンツ
よくある課題①人に関する課題

マネジメントの課題の中で最も多くの管理職が直面するのが「人に関する課題」です。組織の成果は、個々のメンバーの能力や行動に大きく依存するため、チームの人間関係やモチベーション管理、適切な役割分担がうまくいかないと、生産性が大きく低下してしまいます。
ここでは、人に関する代表的な課題を整理し、それぞれの解決策を詳しく解説します。
1.部下が思うように動かない
「指示を出しても思うように動いてくれない」「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)が不足している」「積極性がなく受け身の姿勢になっている」といった悩みは、多くの管理職が抱える共通の課題です。
このような問題が生じる要因として、以下のようなものが考えられます。
- 指示があいまいで、部下が理解できていない
- 指示された仕事の意義が伝わっておらず、モチベーションが上がらない
- 部下自身が自信を持てず、行動に移せない
解決策
1.具体的な指示を出す
管理職がよく陥るミスは、「大まかな指示だけを出して、具体的な行動を伝えない」ことです。たとえば、「もっとお客様に提案をしなさい」という指示だけではなく、「今週中に3件、具体的な改善提案を作り、お客様に提示する」というように、数値や期限を明確に伝えることが重要です。
2.目的と背景を伝える
部下が仕事に対して受け身になっている場合、その仕事の「意義」を理解できていないことが多いです。ただ指示を出すのではなく、「なぜこの仕事をやるのか?」を伝えることが大切です。たとえば、「この改善提案を出すことで、お客様の満足度が上がり、長期的な関係を築ける」といった背景を説明すると、部下の納得感が高まり、主体的に動くようになります。
3.小さな成功体験を積ませる
部下が行動に移せない理由の一つに、「失敗を恐れている」「自信がない」という心理的なブレーキがあります。そのため、最初は小さな目標を設定し、達成を積み重ねることで自信をつけさせることが有効です。たとえば、「まずは既存のお客様1社に対して、新しい提案を試しに話してみる」など、ハードルの低い課題からスタートすると良いでしょう。
2.チームのコミュニケーション不足
チームの成果を最大化するためには、メンバー同士のスムーズな情報共有が不可欠です。しかし、次のような理由で、コミュニケーションが不足しがちです。
- チーム内での役割や責任が曖昧で、連携が取れていない
- メンバー同士の信頼関係が築けていない
- 対面での会話が少なく、メールやチャットだけで済ませている
解決策
1.定期的なミーティングを実施する
週に一度、短時間のチームミーティングを実施し、進捗状況や課題を共有する場を設けることで、コミュニケーション不足を解消できます。特に、リモートワークが増えている環境では、定期的なオンライン会議を行うことが重要です。
2.「心理的安全性」を高める
チーム内で「意見を自由に言える雰囲気」があるかどうかは、コミュニケーションの質に大きく影響します。上司が部下の意見を頭ごなしに否定してしまうと、メンバーは発言を控えるようになり、情報共有が滞ります。上司自身が率先して意見を受け入れる姿勢を見せることが大切です。
3.対面でのコミュニケーションを増やす
最近では、チャットやメールでのやり取りが主流になっていますが、文章だけでは伝わりにくい微妙な意味合いや感情があるため、重要な話はできるだけ対面またはオンラインのビデオ会議で行うと良いでしょう。
3.部下のモチベーションが低い
部下のモチベーションが低いと、仕事の生産性が低下し、組織全体の成果にも悪影響を及ぼします。モチベーションが下がる原因としては、次のようなものがあります。
- 仕事にやりがいを感じられない
- 上司や組織から評価されていないと感じている
- 仕事量が多すぎて疲弊している
解決策
1.「承認」と「評価」を意識する
モチベーションの向上には、部下の努力をしっかり認めることが重要です。「結果」だけでなく、「過程」も評価するようにし、些細な成長でも言葉にしてフィードバックすると良いでしょう。たとえば、「今回の提案は、前回よりも説得力が増していたね」といった具体的なコメントを伝えることで、部下のやる気が引き出されます。
2.仕事の裁量を増やす
単に指示を待つのではなく、自分で考えて行動できる環境を与えることも、モチベーション向上につながります。「この業務について、どう進めるのが良いと思う?」と問いかけることで、自発的な行動を促すことができます。
3.仕事の意味を伝える
部下が「何のためにこの仕事をしているのか」を理解できていないと、モチベーションは低下しやすくなります。たとえば、「この資料を作ることで、営業がよりスムーズに提案できる」といったように、業務の意義を伝えることが大切です。
「人に関する課題」は、マネジメントの中で最も大きな問題の一つですが、適切な対策を講じることで改善することができます。
- 具体的な指示と目的を伝える
- チーム内のコミュニケーションを活性化する
- 部下のモチベーションを高めるための働きかけを行う
これらの施策を取り入れることで、より良いチーム運営が可能になるでしょう。
よくある課題②業務に関する課題

マネジメントの課題として「人に関する課題」に次いで多いのが、「業務に関する課題」です。業務が円滑に進まないと、チームの生産性が低下し、結果的に組織全体の成果にも悪影響を及ぼします。管理職としては、業務の進め方や効率化、業務の優先順位付けを適切に行い、チーム全体の成果を最大化することが求められます。
ここでは、業務に関する代表的な課題を整理し、それぞれの解決策を詳しく解説します。
1.業務の優先順位が不明確で、仕事が非効率になる
多くの職場で、以下のような問題が発生しています。
- どの業務を優先すべきかわからず、重要な仕事が後回しになる
- 緊急対応に追われ、計画的な業務が進まない
- 上司や同僚からの依頼が次々と入り、混乱する
このような状況では、社員が本来やるべき業務に集中できず、組織全体の生産性が低下してしまいます。
解決策
1.業務の「重要度」と「緊急度」を明確にする
業務管理のフレームワークとしてよく使われる「緊急度・重要度マトリクス(アイゼンハワー・マトリクス)」を活用すると、業務の優先順位を明確にできます。
| 重要度\緊急度 | 高い | 低い |
|---|---|---|
| 高い | すぐ対応する | 計画的に進める |
| 低い | 他者に委任する | できるだけ削減する |
たとえば、「クライアントからの急な問い合わせ」 は緊急かつ重要なので、最優先で対応するべきですが、「長期的な戦略立案」 も重要であり、計画的に進める必要があります。一方で、「意味のない定例会議」 のように、緊急でも重要でもない業務は削減するべきです。
2.チーム内で業務の優先順位を共有する
管理職が業務の優先順位を把握していても、部下が理解していなければ意味がありません。週に一度、チームで業務の優先順位を共有するミーティングを設けることで、全員が同じ方向を向いて業務を進めることができます。
2.業務の属人化によるリスク
業務が特定の人に依存してしまう「属人化」は、多くの企業で見られる問題です。たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 特定の社員しか業務の進め方を知らない
- 担当者が休むと業務が止まってしまう
- 引き継ぎが十分にされず、仕事の知識ややり方が受け継がれない
このような状況では、担当者が異動や退職した際に業務の継続が困難になり、組織に大きなリスクをもたらします。
解決策
1.業務の標準化を進める
業務の進め方を明文化し、誰でも対応できるようにすることが重要です。たとえば、「業務マニュアル」や「手順書」を作成し、属人化を防ぐ工夫をするとよいでしょう。
- 業務の手順を文書にまとめる(例:「受発注業務の流れ」など)
- 定期的にマニュアルを更新する(最新の業務手順を反映)
- OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を実施し、実際の業務を通じて指導を行いながら、複数のメンバーに業務を習得させる
2.担当業務を分散させる
1人の社員に業務が集中しないように、業務をチーム内で分散させる仕組みを作ることも有効です。たとえば、特定の社員に業務が偏らないように、一定期間ごとに担当業務を入れ替える「ジョブローテーション」を実施することで、複数の社員が同じ業務を経験し、リスクを分散できます。
3.無駄な業務や会議が多く、生産性が低い
「会議ばかりで業務が進まない」「非効率な業務が多すぎる」という声は、多くの職場で聞かれます。たとえば、以下のような状況がよく見られます。
- 目的が不明確な会議が多い
- 報告のための資料作成に時間がかかる
- 不要な業務が多く、本来の業務に集中できない
このような状態が続くと、社員のモチベーションが低下し、生産性が著しく低下してしまいます。
解決策
1.会議の数と時間を最適化する
会議の効率を上げるために、次のルールを導入すると効果的です。
- アジェンダ(議題)を事前に共有し、無駄な話を省く
- 会議時間は最大30分とし、時間内に決定事項をまとめる
- 「この会議は本当に必要か?」を常に見直す
2.業務の流れを見直す
「本当に必要な業務か?」を定期的に見直し、不要な業務を削減することが重要です。たとえば、手作業で行っている業務をデジタル化することで、業務時間を大幅に削減できます。
- 報告書をExcelで作成していたが、システムを導入して自動化
- 紙ベースの申請業務を電子化し、承認の手続きを簡略化
業務に関する課題を解決するためには、次の3つのポイントを意識することが重要です。
- 業務の優先順位を明確にし、チーム全体で共有する
- 属人化を防ぎ、業務の標準化を進める
- 無駄な業務を削減し、会議や仕事の進め方を最適化する
これらの対策を実施することで、チーム全体の生産性が向上し、組織の成果も大きく改善されるでしょう。
よくある課題③組織体制に関する課題
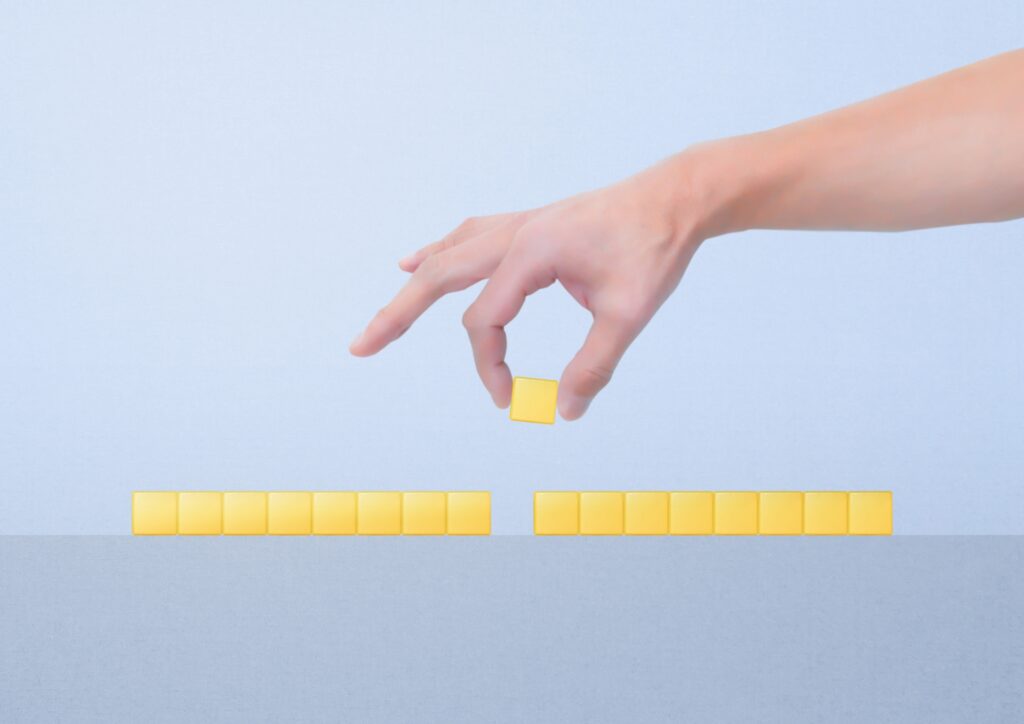
組織の成果は、個々の社員の努力だけではなく、組織全体の仕組みや体制によって大きく左右されます。たとえ優秀な人材がそろっていても、組織の仕組みが適切でなければ、業務の非効率や意思決定の遅れが発生し、成果を出しにくくなります。
ここでは、組織体制に関する代表的な課題を整理し、それぞれの解決策を詳しく解説します。
1.役割分担が不明確で、業務が混乱する
多くの企業で、「誰が何を担当すべきか」が明確になっておらず、以下のような問題が発生しています。
- 業務が属人化し、他のメンバーが対応できない
- 複数の人が同じ業務に取り組み、二重作業が発生する
- 責任の所在が曖昧で、問題が発生しても誰が対応するか決まっていない
このような状態では、チーム内の業務がスムーズに進まず、無駄な時間や労力が増えてしまいます。
解決策
1.業務の役割と責任を明確にする(RACIマトリクスの活用)
役割と責任を明確にするためのフレームワークとして、RACIマトリクスが有効です。
| 役割 | 意味 |
|---|---|
| R(Responsible) | 実際に作業を担当する人 |
| A(Accountable) | 最終的な意思決定や責任を持つ人 |
| C(Consulted) | 意見を求められる人 |
| I(Informed) | 進捗状況を共有される人 |
たとえば、新しいプロジェクトを立ち上げる際、各メンバーの役割をこのマトリクスで整理すると、業務の混乱を防ぐことができます。
2.チーム内で業務分担を可視化する
ホワイトボードやタスク管理ツール(Trello、Asana、Notionなど)を活用し、「誰が何を担当しているのか」 をチーム全体で共有する仕組みを作ると、業務の混乱を防ぐことができます。
たとえば、Trelloは視覚的に仕事の進捗を管理できるカード型の管理ソフト、Asanaはプロジェクトの進み具合を細かく把握できる管理システム、Notionはメモやデータの整理と仕事の管理を一つにまとめられる便利なツールといった特徴があり、業務のやり方に合わせて選ぶことができます。
2. 意思決定のスピードが遅く、業務が停滞する
組織の成長に伴い、次のような問題が発生することがあります。
- 決裁権限が不明確で、意思決定に時間がかかる
- 上層部の承認を待たなければ動けず、スピードが落ちる
- 組織の階層が増えすぎて、情報がうまく伝達されない
このような問題が続くと、競争の激しい市場環境において、柔軟な対応ができず、ビジネスチャンスを逃してしまいます。
解決策
1.意思決定の基準を明確にする
「どのレベルの意思決定は、誰が行うのか?」を事前に明確にすることで、判断スピードを向上させることができます。たとえば、以下のようなガイドラインを設定すると、業務の停滞を防げます。
- 30万円以下の予算決裁は部長レベルでOK
- 顧客対応の即時判断は現場リーダーが実施
- 組織変更などの大きな決定は経営会議で承認
2.権限移譲を進める
すべての意思決定を上層部が行うのではなく、「現場で判断できる範囲を広げる」 ことで、スピード感のある組織運営が可能になります。
たとえば、営業チームに一定の裁量を与えることで、「顧客対応のスピードが向上する」「現場の創意工夫が生まれる」といった効果が期待できます。
3.組織文化が定着せず、社員のエンゲージメントが低い
組織の文化が確立されていないと、以下のような問題が発生します。
- 組織の価値観や、企業が将来どのような姿を目指し、何を実現しようとしているのかを示すビジョンが浸透しておらず、社員の意識がバラバラ
- チームの一体感がなく、離職率が高い
- 上司と部下の信頼関係が築けていない
組織文化が根付いていないと、社員が会社に対して帰属意識を持ちにくくなり、離職率が上がったり、チームワークが機能しなくなったりします。特に、「エンゲージメント」(社員が会社に愛着を持ち、主体的に貢献しようとする意欲)が低下すると、仕事に対するモチベーションや生産性も下がりやすくなります。
解決策
1. 経営理念やミッションを明確にし、発信する
組織の価値観を社員に浸透させるためには、経営理念やビジョンを言語化し、繰り返し発信することが重要 です。
たとえば、
- 朝礼や会議で会社の価値観を共有する
- 社員向けの研修やワークショップを開催する
- 社内報や動画コンテンツを活用し、企業の目的や目指す方向を伝える
などの取り組みを継続的に行うことで、組織文化の定着を図れます。
2.上司と部下の定期的な対話を増やす
組織文化の形成には、「上司と部下の信頼関係」も欠かせません。1on1ミーティングを定期的に実施し、社員の意見や不安を聞き取ることで、エンゲージメントの向上につながります。
組織体制に関する課題を解決するためには、次の3つのポイントを意識することが重要です。
- 役割と責任を明確にし、業務の混乱を防ぐ
- 意思決定のスピードを向上させ、組織の機動力を高める
- 組織文化を確立し、社員のエンゲージメントを向上させる
組織の仕組みを改善することで、個々の社員が能力を発揮しやすくなり、組織全体の成果も向上します。
よくある課題④自分に関する課題

マネジメントにおいて、「人・業務・組織体制」に関する課題が重要なのは間違いありません。しかし、それ以上に 「マネージャー自身が抱える課題」 を見落としてしまうと、組織全体の成長を妨げる要因となります。マネージャーが適切な判断や行動ができなければ、どれだけ優れた組織体制や仕組みを整えても、チームの成果にはつながりません。
ここでは、マネージャー自身が陥りがちな課題を整理し、それぞれの解決策を詳しく解説します。
1.リーダーシップの不足
マネージャーには、チームを率いて成果を出すためのリーダーシップが求められます。しかし、次のような問題が生じることがあります。
- 部下からの信頼が得られない
- 部下を適切に導くことができず、チームがまとまらない
特に、リーダーシップが弱いと、チームが一体となって動けず、個々の社員がバラバラに働くことになります。その結果、チームの生産性が低下し、目標達成が困難になります。リーダーシップとは、単に指示を出すことではなく、「組織の目標を示し、メンバーを動かす力」です。この力を身につけることで、チームをより強固にまとめ、成果を出せる組織へと成長させることができます。
解決策
1.ビジョンを明確にし、チームと共有する
リーダーシップを発揮するためには、「どの方向にチームを導くのか?」という明確なビジョンが必要です。
- 「今期の目標は何か?」
- 「チームとして何を大切にするのか?」
- 「この仕事を通じてどんな成果を出したいのか?」
これらを具体的に言語化し、日々の業務の中で繰り返し発信することが重要です。メンバーは、リーダーの考えが明確であればあるほど安心して行動できます。また、ビジョンを共有することで、メンバーの意識が統一され、チームとしての一体感が生まれます。
2.信頼関係を築く
リーダーとしての影響力は、部下との信頼関係によって大きく変わります。部下からの信頼を得るためには、次のような行動が効果的です。
- 誠実なコミュニケーションを心がける(約束を守る・部下の意見を尊重する)
- 成果だけでなく、努力の過程も評価する(結果だけではなく、日々の取り組みに目を向ける)
- 適切なフィードバックを行い、成長をサポートする(叱るだけでなく、建設的なアドバイスをする)
信頼関係が築かれると、部下は安心して業務に取り組めるようになり、積極的に意見を出しやすくなります。その結果、組織としての意思疎通が円滑になり、リーダーシップが発揮しやすくなります。
2.マイクロマネジメントによる業務過多
マネージャーの中には、部下の業務に細かく口を出しすぎてしまい、以下のような問題に陥ることがあります。
- すべての業務を自分でチェックしなければ気が済まない
- 部下に任せられず、結局自分が手を動かしてしまう
- 結果として、自分の業務量が増えすぎてしまう
このような「マイクロマネジメント」が続くと、マネージャー自身の業務過多につながるだけでなく、部下の自主性が育たず、チームの成長を妨げることになります。
解決策
1.権限移譲(デリゲーション)を意識する
「自分がやったほうが早い」と考えてしまいがちですが、マネージャーの役割は 「業務をこなすこと」ではなく、「チームの生産性を最大化すること」 です。
- 「この業務は部下に任せられるか?」を常に考える
- 仕事を任せる際には、「目的」「期待する成果」「判断基準」を明確に伝える
- 部下に権限を持たせ、意思決定の場面を増やす
2.フィードバックの仕組みを整える
業務を任せる際、「結果が悪かったらどうしよう」と不安に感じることがあります。そのため、途中経過を確認する「チェックポイント」 を設けると安心して任せることができます。
- 毎週の定例ミーティングで進捗確認を行う
- 部下に任せた業務のフィードバックを適切に行う
3.自己成長の停滞
マネージャーは、日々の業務に追われる中で、自分自身の成長を後回しにしてしまう ケースがよくあります。
- 最新のマネジメント手法を学ぶ機会がない
- 業務に忙殺され、自分の成長に目を向けられない
- 気づけば数年前と同じやり方でマネジメントしている
自己成長を怠ると、マネージャーとしての視野が狭くなり、新しいアイデアや戦略を生み出すことが難しくなります。
解決策
1.継続的な学習の習慣をつける
忙しい中でも、以下のような方法で学習の時間を確保することができます。
- 1日15分、ビジネス書を読む
- 業界の最新ニュースや記事をチェックする
- 社外の勉強会やセミナーに参加する
2.メンターやコーチを持つ
自分一人で成長し続けるのは難しいため、「頼れる人」 を持つことも有効です。
- 社内の上司や先輩に定期的に相談する
- 外部のコーチングやマネジメント研修を受ける
- 経営者や管理職向けのネットワークに参加する
メンターは経験や知識をもとに助言を与え、成長を支援する存在であり、コーチは対話を通じて考えを引き出し、自ら答えを見つけられるようサポートする役割を担います。
4.メンタルマネジメントができていない
マネージャーは、組織の責任を背負う立場にあるため、次のようなストレスを抱えがちです。
- プレッシャーによる精神的な負担
- 部下との人間関係の悩み
- 成果を求められるプレッシャー
これらのストレスを適切に管理できないと、心身に悪影響を及ぼし、仕事の質や効率が低下してしまいます。
解決策
1.ストレスを発散する時間を確保する
マネージャーも人間です。適切に休息を取り、ストレスを発散する時間を作ることが重要です。
- 週に1回は趣味や運動の時間を確保する
- 休日は仕事から完全に離れる
- リラックスできる環境を意識的に作る
2. 必要な時は周囲に頼る
すべての問題を一人で解決しようとすると、精神的な負担が増大します。適切なタイミングで上司や同僚に相談し、サポートを得ることも大切です。
マネージャー自身の課題を解決するためには、次のポイントが重要です。
- リーダーシップを磨き、明確なビジョンを示す
- 業務を部下に適切に委任し、マイクロマネジメントを避ける
- 継続的に学び、自己成長の機会を確保する
- メンタルマネジメントを意識し、ストレスを適切に管理する
自分自身を成長させることで、チームの成果も向上し、組織全体の成果につながります。
課題の解決に必要な能力

これまでのコラムでは、マネジメントにおけるさまざまな課題について解説してきました。マネージャーが直面する課題は、大きく「人」「業務」「組織体制」「自分」の4つに分類でき、それぞれに適した対策を講じることが重要です。しかし、これらの課題を効果的に解決し、成果を上げるためには、マネージャー自身が必要な能力を身につけることが欠かせません。
ここでは、マネジメントの課題解決に必要な主要な能力について、具体的な解説と実践的なアドバイスを紹介します。
1.課題発見力(問題を特定する力)
多くの組織では、表面的な問題に気を取られ、真の課題を見落としがちです。たとえば、「部下のモチベーションが低い」という問題がある場合、その原因は「上司のフィードバック不足」「業務の目的が明確でない」「評価制度が適切でない」など、さまざまな要因が考えられます。マネージャーには、こうした「本当の問題は何か?」を見極める能力が求められます。
実践方法
- 現場の声を積極的に聞く(1on1ミーティングやアンケートを活用)
- 「なぜ?」を繰り返し、問題の根本原因を探る(5Why分析)
- データを活用し、感覚ではなく客観的に問題を判断する
2.コミュニケーション力(伝える力・聞く力)
マネジメントにおいて、最も基本的でありながら、最も重要なのがコミュニケーション能力です。部下や上司、他部門と円滑に意思疎通を図り、適切な情報を共有することで、組織全体の動きをスムーズにします。
実践方法
- 「伝え方」に注意し、具体的かつ簡潔な指示を心がける(抽象的な表現を避ける)
- 部下の話をよく聞き、相手の立場を理解する(アクティブリスニング)
- オンライン・オフラインの適切なツールを使い分ける(対面、メール、チャット、会議の使い分け)
3.意思決定力(素早く適切な判断をする力)
意思決定のスピードと質は、マネージャーの役割において非常に重要です。判断が遅れると、組織全体の進捗が滞り、競争力が低下する可能性があります。
実践方法
- 80%の情報が揃ったら決断する(完璧を求めすぎない)
- 意思決定の手順を標準化し、迅速な判断ができる体制をつくる
- 優先順位を明確にし、「重要なこと」に集中する(アイゼンハワーマトリクスを活用)
4.リーダーシップ(チームを導く力)
リーダーシップとは、単に部下に指示を出すことではなく、「ビジョンを示し、チームを前進させる力」です。メンバーが同じ方向を向いて取り組めるよう、マネージャーには組織の目標や価値観を明確に伝え、チームを牽引する役割が求められます。
実践方法
- 組織の目標を明確に伝え、ビジョンを共有する
- 部下に役割と期待値をしっかり伝え、納得感を持たせる
- チームの成功を称賛し、モチベーションを高める(承認・フィードバックを意識的に行う)
5.部下育成力(人を成長させる力)
部下の成長なくして、組織の成長はあり得ません。マネージャーの役割は「自分が成果を出すこと」ではなく、「チーム全体の成果を最大化すること」です。そのためには、人材育成を意識し、部下がスキルを高め、自立して動けるようにする育成力が欠かせません。日常業務の中で育成の機会を設け、メンバーの成長を促すことが、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
実践方法
- 部下に仕事を「任せる」機会を増やし、成長の場を提供する
- 適切なフィードバックを行い、改善点を明確にする
- 個々の成長プランを一緒に考え、人材育成を通じてキャリア形成をサポートする
6.柔軟性(変化に適応する力)
ビジネス環境が急速に変化する現代において、「これまでのやり方」に固執せず、新しい手法や考え方を取り入れる柔軟性が求められます。特に、デジタル化やリモートワークの普及など、働き方の変化に対応できるマネージャーが、今後ますます重要になります。
実践方法
- 定期的に最新のマネジメント手法を学ぶ(書籍・セミナー・勉強会の活用)
- 部下の意見を積極的に取り入れ、チーム内で変化を促す
- 「失敗を恐れずに挑戦する」文化をつくる
7.ストレスマネジメント(自身の心身を管理する力)
マネージャーは、業務のプレッシャーや対人関係のストレスを抱えやすい立場です。適切にストレスを管理できないと、判断力の低下や仕事の質や効率の低下を招き、最終的には組織全体にも悪影響を及ぼします。
実践方法
- 仕事とプライベートのバランスを意識し、適切に休息を取る
- ストレスの原因を把握し、対処法を考える(運動・リラックス・相談など)
- 周囲に頼ることを意識し、必要に応じてサポートを求める
マネジメントの課題を解決し、組織を成功へと導くためには、以下の7つの能力が必要です。
- 課題発見力(問題の本質を見抜く力)
- コミュニケーション力(伝える力・聞く力)
- 意思決定力(素早く適切な判断をする力)
- リーダーシップ(チームを導く力)
- 部下育成力(人を成長させる力)
- 柔軟性(変化に適応する力)
- ストレスマネジメント(自身の心身を管理する力)
これらの能力を身につけることで、マネージャーとしての成長だけでなく、チーム全体の成功にもつながります。日々の業務の中で意識的に取り組み、より強いマネジメント力を磨いていきましょう。
関連コンテンツ
マネジメント課題を乗り越えるために
本コラムでは、マネジメントの課題が何に起因するのかを整理し、「人」「業務」「組織体制」「自分」の4つの側面から、よくある問題とその解決策について詳しく解説しました。さらに、これらの課題を乗り越えるために必要な能力についても紹介しました。
マネジメントは、一つの正解があるものではなく、組織やチームの状況、メンバーの特性、業務内容によって最適な方法が異なります。 そのため、重要なのは「完璧なマネージャー」を目指すことではなく、状況に応じて柔軟に対応できる力を養うことです。
また、マネージャーは課題を解決する「答え」を持つことが求められる立場ではありますが、必ずしもすべてを一人で解決する必要はありません。 部下やチームメンバーと協力しながら、組織全体で成長していくことが、持続的な成功につながります。
本コラムが、日々マネジメントに向き合う皆様のヒントとなり、課題解決の一助となれば幸いです。試行錯誤を重ねながら、一歩ずつ前進し、より良い組織づくりを目指していきましょう。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。




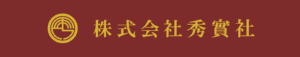
コメント