現代の企業が成功し続けるには、時代の変化に適応する組織改革とは何かを理解し、実践することが必要です。本コラムでは、組織改革が求められる背景や成功のポイントを解説し、実践に役立つフレームワークを紹介します。変革を進めるための重要な要素を押さえ、自社に適した改革の進め方を具体的に考えましょう。
Contents
組織に改革が求められる理由や背景
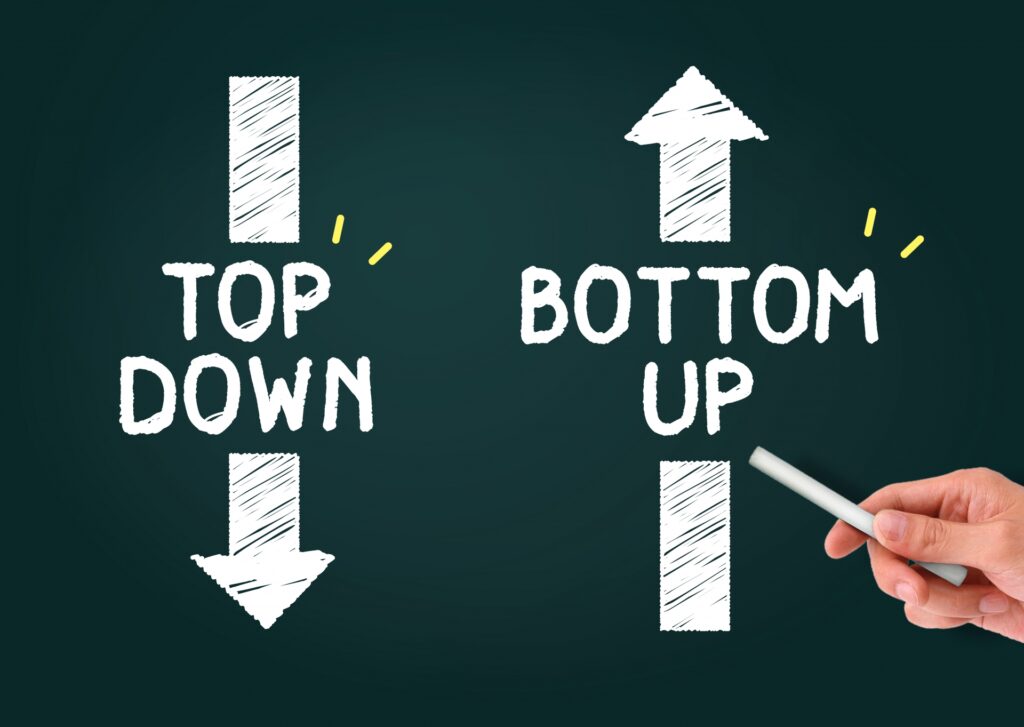
企業は時代の変化に適応しながら成長を続けなければなりません。しかし、現状の組織体制や業務の進め方が変化に対応できていないと、企業の競争力は低下し、成長が停滞してしまいます。そのため、組織改革は企業の存続と発展に欠かせない取り組みです。
ここでは、組織に改革が求められる理由や背景について詳しく解説します。
1.環境の変化に適応する必要がある
現代のビジネス環境は急速に変化しています。新しい技術の発展、グローバル競争の激化、消費者ニーズの多様化、そして働き方の変化など、企業を取り巻く環境は常に変わり続けています。
1.デジタル化・DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展
AIやIoT、ビッグデータといったデジタル技術の発展により、業務の効率化や新たなビジネスモデルの構築が求められています。従来のやり方では市場の変化についていけず、競争力を維持することが難しくなります。そのため、企業向けのDX推進施策や、従業員向けのデジタルスキル向上研修といった取り組みが不可欠です。
2.グローバル化による競争の激化
日本国内だけでなく、海外企業との競争もますます激しくなっています。国際市場で戦うためには、組織の意思決定のスピードを上げる、柔軟な組織体制を作るといった改革が必要です。特に、古い縦割り組織のままでは、迅速な対応ができず、市場の変化についていけません。
3.働き方の多様化
リモートワークやフレックスタイム制、副業の解禁など、従来の働き方にとらわれないスタイルが浸透しつつあります。従業員の価値観も変化し、「仕事のやりがい」「仕事と私生活のバランス」「キャリアの選択肢」などが重視されるようになりました。これらのニーズに応えられる組織でなければ、優秀な人材の確保・定着が難しくなります。
2.組織の硬直化による成長の停滞
組織が長年同じ体制のままだと、次のような問題が発生しやすくなります。
- 意思決定のスピードが遅い
- 新しいアイデアが生まれにくい
- 変化に対する抵抗が強くなる
特に、大企業や歴史のある企業ほど「前例主義」「年功序列」といった慣習が根強く、新しい取り組みを進めるのが難しくなりがちです。このような硬直化した組織を放置すると、市場の変化に適応できず、結果として企業の成長が停滞してしまいます。
組織改革によって柔軟な意思決定ができる体制を整え、変化に適応できる仕組みを構築することが必要です。
3.人材の成長と活用のため
組織は「人」で成り立っています。企業が成長を続けるためには、従業員一人ひとりが能力を発揮し、成長し続ける環境を作ることが重要です。
1.人材の多様性を活かす
従業員の価値観やスキル、これまでの経験や育ってきた環境は多様化しています。しかし、従来の画一的な組織運営では、それぞれの個性や強みを十分に活かしきれません。組織改革を通じて、個々の特性に応じた成長の道筋や昇進の仕組みを導入することで、人材の活躍の幅を広げることができます。
2.次世代リーダーの育成
企業の持続的な成長には、次世代を担うリーダーの育成が欠かせません。しかし、組織改革を行わずに現状のままでは、リーダー候補が十分に経験を積めず、育成が進まない可能性があります。組織を変えることで、若手社員に責任ある役割を任せるなど、新たなリーダーを生み出す機会を増やすことができます。
4.業績向上と競争力強化のため
組織改革の目的のひとつは、企業の業績を向上させ、競争力を強化することです。次のような課題を解決するためにも、改革が求められます。
1.無駄な業務の削減と生産性向上
- 意味のない会議が多い
- 業務の分担が不明確で、同じ作業を複数の人が行っている
- 上司や関係者の確認や許可を得る手続きが多すぎて、意思決定に時間がかかる
こうした課題を解決するためには、仕事の進め方を見直し、組織の仕組みを改善することが必要です。
2.顧客ニーズに応じた柔軟な対応
市場の変化が激しい中、顧客のニーズも多様化しています。しかし、硬直化した組織では、こうした変化に柔軟に対応することが難しくなります。組織改革を通じて、顧客ニーズに応じたサービスや商品の開発スピードを向上させることが求められます。
5.組織改革を怠るリスク
組織改革を行わずに現状維持を続けると、企業には次のようなリスクが生じます。
競争力の低下
市場の変化に対応できず、他社に後れを取る
優秀な人材の流出
社員が成長できる環境がないため、他社へ転職してしまう
業績の悪化
生産性が低下し、売上や利益が伸び悩む
これらのリスクを回避し、企業の持続的な成長を実現するためには、組織改革が不可欠です。
組織に改革が求められる理由は、このように多岐にわたります。変化の激しい現代において、企業が生き残るためには、常に柔軟な組織運営を意識し、必要に応じて改革を進めることが重要です。
そもそも組織改革とは

企業が成長し続けるためには、市場の変化や経営環境に適応し、組織の仕組みや運営方法を進化させる必要があります。そのために不可欠なのが「組織改革」です。では、そもそも組織改革とは何を指し、どのような目的で行われるのでしょうか。
以下では、組織改革の基本的な定義や目的、重要性について詳しく解説します。
1.組織改革とは何か?
組織改革とは、企業や組織の仕組み・構造・文化・運営方法を見直し、より良い形へと変える取り組みのことを指します。具体的には、業務の進め方や意思決定の仕組みを改善したり、部門の役割や人員配置を最適化したりするなど、多岐にわたります。企業が市場や社会において必要とされる存在であり続けるためにも、組織の在り方を見直し、進化させることが重要です。
組織改革は単なる制度の変更ではなく、「企業の目指す方向性に合わせて、組織をより効率的かつ柔軟なものへと変えていく取り組み」です。成功すれば、組織の競争力を高め、企業の成長を促進する大きな要因となります。
2.組織改革の対象となる主な領域
組織改革は幅広い領域に及びますが、大きく以下の5つの視点で考えられます。それぞれの領域ごとに、どのような内容が含まれるのかを見ていきましょう。
1.組織構造の変更
- 部門の統合・分割
- 階層の削減(フラット化)
- プロジェクト型組織(特定の課題や目標に応じて柔軟にチームを編成し、部門を超えて協力しながら進める組織形態。変化の激しい環境に対応しやすく、専門性を活かした業務推進が可能)への移行 など
組織の構造を見直すことで、よりスムーズな意思決定や業務の効率化が図れます。たとえば、経営層が意思決定を行い、指示を階層的に下ろすトップダウン型組織から、現場の意見を反映しやすいフラットな組織に移行するケースがあります。
2. 業務の流れの見直し
- 業務手順の効率化
- ペーパーレス化・デジタル化
- 権限移譲による意思決定の迅速化 など
業務の流れを見直し、無駄を削減することで、生産性を向上させることができます。特に、ITの活用や業務の標準化を進めることが、組織改革の成功につながります。
3.人材の配置・育成
- 適材適所の人員配置
- 次世代リーダーの育成
- 評価制度の見直し など
組織改革の中で、人材の活用は重要なポイントです。従業員の強みを活かせる環境を整え、成長の機会を提供することが、企業の持続的な発展につながります。
4.組織文化・風土の変革
- 企業理念やビジョンの再構築(企業が目指す方向性や価値観を明確にし、組織全体で共有することで、一貫性のある経営を実現する。)
- 社員のエンゲージメント向上(社員が企業の目標や価値観に共感し、自発的に貢献しようとする意欲を高める。働きがいの向上や離職率の低下につながる。)
- 風通しの良いコミュニケーションの促進 など
組織の文化を変えることで、社員の意識や行動を変え、より活気のある職場環境を作ることができます。
5.マネジメント体制の見直し
- 管理職の役割と責任の明確化
- リーダーシップの強化
- コーチングや1on1ミーティングの導入 など
コーチングとは、対話を通じて相手の考えや能力を引き出し、自発的な成長を促す指導方法。単なる指示やアドバイスではなく、質問や傾聴を通じて気づきを与え、主体的な行動を引き出すことを目的とする。
管理職の役割を見直し、リーダーシップを強化することで、組織全体の成果や生産性を向上させることができます。
3.組織改革の重要性
組織改革は単なる制度の変更ではなく、企業の成長に直結する重要な取り組みです。以下の3つの観点から、その重要性を整理します。
1.変化に適応できる組織を作る
市場環境が変化する中で、企業が生き残るためには、常に柔軟な組織運営が求められます。組織改革によって、新しい環境に適応できる企業体質を作ることができます。
2.社員のモチベーション向上
組織の課題が放置されると、社員のモチベーション低下につながります。組織改革を通じて、働きやすい環境を整え、社員がやりがいを持って働けるようにすることが重要です。
3.持続的な成長の実現
企業が長期的に成長を続けるためには、組織の仕組みを適切に整えることが不可欠です。組織改革を定期的に行い、時代の変化に応じた最適な運営を目指すことで、企業の競争力を維持することができます。
組織改革とは、企業の仕組みや運営方法を見直し、より柔軟で効率的な組織を作るための取り組みです。変化の激しい時代において、企業が持続的に成長するためには、組織改革が欠かせません。
関連コンテンツ
目指すゴールはどこにあるのか

組織改革は、単なる業務改善や構造の変更ではなく、企業が成長し続けるための重要な取り組みです。しかし、「何を目指して改革を進めるのか?」というゴールが明確でなければ、組織改革は成功しません。単なる変化を目的にするのではなく、企業のビジョンや経営目標と連動した改革が求められます。
ここでは、組織改革において目指すべきゴールについて詳しく解説します。
1.組織改革のゴールとは?
組織改革のゴールは、企業の成長や競争力向上を実現するために、「より柔軟で効率的に機能する組織を作ること」 です。つまり、「市場の変化に対応できる」「社員が活躍できる」「業績が向上する」といった目的を達成するための組織作りが求められます。
しかし、企業によって抱える課題や目指す方向は異なります。そのため、組織改革のゴールも一律ではなく、企業の状況や目標に応じて明確に設定することが大切です。また、組織の変革を成功させるには、従業員一人ひとりが「自分も改革の一部である」という意識を持つことが重要です。
2.組織改革の主なゴール
組織改革のゴールを大きく分類すると、以下の5つに分けることができます。
1.組織の柔軟性・適応力を高める
市場環境の変化に対応し、競争力を維持するためには、組織の柔軟性が不可欠です。環境が急速に変化する現代において、旧来の硬直的な組織では対応が難しくなります。
目指すべきポイント
- 意思決定のスピードを速める(階層構造の見直し、権限移譲の推進)
- 変化に対応できる組織文化を育てる(挑戦を歓迎する風土の形成)
- 部門間の連携を強化し、組織全体の一体感を高める
具体例
- 上下関係をできるだけ減らした組織へ移行し、トップダウンではなく現場の裁量を拡大
- 事業の変化に応じて、柔軟にチーム編成を行える体制を整備
2.業務の効率化・生産性向上
組織改革の重要なゴールの一つは、「業務の効率化」と「生産性の向上」です。無駄な業務や意思決定の遅れをなくし、よりスムーズに働ける環境を整えることで、企業全体の成長を促進します。
目指すべきポイント
- 不要な業務の削減(ペーパーレス化、会議の効率化など)
- IT・デジタルツールの活用による業務効率の向上
- 各部署の役割を明確にし、業務の重複をなくす
具体例
- 承認の手続きを簡単にし、意思決定を速める
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し、定型業務を自動化
3.従業員の力を引き出し、成長を支える仕組みづくり
組織改革は、単なる業務改善だけでなく、「人が活躍できる組織づくり」 を目指すことも重要です。従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境を整え、成長を促すことが、企業全体の成長につながります。
目指すべきポイント
- 適材適所の人員配置(個々の強みを活かす)
- 社員のキャリア形成を支援し、成長機会を提供する
- 柔軟な働き方を導入し、仕事と私生活のバランスを整える
具体例
- 若手社員にも責任のある仕事を任せ、成長の機会を増やす
- 働き方改革を推進し、リモートワークやフレックス制度を導入
4.組織文化の改革とエンゲージメント向上
組織の文化や風土は、社員のモチベーションや働きやすさに大きな影響を与えます。組織改革では、社員が働きがいを感じられる環境を作ること も重要なゴールの一つです。
目指すべきポイント
- 透明性の高い組織運営(情報共有の促進、風通しの良いコミュニケーション)
- 企業のビジョンや価値観を浸透させ、社員の意識を統一
- 社員同士の協力を促進し、チームワークを強化
具体例
- 経営陣が定期的に社員と対話し、意見を吸い上げる場を作る
- フィードバック文化を根付かせ、上司と部下が双方向の対話を行う
5.企業の持続的な成長と新たな発想の実現
最終的に、組織改革のゴールは「企業が持続的に成長し続けること」です。そのためには、新しいアイデアを生み出し、変化を恐れずに挑戦する文化を作ることが不可欠です。
目指すべきポイント
- 新規事業や新しい発想を生み出せる環境の整備
- 社員が積極的にアイデアを提案できる仕組みの構築
- 社内起業やプロジェクト制を導入し、挑戦を促す
具体例
- 社員の新規事業提案を募集し、成功すれば実際にプロジェクト化する制度を導入
- 失敗を恐れずチャレンジできる風土を作る(例:「失敗を賞賛する社内表彰制度」)
3.ゴール設定のポイント
組織改革を成功させるためには、明確なゴール設定が不可欠です。ゴールを設定する際のポイントを以下にまとめます。
1.組織全体の方向性と一致させる
組織改革のゴールは、企業のビジョンや中長期戦略と連携している必要があります。単なる部分最適ではなく、全体最適を考えたゴールを設定しましょう。
2.数値で測れる指標を設定する
「業務の効率化」や「社員のエンゲージメント向上」などの抽象的な目標ではなく、「意思決定のスピードを30%向上」「社員満足度を80%以上にする」達成度を測るための具体的な指標(KPI:重要業績評価指標)を設定することが重要です。
KPIとは、目標の達成度を数値で測るための基準を指します。
3.社員が納得できる目標を掲げる
組織改革は、社員の協力が不可欠です。経営層だけでなく、社員にとっても意義のあるゴールを設定し、改革の必要性を理解してもらうことが成功の決め手となります。特に、社員自身が「自分の成長や働きやすさにどうつながるのか」を実感できる目標設定が重要です。
組織改革のゴールは、柔軟な組織作り、生産性向上、人材の活用、組織文化の変革、そして持続的な成長など、幅広い分野に及びます。明確なゴールを設定し、改革の方向性を共有することで、組織全体が一丸となって変革に取り組むことができます。
組織改革の流れとタイミング

会社の組織改革を成功させるには、単なる施策の実行ではなく、適切な進め方とタイミングを押さえることが不可欠です。改革の進行にはいくつかの段階があり、それぞれの場面に応じた適切な対応が求められます。
ここでは、組織改革の基本的な流れと、実施すべきタイミングについて詳しく解説します。
1.組織改革の流れ
1.現状分析と課題の明確化
組織改革の第一歩は、自社の現状を正しく把握することです。この段階では、以下のような手法を活用して課題を洗い出します。
従業員アンケート・ヒアリング
従業員の声を収集し、現場の課題を把握する。
業績データの分析
売上や生産性などの指標を確認し、どこに問題があるのかを特定する。
競合分析
業界の動向や競合他社と比較し、自社の強み・弱みを整理する。
課題の明確化が不十分だと、ピントのずれた改革を行い、逆に現場の混乱を招くことがあります。そのため、「なぜ改革が必要なのか?」を徹底的に議論し、経営層と現場の認識をすり合わせることが重要です。
2.目標設定とビジョンの策定
次に、組織改革の目指すべき方向性を定めます。目標が曖昧だと、改革の進捗が測れず、現場に浸透しにくくなります。
目標設定のポイントは、以下のような具体的な指標を持つことです。
- 売上の〇%向上
- 離職率を△%改善
- 社内コミュニケーションの向上(定量的な指標を設定)
- 新規事業の成功率を□%まで引き上げる
また、目標設定と同時に、「なぜこの目標を達成するのか?」というビジョンを明確にし、社員が共感できる形で発信することが重要です。
3.具体的な施策の立案と設計
次のステップでは、改革を実行するための具体的な施策を設計します。組織改革の施策には以下のようなものがあります。
組織構造の変更
部署の統廃合、フラット化、機能別組織への移行など
評価制度の見直し
成果主義の導入、360度評価の実施など
業務の進め方の見直しと改善
DXの導入、ペーパーレス化など(デジタル技術を活用した業務の効率化)
企業文化の改革
心理的安全性の確保、フィードバック文化の定着など
この段階では、「実現可能性」と「現場の負担」を考慮しながら、優先順位をつけて施策を選定していく必要があります。
4.実行とモニタリング
施策が決定したら、実行に移します。ただし、一気に大改革を進めるのではなく、「小さく始めて、大きく展開する」方法が効果的です。
試験導入(パイロット施策)
まずは一部の部署やチームで施策を試し、その結果をもとに改善を行う。
PDCAサイクルの運用
PDCAサイクルとは、Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Act=改善を繰り返し、業務を継続的に改善する手法。施策の効果を定期的にモニタリングし、必要に応じて修正する。
社内への浸透施策
社員への説明会や研修を通じて、改革の意義を伝え、協力を促す。
この段階で現場の抵抗を受けることも多いため、リーダーシップを発揮しながら、組織の意識改革を進めることが求められます。
5.定着とさらなる改善
改革を一度実施しただけでは、定着しないことが多いです。継続的に組織をモニタリングし、必要に応じて追加施策を打つことが重要です。
- 定期的なアンケート・ヒアリングの実施
- データを活用した効果測定
- 経営層による定期的な進捗確認
- 成果を上げた組織への特別な評価や報酬の仕組みを導入
また、環境の変化に応じて組織のあり方も進化させる必要があります。長期的な視点を持ち、常に改革の方向性を見直すことが不可欠です。
2.組織改革を実施する最適なタイミング
組織改革の成功には、適切なタイミングを見極めることが重要です。以下のような状況では、改革を進める絶好の機会となります。
1.業績が低迷しているとき
売上の減少や市場シェアの低下が見られる場合、組織の抜本的な見直しが求められます。特に、競争環境が変化している場合は、迅速な対応が必要です。
2.事業拡大・企業合併のタイミング
新規事業の立ち上げや企業の合併・買収を行う際には、新しい組織体制を整える絶好の機会です。これを怠ると、統合後に組織内で意見の対立が起こったり、業務がスムーズに進まなくなったりする可能性があります。
3.組織の成長が鈍化したとき
売上や社員数は増えているのに、意思決定が遅くなったり、社員のモチベーションが低下したりする場合、組織の構造を見直す必要があります。
4.経営陣の交代
新しい経営者が就任するタイミングでは、組織改革がスムーズに進みやすくなります。トップダウンでの意思決定が可能になり、新しい戦略に沿った改革が実施しやすくなります。
5.外部環境の変化
法改正や市場の変動(例:DX化の進展、働き方改革の推進)によって、既存の組織運営では対応が難しくなるケースもあります。こうした外部環境の変化に応じて、組織を変革することが求められます。
組織改革は、一度実施すれば終わりではなく、継続的に取り組むべきです。現状分析から始まり、目標設定、施策立案、実行、モニタリング、そして定着と改善まで、一連の流れを丁寧に進めることが成功を左右します。
また、改革のタイミングを見極め、適切な時期に着手することも重要です。
組織改革は企業の成長に不可欠な取り組みであり、計画的かつ柔軟に進めていくことが求められます。
組織改革にはマネジメントが必須

組織改革を成功させるためには、単なる制度変更や組織構造の見直しだけではなく、それを適切に運用・定着させる「マネジメント」が不可欠です。マネジメントが機能しなければ、せっかくの改革も絵に描いた餅となり、現場の混乱を招くだけで終わってしまう可能性があります。
ここでは、組織改革におけるマネジメントの重要性と、成功のためのポイントを解説します。
1.なぜ組織改革にはマネジメントが必要なのか?
組織改革は、「組織のあり方を根本から見直し、より良い形へと生まれ変わらせる取り組み」です。しかし、組織は人によって構成されており、変革には必ず「人の抵抗」が伴います。マネジメントの役割は、こうした抵抗を最小限に抑えつつ、新たな仕組みや文化を定着させることです。
マネジメントの役割
ビジョンの提示
組織改革の目的や意義を明確にし、全社的に共有する。
リーダーシップの発揮
変革を主導するリーダーが、現場と経営層をつなぐ橋渡し役となる。
変革プロセスの管理
ステップごとに進捗を管理し、適宜軌道修正を行う。
従業員の意識改革
変革を前向きに受け入れ、主体的に取り組めるよう支援する。
これらの要素が機能しなければ、改革は表面的なものにとどまり、持続可能な変化を生み出すことは難しくなります。
2.組織改革を阻む主な課題
組織改革を進める上で、以下のような課題が発生しやすいとされています。
1.変革への抵抗
組織内には「変化を避ける心理的傾向」が働き、新しい制度や仕組みに対して抵抗する人が出てきます。「以前のやり方のほうが良かった」「なぜ変えなければならないのか」といった声が上がり、改革の足かせになることがあります。
2.経営層と現場の認識のズレ
改革の方向性を決定するのは経営層ですが、実際にその変革を実行するのは現場です。経営層の意図が現場に正しく伝わらない場合、施策が形骸化し、改革が進まない原因になります。
3.目標や評価基準の不明確さ
改革の成功を判断する基準が曖昧だと、従業員のモチベーションが低下し、効果的な実行が難しくなります。
4.マネジメント層のスキル不足
現場のリーダー層が適切に変革をマネジメントできない場合、従業員の混乱を招き、結果として改革が失敗に終わることがあります。
3.組織改革を成功させるマネジメントのポイント
成功する組織改革には、マネジメント層が適切に変革をリードし、現場を巻き込むことが不可欠です。以下のポイントを意識することで、改革の実行力を高めることができます。
1.変革のビジョンを明確にし、共有する
組織改革の目的や目指す姿を、経営層だけでなく従業員全員と共有することが重要です。単なる「業務改革」ではなく、「組織がどう変わるのか」「なぜ必要なのか」を理解させることで、従業員の納得感を高められます。
2.変革を段階的に進める
一度に大きな変革を実施すると、現場の混乱を招くリスクがあります。段階的に変化を進め、節目を設けて進捗を管理しながら進めることが効果的です。
3.経営層と現場の双方向のコミュニケーションを強化する
経営層からの上からの指示だけでなく、現場の意見を吸い上げる現場からの意見の吸い上げの仕組みを整えることが不可欠です。双方向のコミュニケーションを通じて、現場の理解を深め、納得感を高めるします。
4.組織文化の変革を意識する
組織改革は単なる制度変更ではなく、組織文化にも影響を与えます。経営陣が率先して新しい価値観や行動を示すことで、従業員が変化を受け入れやすくなります。
5.マネジメント層のスキル強化
変革を成功させるには、現場の管理職(ミドルマネジメント)がしっかりとしたマネジメント能力を持っていることが不可欠です。リーダーシップ研修やマネジメント研修を通じて、適切なスキルを習得させることが重要です。
組織改革は、単なるルール変更や組織構造の見直しではなく、マネジメントを通じて現場の納得感を高め、定着させることが重要です。
- 組織改革には「人の抵抗」が伴うため、適切なマネジメントが必要。
- 経営層と現場のずれを防ぐため、ビジョンの明確化と双方向のコミュニケーションが不可欠。
- 段階的に取り組み、組織文化の変革も視野に入れる。
- マネジメント層のスキルアップを図り、リーダーシップを強化する。
これらを意識することで、組織改革は「一時的な施策」ではなく、「持続可能な成長」へとつながるのです。
覚えておきたいフレームワーク

組織改革を進めるにあたり、適切なフレームワークを活用することで、論理的かつ体系的に変革を推進できます。フレームワークは現状の課題を整理し、解決策を導き出すための「道しるべ」となるため、組織の現状や目指すべきゴールに応じて最適なものを選ぶことが重要です。
ここでは、組織改革を推進する際に役立つ代表的なフレームワークを事例とともに紹介し、それぞれがもたらす効果について解説します。
1.7S(セブンエス)モデル
マッキンゼーが提唱した「7S」モデルは、組織を以下の7つの要素に分解し、バランスを取ることで組織改革を成功に導くフレームワークです。
| Strategy(戦略) | 組織の方向性や競争優位性を確保する計画 |
| Structure(組織構造) | 組織の階層、役割、権限の分配 |
| Systems(制度・システム) | 人事評価、業務の流れ、ITシステムなど |
| Shared Values(共通の価値観) | 組織文化や理念 |
| Style(経営スタイル) | リーダーシップの特徴や意思決定のスタイル |
| Staff(人材) | 人材の質や育成方針 |
| Skills(スキル) | 組織の持つ専門能力や技術力 |
組織改革を進める際、戦略や構造だけを見直しても成功しません。7Sモデルを活用することで、組織の各要素を総合的に捉え、バランスよく改革を進めることができます。特に、「共通の価値観(Shared Values)」を基盤としながら、その他の要素を整えていくことが重要になります。
事例
ある製造業の企業では、従来のトップダウン型の組織運営を見直すために、7Sモデルを活用しました。特に「Shared Values(共通の価値観)」を軸に、部門間の連携を強化する施策を実施した結果、意思決定のスピードが向上し、新規事業の成功率が高まりました。
2.KPIツリー
KPI(Key Performance Indicator:重要業績指標)ツリーは、最終的な目標(KGI)を達成するために必要な要素を分解し、各レベルのKPIを設定する手法です。
| KGI(Key Goal Indicator) | 最終目標(例:売上○○億円の達成) |
| KPI | KGIを達成するための中間指標(例:顧客単価の向上、新規顧客の獲得数の増加など) |
| KSF(Key Success Factors) | KPI達成のための具体的な取り組み(例:マーケティング施策の強化、営業スキルの向上) |
組織改革のゴールを明確にし、進捗を可視化できるため、改革の成功確率が高まります。定量的な指標を持つことで、感覚ではなくデータに基づいた意思決定が可能になり、変革の進捗管理が容易になります。
事例
企業向けのクラウドサービスを提供する会社では、売上向上を目的にKPIツリーを導入しました。最終的な目標として「契約数の増加」を掲げ、その下に「問い合わせ件数の増加」や「商談の成約率向上」といった指標を設定しました。その結果、営業活動の重点ポイントが明確になり、成約率が20%向上しました。
3.PDCAサイクル
PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルは、計画を立て(Plan)、実行し(Do)、検証し(Check)、改善を行う(Action)プロセスを繰り返すことで、継続的な成長を促すフレームワークです。
| Plan(計画) | 目標設定と戦略策定 |
| Do(実行) | 計画の実施 |
| Check(評価) | 実施結果の振り返り |
| Action(改善) | 改善策の導入 |
改革は一度で成功するものではなく、試行錯誤が必要です。PDCAサイクルを回すことで、計画の実行と改善を継続的に行い、組織改革の定着を図ることができます。特に、Check(評価)とAction(改善)を重視することで、実効性のある変革を実現できます。
事例
ある飲食チェーンでは、新たなメニュー開発プロジェクトにPDCAサイクルを活用。試験販売(Do)の結果をデータ分析(Check)し、改良を重ねながら商品を完成させました。これにより、ヒット商品が生まれ、売上が大幅に向上しました。
4.バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業の活動を「価値を生み出す仕組み」として捉え、どの部分を改善すれば競争力を高められるかを分析するフレームワークです。
主活動(製品やサービスの提供に直接関わる活動)
- 購買物流
- 製造(オペレーション)
- 出荷物流
- マーケティング・販売
- サービス など
支援活動(主活動を支える間接業務)
- 企業インフラ(経営管理)
- 人的資源管理
- 技術開発
- 調達活動 など
業務のどの部分が強みとなり、どこに改善の余地があるのかをはっきりと把握できます。特に、組織改革では『人的資源管理』や『企業インフラ(経営管理)』の最適化が重要なテーマとなるため、業務の流れや進め方を見直すのに有効です。
事例
あるアパレル企業は、バリューチェーン分析を用いて「在庫管理」の課題を特定しました。そこで、サプライチェーンの効率化を進め、需要予測の精度を向上させた結果、在庫コストを30%削減することに成功しました。
5.チェンジマネジメントモデル(ADKARモデル)
ADKARモデルは、個人の行動変容を促し、組織改革を円滑に進めるためのフレームワークです。
| Awareness(認識) | 変革の必要性を認識させる |
| Desire(意欲) | 変革に対する意欲を高める |
| Knowledge(知識) | 変革に必要な知識やスキルを提供する |
| Ability(能力) | 変革を実行できる能力を育成する |
| Reinforcement(定着) | 変革を組織文化として定着させる |
組織改革は最終的に「人の意識と行動の変革」に行き着きます。ADKARモデルを活用することで、社員一人ひとりが改革に前向きに取り組めるようになり、改革の成功確率が高まります。
事例
ある金融機関では、DX推進においてADKARモデルを活用しました。従業員の「認識(Awareness)」を高めるために研修を実施し、ITスキル向上のためのトレーニング(Knowledge・Ability)を強化。その結果、新システムの定着率が向上しました。
6.コッターの8段階の変革プロセス
ジョン・P・コッターは、組織変革を成功させるためのプロセスを8つのステップに整理しました。組織改革の現場では、「変革がなかなか定着しない」「改革への抵抗が大きい」といった問題が発生しがちですが、このモデルを活用することで、スムーズな変革を実現できます。
コッターの8段階
1.危機意識を高める(Establish a Sense of Urgency)
組織全体に「今すぐ変革が必要だ」という意識を持たせるために、組織改革が求められる理由を明確にし、危機感を共有する。
2.変革推進チームをつくる(Form a Powerful Guiding Coalition)
変革を主導するリーダーや影響力のある人物を集め、変革の推進チームを結成する。
3.ビジョンと戦略を策定する(Create a Vision for Change)
変革後の理想的な姿を示し、それを実現するための戦略を立てる。
4.ビジョンを周知する(Communicate the Vision)
組織内で繰り返しビジョンを伝え、全員が変革の目的を理解できるようにする。
5.従業員の自発的な行動を促す(Empower Others to Act on the Vision)
現場レベルで変革が進むよう、権限移譲を行い、組織内の障害を取り除く。
6.短期的な成功を生み出す(Generate Short-Term Wins)
小さな成功を積み重ねることで、改革が進んでいる実感を持たせ、士気を高める。
7.成果をもとにさらなる変革を推進する(Consolidate Gains and Produce More Change)
一度の成功に満足せず、継続的な改善を進めることで改革の定着を図る。
8.新しい方法を組織文化に定着させる(Anchor New Approaches in the Culture)
変革を一過性のものではなく、組織の文化として根付かせる。
コッターのモデルは、特に 「組織内の抵抗をどう乗り越えるか」 に重点を置いています。変革に対する心理的な壁を克服しながら、組織全体を巻き込んで改革を進められるのが大きなメリットです。短期的な成功を積み重ねながら、変革の勢いを生み出し、最終的に定着させるための道筋を示しています。
事例
ある小売業では、コッターのプロセスを活用し、変革推進チームを組織(Step2)し、短期的な成功事例を社内で共有(Step6)することで、改革への抵抗を減らしました。結果として、業務の効率化と売上増加につながりました。
7.レヴィンの変革モデル
クルト・レヴィンが提唱した「組織変革の3段階モデル」は、変革の基本的な流れを示すシンプルなフレームワークです。彼は組織を「氷」に例え、変革を 「解凍(Unfreeze)→ 変革(Change)→ 再凍結(Refreeze)」 の3つのプロセスで説明しました。
レヴィンの3段階の変革のプロセス
1.解凍(Unfreeze)
- 現在の組織のあり方を見直し、変革の必要性を理解させる。
- 既存のやり方を変えることへの抵抗を和らげるための準備段階。
2.変革(Change)
- 実際に新しい仕組みや文化を導入し、組織の動きを変える。
- この段階では、試行錯誤を重ねながら新しい行動を定着させる。
3.再凍結(Refreeze)
- 変革後の状態を標準化し、組織文化として定着させる。
- 過去のやり方に戻らないよう、制度・ルール・評価基準を見直す。
レヴィンのモデルは、組織の「心理的変化」に着目したシンプルなフレームワークであり、「変革の定着」を重視している点が特徴 です。特に、組織内で新しい取り組みを導入しても、それが定着せずに元の状態に戻ってしまうことが多いですが、レヴィンのフレームワークを意識することで、改革を組織文化へと浸透させることができます。
事例
ある老舗メーカーは、従来の働き方を見直し、リモートワークの導入を決定。しかし、初期段階(Unfreeze)で社員の不安が大きかったため、試験導入と説明会を実施(Change)。最終的に、全社的なリモートワークの定着(Refreeze)に成功しました。
組織改革を推進するには、適切なフレームワークを活用しながら、戦略的に進めることが重要です。
| 7Sモデル | 組織全体のバランスを見直す |
| KPIツリー | 目標を明確にし、進捗を可視化 |
| PDCAサイクル | 継続的な改善を実施 |
| バリューチェーン分析 | 価値創出プロセスを最適化 |
| ADKARモデル | 社員の意識改革を促進 |
| コッターの8段階の変革プロセス | 組織内の抵抗を乗り越えながら変革を推進 |
| レヴィンの変革モデル | 変革の心理的プロセスを整理し、定着を図る |
特に、組織改革の過程では、「人の意識や行動の変容」を促すことが成功のカギとなります。
コッターの8段階やレヴィンの変革モデルは、この「人の心理的な抵抗」や「組織文化の変化」を意識したフレームワークであり、組織改革の成功率を高めるうえで非常に有効です。
どのフレームワークを活用するかは、組織の課題や状況によって異なりますが、組み合わせて活用することで、より確実な変革を実現できるでしょう。
関連コンテンツ
まとめ
組織改革は、一時的な取り組みではなく、組織の持続的な成長を支える重要なプロセスです。変化が求められる背景を理解し、改革の目的を明確にすることで、組織全体が同じ方向を向き、効果的な取り組みが可能になります。
また、改革を成功させるには、適切なタイミングを見極め、段階的に進めることが重要です。そのためには、経営層のリーダーシップやマネジメントの力が不可欠であり、単なる制度や構造の変更ではなく、人の意識や行動の変革にも焦点を当てる必要があります。
本コラムで紹介したフレームワークを活用することで、組織改革をより体系的かつ実践的に進めることができます。しかし、最も大切なのは、組織内の一人ひとりが改革の意義を理解し、主体的に関わることです。
変革には時間がかかりますが、確かな方向性と適切な手法をもって取り組むことで、組織はより強く、しなやかに成長していくでしょう。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

コメント