時代の不確実性が増すとともに、市場競争が国境を越えて激化する中、企業は持続的な成長を目指しそれぞれが独自の経営戦略を策定しています。
企業が持続的な成長を実現するためには、経営戦略が明確になっていることが重要です。そこで、今回は「経営戦略」について、その定義や種類、フレームワークなどについて詳しく解説します。
Contents
「経営戦略」の定義

経営戦略は、企業が長期的な目標を達成し、競争優位性を確立するための計画や方針の体系的な体現です。この戦略は、組織の使命やビジョン、価値観に基づいて策定され、内外の環境要因や資源を活用して持続的な成長や成功を促進します。
目標の設定と方向性
経営戦略は、組織が達成したい長期的な目標や方向性を明確に示します。これには、利益の最大化、市場シェアの拡大、技術革新のリーダーシップ、社会的責任の実現などが含まれます。経営戦略は、組織の使命やビジョンに基づいて設定されるため、これらの目標は組織の核心的な価値観と一致しています。
環境分析と競争力
経営戦略は、外部環境や市場の動向、競合他社の動向などを詳細に分析し、組織の競争力を高めるための戦略を策定します。これには、PESTLE分析(政治、経済、社会、技術、法律、環境)、市場のポーターのファイブフォース分析、顧客ニーズの調査などが含まれます。この分析を通じて、組織は自社の強みや弱みを理解し、市場での競争力を向上させるための適切な戦略を構築します。
リソースの最適化とポートフォリオ管理
経営戦略は、組織のリソース(人材、資金、技術、ブランド価値など)を最適化するための計画を提供します。これには、事業ポートフォリオの管理や投資配分、財務戦略、人材管理などが含まれます。組織は、リソースを効果的に活用して競争優位性を確立し、長期的な成長を実現するための戦略的なアプローチを採ります。
成果の評価と戦略の調整
経営戦略は、定期的な評価とフィードバックを通じてその成果を測定し、必要に応じて戦略の調整や修正を行います。組織は、戦略の実行状況や市場の変化に応じて柔軟に対応し、目標達成に向けて持続的な改善を図ります。
経営戦略は、組織が持続的な競争優位性を確立し、市場でのリーダーシップを築くための重要な枠組みです。これは、組織が将来の不確実性や変化に対応し、成長と成功を維持するための基盤となります。
目的と必要性

経営戦略において目的と必要性は非常に重要です。これらは企業が長期的な目標を達成し、競争力を維持・強化するための指針となります。以下では、経営戦略の目的と必要性について詳しく説明します。
目的
長期的な成長と繁栄
経営戦略の主要な目的の1つは、企業が長期的な成長と繁栄を実現することです。これは、市場シェアの拡大、売上高と利益の増加、新規事業の開発などを通じて達成されます。
競争力の維持と強化
経営戦略は、競争激化する市場で企業が競争力を維持・強化するための重要な手段です。競合他社との差別化やコストリーダーシップの確立などの戦略的アプローチによって、企業は競争優位性を獲得できます。
リソースの効率的な活用
経営戦略は、企業のリソースを効率的に活用し、最大限の価値を生み出すための枠組みを提供します。資金、人材、技術、ブランド価値などのリソースを最適化することで、企業は競争力を高め、持続可能な成長を実現できます。
市場環境への適応
経営戦略は、急速に変化する市場環境に適応するための重要な手段です。新技術の登場、規制の変更、消費者の嗜好の変化などに対応するために、企業は柔軟性を持った戦略を策定する必要があります。
ステークホルダー価値の最大化
経営戦略は、企業がステークホルダー価値を最大化することを目指します。株主、顧客、従業員、地域社会など、企業に関係するすべてのステークホルダーの利益をバランス良く考慮し、最良の結果を提供することが求められます。
必要性
方向性の明確化: 経営戦略は企業の方向性を明確にするために不可欠です。明確な目標と戦略は、組織全体が一貫した方向に向かって行動し、資源を集中的に活用することを可能にします。
意思決定の支援
経営戦略は意思決定のプロセスを支援します。情報収集、分析、リスク評価などを通じて、経営者は戦略的な決断をより客観的かつ効果的に行うことができます。
リソースの効率的な配置
有限なリソースを最適化するためには、経営戦略が不可欠です。資金、人材、時間などのリソースを最適なプロジェクトや活動に割り当てることで、企業の成果を最大化することができます。
競争力の獲得
競争激化する市場環境では、競争力を獲得することが生存に不可欠です。経営戦略は、企業が競争上の優位性を確立し、市場での地位を強化するための道筋を提供します。
変化への適応性
経営戦略は、市場の変化や環境の変動に対応するための柔軟性を確保します。迅速かつ効果的な対応ができるように、企業は戦略を定期的に見直し、修正する必要があります。
経営戦略の目的と必要性は、企業が競争激化する市場環境で生き残り、成長するために不可欠な要素です。適切な戦略の策定と実行は、企業の持続可能な成功に不可欠な要素となります。
3つの戦略①企業戦略
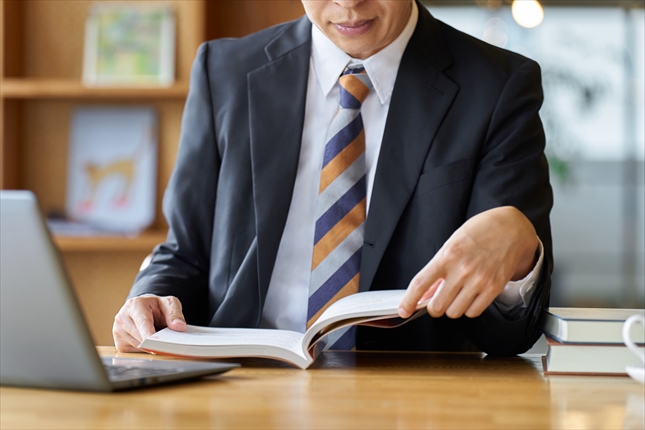
企業戦略は、企業が長期的な目標を達成し、競争力を維持・強化するための全体的な計画や方針を指します。この戦略は、企業の使命やビジョン、価値観に基づいて策定され、事業領域やリソースの配置、成長戦略、競争上の差別化などを含みます。以下では、企業戦略の重要性、基本的なアプローチ、および具体的な戦略の例について詳しく説明します。
企業戦略の重要性
企業戦略は、次の点で重要な役割を果たします。
目標達成の指針
企業戦略は、組織がどのような方向に進むかを明確に示し、目標達成に向けて従業員の行動を指針とします。
競争力の構築
適切な企業戦略によって、企業は市場での競争力を構築し、顧客のニーズに適切に対応することができます。
リソースの効果的な活用
企業戦略は、限られたリソースを最適に活用するための計画を提供します。これにより、組織の成果を最大化し、効率性を向上させます。
成長と持続可能性
適切な戦略が採用されることで、企業は成長を促進し、持続可能なビジネスモデルを確立することができます。
企業戦略のアプローチ
企業戦略の策定には、以下のようなアプローチが一般的に用いられます。
外部環境の分析
市場の動向や競合状況を把握し、外部環境の変化に対応するための情報収集が重要です。
内部資源と能力の評価
自社の強みや弱みを理解し、競争上の優位性を構築するための内部資源や能力を評価します。
目標設定
企業のビジョンや使命に基づき、具体的な目標を設定します。これにより、組織全体が目指す方向が明確になります。
戦略の策定と実行
上記の情報をもとに、適切な戦略を策定し、実行に移します。これには、リソースの配分やプロジェクトの管理などが含まれます。
企業戦略の例
市場リーダーシップ戦略
企業が市場のリーダーとなるために、ブランドの差別化や革新的な製品の開発に焦点を当てる戦略です。
成本リーダーシップ戦略
企業が市場で低価格を提供することによって、競争上の優位性を確保する戦略です。
差別化戦略
企業が独自の価値提供を行い、顧客のニーズに特化した製品やサービスを提供する戦略です。
成長戦略
企業が市場拡大や新規事業の開発などを通じて成長を促進するための戦略です。
企業は自社の状況や目標に応じて適切な戦略を選択し、実行に移すことで競争力を維持・強化し、持続可能な成長を実現することが求められます。
3つの戦略②事業戦略

事業戦略は、企業が競争環境で成功するために採用する計画や方法論を指します。これは、企業の目標や価値観に基づいて、事業を成長させ、競合他社から差別化し、市場での地位を築くための方法を戦略的に設計するプロセスです。以下では、事業戦略の重要性、その構築に必要な要素、そして成功するためのいくつかの一般的なアプローチについて説明します。
市場分析と競争分析
市場の動向や競合他社の戦略を分析し、自社の位置を理解することが重要です。顧客のニーズや嗜好、競合他社の強みや弱みを把握することで、戦略の方向性を決定する際の参考情報となります。
顧客志向の戦略
顧客のニーズを満たすことを中心に据えた戦略を構築することが重要です。顧客の声を聞き入れ、製品やサービスの改善を行うことで、顧客満足度を高め、競争優位性を確立することができます。
製品・サービスの差別化
競争激化する市場においては、製品やサービスの差別化が重要です。独自の価値提供を行い、顧客にとって他社との選択肢とならない魅力を持つ製品やサービスを提供することで、市場での地位を確立することができます。
成長戦略
事業の成長を促進するための戦略も重要です。市場開拓、新規製品の開発、M&Aなどの手段を活用して、事業を拡大し、収益を増加させることができます。
コストリーダーシップ戦略
低コストで製品やサービスを提供することで市場での競争優位性を確立する戦略です。生産効率の向上や原材料の調達コストの削減など、コスト削減に焦点を当てます。
差別化戦略
独自の価値提供やブランドイメージを構築することで、顧客のニーズに応える戦略です。製品やサービスの品質向上や革新的な機能の追加など、顧客にとって魅力的な要素を強調します。
集中戦略
特定の市場セグメントや地域に焦点を絞り、その領域で競争力を高める戦略です。競争が激しい広範な市場ではなく、ニッチな市場での強みを活かします。
以上のように、事業戦略は企業の成長と競争力確立のために不可欠な要素です。市場や競合状況を分析し、顧客志向の戦略を展開し、製品やサービスの差別化を図ることで、企業は持続可能な成功を達成することができます。
3つの戦略③機能戦略

機能戦略は、企業がその事業戦略を達成するために、組織内の特定の機能や部門に焦点を当てて採用する戦略です。機能戦略は、各機能が目標達成に向けて効果的に機能し、組織全体がシームレスに連携して働くように設計されます。以下では、機能戦略の重要性、主要な機能領域、および成功するためのアプローチについて説明します。
機能戦略は、組織が事業戦略を実現するために必要なリソースや能力を確保し、最適化するために不可欠です。組織内の様々な機能が協力して、製品やサービスの開発、生産、販売、および顧客サポートを最適化することで、事業戦略の成功に向けた基盤を築くことができます。
主要な機能領域には以下のものがあります。
マーケティングおよび販売
マーケティングおよび販売機能は、顧客ニーズを理解し、製品やサービスを市場に適切に位置付けるための重要な役割を果たします。市場調査、プロモーション、営業戦略の策定などが含まれます。
製品開発およびイノベーション
製品開発機能は、市場ニーズに応える新製品やサービスの開発を担当します。顧客フィードバックの収集、競合分析、技術革新の推進などが含まれます。
生産およびオペレーション
生産およびオペレーション機能は、製品やサービスの生産性と効率性を最大化し、コストを最適化することに焦点を当てます。生産計画、資材調達、品質管理、生産プロセスの改善などが含まれます。
人事および組織開発
人事および組織開発機能は、組織内の人材を管理し、組織の目標達成に向けて適切な人材戦略を策定します。採用、トレーニング、パフォーマンス評価、組織文化の構築などが含まれます。
クロス機能連携
各機能領域がシームレスに連携し、情報やリソースを共有することが重要です。マーケティングからの市場情報を製品開発にフィードバックし、生産部門との協力によって市場ニーズに応える製品を効率的に製造するなど、異なる機能間の連携を強化します。
技術の活用
技術を活用して、各機能を強化し、業務プロセスを効率化します。例えば、製品開発においてはCADソフトウェアやシミュレーションツールを利用して設計を最適化し、生産部門にスマートファクトリーソリューションを導入して生産プロセスを最適化するなどが挙げられます。
リーダーシップと文化の醸成
リーダーシップと組織文化の醸成は、組織内の機能が協力して働くための重要な要素です。リーダーはビジョンを明確にし、チームの方向性を示し、組織文化を通じて協力と効率性を促進します。
機能戦略は、事業戦略の成功に不可欠な要素であり、組織内の機能が効果的に連携し、組織全体が目標に向かって一致団結するための基盤を提供します。組織は各機能領域を適切に管理し、異なる機能間の連携を強化することで、事業戦略の実現に向けて効果的に取り組むことができます。
策定する前にまずは経営理念やビジョンを明確にする

経営戦略を策定する前に、経営理念やビジョンを明確にすることは重要です。以下に、その重要性を示す5つの項目を述べます。
方向性の確立
経営理念やビジョンは、企業の方向性を示すものです。経営者や従業員が企業の目標や価値観を理解し、共有することで、一貫性のある戦略の策定や実行が可能になります。方向性が明確であれば、組織全体が同じ目標に向かって努力することができます。
利害関係者への説明
経営理念やビジョンは、顧客、従業員、株主などの利害関係者にとって重要な情報源です。これらの要素を明確にすることで、利害関係者とのコミュニケーションが円滑になり、彼らの信頼を獲得しやすくなります。また、企業の方針や目標に共感する人々が集まりやすくなり、組織の成長につながります。
競争力の向上
経営理念やビジョンが明確であれば、企業は自らの強みや競争優位性を理解しやすくなります。その結果、競合他社との差別化が可能になり、市場での競争力が向上します。また、経営理念やビジョンに基づいた戦略の策定や実行は、企業の成長戦略を強化し、持続的な競争優位性を築くための基盤となります。
組織文化の形成
経営理念やビジョンは、組織文化の形成に重要な役割を果たします。これらの要素が従業員に浸透することで、共通の価値観や行動基準が確立され、組織全体が一体となって目標に向かって努力することができます。組織文化が強固であれば、従業員のモチベーションや生産性が向上し、組織の成果に直結します。
変化への適応
経営理念やビジョンは、外部環境の変化に対する組織の適応力を高めるための指針となります。変化する市場や技術の動向に対応するためには、経営理念やビジョンに基づいた柔軟な戦略の策定や実行が必要です。これらの要素が明確であれば、組織は変化に対して迅速かつ効果的に対応し、持続的な成長を実現することができます。
経営理念やビジョンを明確にすることは、経営戦略を策定する上での基盤となるだけでなく、企業の成長や競争力向上、組織文化の形成など、さまざまな面で重要です。これらの要素を考慮しながら、経営理念やビジョンを策定し、経営戦略の成功につなげていくことが求められます。
策定から実行までの基本的な流れ

経営戦略を策定から実行までの基本的な流れにはいくつかの重要なステップがあります。以下にその流れを詳しく説明します。
現状の評価と目標の設定
最初のステップは、組織が現在位置している状況を評価し、将来の目標を設定することです。これには、内部の強みや弱み、外部の市場状況や競合状況を分析し、経営陣や関係者が共有するビジョンや目標を明確にすることが含まれます。
戦略の策定
現状分析と目標設定を踏まえて、経営戦略を策定します。戦略は、企業が競争優位性を確立し、目標を達成するための計画です。この段階では、SWOT分析やポーターの競争戦略、BCGマトリックスなどのフレームワークを活用して戦略を構築します。
計画の具体化とリソースの確保
策定された戦略を実現するために、具体的な計画を立てます。この際には、各戦略的イニシアチブやプロジェクトを明確にし、必要なリソース(人材、資金、技術など)を確保します。また、タイムラインや責任者を定め、計画の実行可能性を確保します。
組織の整備とコミュニケーション
経営戦略を実行するためには、組織内での適切な体制やプロセスを整備する必要があります。これには、戦略的な役割や責任の明確化、組織文化の調整、情報共有やコミュニケーションの強化などが含まれます。組織のメンバーが戦略に共感し、自らの役割を理解し、共有することが重要です。
実行とモニタリング
実行段階では、計画を実行し、戦略的目標を達成するための行動を起こします。これには、プロジェクト管理、リーダーシップ、コーディネーション、問題解決などが必要です。同時に、進捗状況や成果を定期的にモニタリングし、必要に応じて調整を行います。
評価と改善
戦略の実行が進むにつれて、その効果や成果を評価し、戦略の改善や修正が必要になる場合があります。定期的な評価とフィードバックを通じて、問題点や改善の余地を特定し、戦略の持続的な最適化を図ります。
このように、経営戦略の策定から実行までのプロセスは継続的であり、柔軟性と適応性が求められます。経営者やマネージャーは、環境の変化や市場の要求に応じて戦略を柔軟に調整し、組織全体が目標に向かって一体となって取り組むことが重要です。
企業戦略との違い

経営戦略と企業戦略は、似ているようで異なる概念です。以下に、両者の違いを示します。
定義と範囲
経営戦略
企業が全体として長期的な目標を達成するための計画や手段を指します。これには、事業領域の選択、成長戦略、リソースの配分、競争優位性の構築などが含まれます。
企業戦略
特定の事業部門や機能領域に焦点を当てた戦略を指します。これは、商品やサービスの開発、市場セグメンテーション、販売チャネルの選択など、個々のビジネスや機能の戦略を意味します。
対象と規模
経営戦略
企業全体の視点から検討され、組織全体の方向性や戦略的な重点に関わる決定を含みます。
企業戦略
特定の事業部門や製品ラインなど、企業の一部に焦点を当てています。これは、個々の部門やプロジェクトに関連する戦略的な問題に対処することを意味します。
時間の視点
経営戦略
長期的な視点で検討されます。これは、企業が将来の成長や持続可能な競争力を確保するための戦略的な方向性を示します。
企業戦略
中期や短期の目標に焦点を当てることがあります。これは、特定の製品やサービスの成功を促進するための戦略的な取り組みを指します。
決定のレベル
経営戦略
最高経営責任者(CEO)や経営陣などの上級管理職が策定し、承認します。これは、企業全体のビジョンと目標を反映したものです。
企業戦略
中級管理職や部門長など、特定の事業部門や機能の責任者が策定します。これは、個々のビジネスユニットや部門のニーズや目標に基づいています。
関連性と連携
経営戦略
企業戦略と密接に関連しています。経営戦略が企業の全体的な方向性を定め、企業戦略がその方向性を具体的な戦術や計画に落とし込みます。
企業戦略
経営戦略の実現を支援します。個々の事業部門や機能が自らの戦略を立て、それを統合して経営戦略の達成に貢献します。
これらの違いからもわかるように、経営戦略と企業戦略は密接に関連していますが、異なるレベルや範囲での概念であり、それぞれが異なる目的と視点を持っています。企業は、両方の戦略を適切に調整し、統合することで、長期的な成長と競争力の確保を目指すことが重要です。
マーケティング戦略との違い

経営戦略とマーケティング戦略は、企業が目標達成のために採るアプローチであり、互いに密接に関連していますが、異なる側面を持ちます。以下では、それぞれの違いについて解説します。
経営戦略
企業全体の方向性や長期的な目標を定めるための戦略です。これは、組織の使命やビジョンに基づき、競争環境や資源、市場の動向などを考慮して策定されます。経営戦略は、企業の価値創造や成長戦略を決定し、リソースの配置や事業ポートフォリオの構築など、全体的な方針を確立します。
マーケティング戦略
特定の製品やサービスの販売促進や市場シェアの拡大を目指すための戦略です。これは、市場分析や顧客ニーズの把握、競合状況の分析などを通じて、製品やサービスの価値提供方法を計画し、市場での競争力を強化するためのアクションを立案します。マーケティング戦略は、広告やプロモーション、価格戦略、販売チャネルの選択など、市場での競争優位性を獲得するための手段を含みます。
経営戦略とマーケティング戦略の違いは、主に以下の点で見ることができます。
範囲と視点の違い
経営戦略
企業全体の方向性や長期的な目標に焦点を当てます。
マーケティング戦略
製品やサービスの市場での位置付けや顧客との関係構築に焦点を当てます。
決定のレベルの違い
経営戦略
最高経営責任者(CEO)や経営陣などのトップレベルで決定されます。
マーケティング戦略
通常はマーケティング部門や担当者が策定し、実行します。
時間の視点の違い
経営戦略
長期的な視野に立って策定され、通常は数年から数十年にわたるビジョンを対象とします。
マーケティング戦略
中期的な視点であり、通常は数か月から数年の期間をカバーします。
対象となる要因の違い
経営戦略
市場以外の要因(例:組織内のリソース、技術の進歩、法的環境など)も考慮に入れます。
マーケティング戦略
主に市場や顧客のニーズ、競合状況など外部環境に焦点を当てます。
経営戦略とマーケティング戦略は、企業の成功に不可欠な要素であり、相互に補完しあいながら、統合されたアプローチを取ることが重要です。経営戦略が企業の方向性を定め、マーケティング戦略がその方向性を具体化して市場での競争力を高める役割を果たします。
押さえておきたいフレームワーク

経営戦略を構築する上で押さえておくべきフレームワークにはいくつかあります。以下に、その中でも特に重要なフレームワークをいくつか紹介します。
SWOT分析
SWOT分析は、企業の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を明らかにするための枠組みです。
これにより、企業は内外の環境要因を理解し、自社の競争優位性を活かしながら、脅威に対処し、機会を最大限に活用する戦略を立てることができます。
ポーターの競争戦略
マイケル・ポーターによって提唱された競争戦略は、コストリーダーシップ、差別化、集中戦略の3つに分類されます。
コストリーダーシップ戦略は低価格を競争優位とし、差別化戦略は独自性や付加価値を提供して競争優位を築くことを目指します。
適切な競争戦略を選択することで、企業は市場での地位を確立し、収益性を向上させることができます。
BCGマトリックス
Boston Consulting Group(BCG)が提唱したこのマトリックスは、製品や事業ポートフォリオを分析し、成長率と市場シェアに基づいて4つのカテゴリーに分類します。
スター、キャッシュ・カウ(現金源)、疑問児童、犬(ドッグ)の各セグメントは、戦略的な投資や撤退の判断に役立ちます。
アンソフの成長マトリックス
アンソフの成長マトリックスは、市場開拓、市場開発、製品開発、多角化の4つの成長戦略を提供します。
このフレームワークは、企業が現在の市場と製品にとどまるか、新しい市場や製品に進出するかを決定する際に役立ちます。
7Sモデル
McKinsey & Companyが提唱したこのモデルは、組織の戦略的変革を促進するための7つの要素(Strategy、Structure、Systems、Shared values、Skills、Style、Staff)を定義します。
このフレームワークは、組織内の相互関係と影響を分析し、戦略の実装に必要な変更を促進します。
これらのフレームワークは、経営戦略を策定し、実行する際に非常に役立ちます。ただし、状況や産業によって適用するフレームワークは異なる場合があります。経営者やマネージャーは、これらのフレームワークを組織の独自のニーズや状況に合わせて適用し、最適な戦略を策定することが重要です。
まとめ
経営戦略は、企業が長期的な目標を達成し、競争力を維持・強化するための計画や方針のことです。経営戦略は、外部環境の変化や内部の強み・弱みを分析し、市場の需要や競合状況を考慮して策定されます。これにより、企業は競争優位性を築き、利益を最大化するための取り組みを展開します。
経営戦略は、事業領域の選択、市場参入のタイミング、製品やサービスの差別化、リソースの配分などを含みます。そのため、経営戦略の策定には、情報収集・分析、戦略の設計・実行、評価・改善のプロセスが必要です。自社の目指す姿や現状を適切に把握して、持続的な成長を実現できる経営戦略を策定・実行しましょう。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

コメント