企業が持続的に成長するためには、組織運営の最適化が必要です。それには、適切なマネジメントによって人材や仕組みを活かすことが重要です。本コラムでは、組織運営の基本から実践的なスキルまでを解説。
経営者や人事担当者の皆さまに役立つ情報を提供します!
「組織運営」とは

企業が持続的に成長し、競争力を維持するためには、適切な「組織運営」が欠かせません。
以下では、組織運営の基本的な考え方を解説します。
組織運営の基本概念
組織運営とは、単に会社を動かすための管理業務を指すものではなく、 「組織の目的を達成するために、人・仕事の流れ・働く環境を整えること」 です。企業においては、「経営戦略」や将来の理想像や目指す方向性を示す「ビジョン」を具現化するために、部門ごとの役割を明確にし、社員が適切な役割を果たせるように支援することが求められます。
組織運営には、以下のような要素が含まれます。
| 組織構造の設計 | ピラミッド型(上層部が意思決定を行い、指示が階層的に下りていく伝統的な組織構造)、フラット型(管理層を減らし、現場の意思決定権を強めた組織構造)、マトリックス型(一人の社員が複数の上司やチームに属し、部門横断的にプロジェクトを進める組織構造) など |
| 業務の流れの効率化 | 仕事の流れを明確にし、無駄を減らす |
| リーダーシップと意思決定 | 経営層の指針と現場の柔軟性 |
| 人材育成と評価制度 | 適材適所の配置、キャリアの道筋の設計 |
| 企業文化を築く | 価値観や行動指針の共有 |
企業の規模や業種によって適切な組織運営の形は異なりますが、共通して言えるのは、
「戦略を支える組織づくり」 が不可欠
だという点です。
組織運営を支える「人」と「仕組み」
組織運営には、「人」と「仕組み」の両方を整えることが求められます。
1.人材のマネジメント
組織は人によって成り立っています。そのため、 適切なリーダーシップと人材育成が大切 です。リーダーには、以下のような役割が求められます。
方向性を示す
企業のビジョンや戦略を明確に伝え、チームを導く
環境を整える
社員が能力を発揮できるような仕組みを整える
評価とフィードバックを行う
公正な評価制度を設計し、成長を促す
2.組織運営の仕組みづくり
人だけでなく、仕組み(制度・ルール・手順)が整っていないと、組織は機能しません。たとえば、以下のような仕組みが必要になります。
意思決定の流れ
誰がどのように判断を下すのか
業務の標準化
特定の人にしかできない業務を減らし、効率化する
評価制度の設計
成果を適切に評価し、成長を促す
仕組みがしっかりしていると、担当者が変わっても仕事がスムーズに進み、組織を安定して運営することができます。
「組織運営」とは、単なる業務管理ではなく 企業の目標を実現するための「人」と「仕組み」を整えること です。適切な組織運営を行うことで、企業の戦略実行力が高まり、企業や仕事に対する愛着や意欲である社員のエンゲージメント(企業や仕事に対する愛着や意欲)が向上し、変化に強い組織を作ることができます。
組織マネジメントの必要性

企業が持続的に成長し、変化の激しい市場環境の中で競争力を維持するためには、組織マネジメントの適切な実践が不可欠 です。組織マネジメントは単なる管理業務ではなく、企業のビジョンを実現し、従業員一人ひとりが力を発揮できる環境を作るための「戦略的な経営手法」と言えます。
ここでは、なぜ組織マネジメントが重要なのかを、具体的な視点から解説していきます。
1.なぜ組織マネジメントが必要なのか?
組織マネジメントが企業にどのような価値をもたらすのか、以下の4つの視点から解説します。
1.組織の持続的成長を実現する
企業が長期にわたって成長し続けるためには、一過性の成功ではなく、安定した組織運営と進化を続ける仕組みが不可欠です。
市場環境が変化しても、組織が柔軟に適応しながら持続的に成長するには、社員一人ひとりの意欲と能力を引き出し、組織全体で学習と改善を積み重ねることが重要です。適切な仕組みとリーダーシップのもとで、変化をチャンスに変えられる組織こそが、持続的成長を実現できるのです。
2.イノベーションを促進する
企業が競争力を維持するためには、変化を恐れずに新しい価値を生み出すことが大切です。しかし、新しい製品やサービス、ビジネスモデルを生み出すイノベーション(新しい製品やサービス、ビジネスモデルを生み出すこと)は偶然生まれるものではなく、組織マネジメントによって意図的に促進されるものです。
3.企業文化を築き、一体感を生み出す
企業文化は、企業の持続的な成功にとって欠かせないな要素です。組織マネジメントが適切に行われることで、社員が共通の価値観を持ち、一体感のある組織が形成されます。
4.社会的責任(CSR)を果たし、ブランド価値を高める
近年、企業には利益の追求だけでなく、社会的責任(CSR)やサステナビリティへの対応が求められています。組織マネジメントが適切に行われることで、これらの取り組みを戦略的に進めることが可能になります。
2.組織マネジメントの効果とは?
適切な組織マネジメントを実施すると、企業は以下のようなメリットを得られます。
1.事業戦略の実行力が向上
組織マネジメントがしっかり機能していると、経営層の意思決定がスムーズになり、現場への落とし込みが迅速になります。 たとえば、経営戦略が社員に適切に伝わり、それに基づいて目標設定や行動計画が立てられるようになります。その結果、企業のビジョンが形になり、組織全体の方向性が統一されます。
2.従業員のエンゲージメント向上
組織マネジメントが適切に行われると、従業員が自分の役割や目標を明確に理解できるため、仕事への意欲や帰属意識が向上します。 また、評価制度が整っていると、自分の成果が正当に評価されるため、モチベーションアップにつながります。
3.市場変化への対応力が向上
市場環境は常に変化しており、企業は柔軟に対応する必要があります。組織マネジメントが機能していると、変化に応じた迅速な意思決定と組織の適応が可能になります。
3.組織マネジメントの導入ステップ
組織マネジメントを強化するためには、以下のステップが有効です。
1.現状の課題を把握する
- 社員の意見をヒアリングし、組織の課題を洗い出す。
- 組織の強み・弱みを分析する。
2.組織のビジョンと目標を明確化する
経営方針や中長期的な目標を整理し、全社員に共有する。
3.組織構造と役割分担を最適化する
- ピラミッド型、フラット型、マトリックス型など、最適な組織構造を選定。
- 部署ごとの役割を明確にし、業務の属人化を防ぐ。
| ピラミッド型 | 階層的な組織構造で、上層部が意思決定を行い、指示が下へ伝達される。大企業や官公庁などで一般的 |
| フラット型 | 管理層を減らし、現場の自主性を重視する組織構造。意思決定が速く、新しく事業を立ち上げた企業やIT企業でよく採用される。 |
| マトリックス型 | 一人の社員が複数の部門やプロジェクトに属し、横断的に業務を進める組織構造。グローバル企業や研究開発部門で採用されることが多い。 |
4.評価制度と人材育成を強化する
- 社員が納得できる評価制度を整え、モチベーションを高める。
- 育成プログラムを導入し、リーダー候補を育てる。
5.継続的に改善する
定期的に組織運営を見直し、改善策を講じる。
企業が持続的に成長し、変化の激しい市場環境の中で競争力を維持するためには、適切な組織マネジメントの実践が欠かせません。組織マネジメントを強化することで、企業の戦略実行力が高まり、イノベーションが促進され、社員のエンゲージメントや企業文化の定着にもつながります。また、社会的責任を果たしながらブランド価値を向上させることも可能になります。
適切な組織マネジメントを導入・改善するには、現状の課題を把握し、ビジョンや目標を明確にしながら、組織構造の最適化や人材育成、評価制度の整備を進めることが重要です。これらを継続的に見直し、改善していくことで、変化に強く、成長し続ける組織を実現することができます。
解決できる課題

多くの企業では、組織の管理体制や業務の流れに課題を抱えており、それが業績や社員のモチベーション低下につながることもあります。
ここでは、組織運営を適切に行うことで解決できる課題を具体的に解説し、経営者や人事担当者がどのように改善に取り組めるのかをご紹介します。
1.組織運営が解決できる主要な課題
1.特定の人に依存した業務と情報共有の問題
- 特定の社員にしか分からない業務が多く、担当者が不在になると業務が停滞する。
- ノウハウが共有されておらず、新人や異動者がスムーズに業務を引き継げない。
- 必要な情報が適切に共有されず、組織全体の意思決定が遅れる。
解決策
- 業務の標準化を進め、マニュアル化や知識やノウハウを共有する仕組みを整備する。
- 業務の進捗を可視化するツールやシステムを活用し、情報共有の仕組みを強化する。
- 定期的なミーティングや社内SNSを活用し、チーム全体で知識を共有する文化を育てる。
2.コミュニケーション不足による組織の停滞
- 経営層と現場の間で情報がうまく伝わらず、組織の方向性が統一されない。
- 部署間の連携が悪く、業務の進め方がバラバラになり、ムダが生じる。
- 上司と部下の間でフィードバックが不足し、社員が適切な指示を受けられない。
解決策
- 定期的な経営層と現場の対話の場(全社ミーティング、1on1面談など)を設ける。
- 部署間の連携強化のために、横断的なプロジェクトチームを作る。
- オープンな社内コミュニケーションツール(チャットツールやグループウェア)や情報共有システムを導入することで、組織全体の意思疎通をスムーズにする。
3.人材の定着率の低下
- 評価制度が不明確で、社員が「何を頑張れば評価されるのか」分からず、不満が蓄積する。
- キャリアの道筋が見えず、優秀な人材が他社へ流出する。
- 社員のモチベーションが低く、成長意欲が減退する。
解決策
- 評価制度の透明化を進め、成果と成長が正当に評価される仕組みを導入する。
- キャリアの道筋の明確化により、社員が将来の成長イメージを持てるようにする。
- 社内研修やスキルアップ制度を充実させ、社員の成長を支援する。
4.意思決定の遅れと市場変化への対応力の欠如
- 経営陣の意思決定が遅く、競争環境の変化に適応できない。
- 現場の意見が経営層に届かず、柔軟な戦略変更ができない。
- データ活用が不十分で、感覚的な判断が多くなる。
解決策
- 迅速な意思決定を行うために管理層を減らし、現場の裁量を大きくした組織構造を採用する。
- 定期的な経営戦略を見直す会議を実施し、変化に応じた軌道修正を行う。
- データを活用した経営を導入し、売上データや顧客の声を活用して戦略を立てる。BI(ビジネスインテリジェンス)システムを活用することで、リアルタイムでデータを分析し、迅速な意思決定を可能にする。
組織運営を適切に行うことで、企業はこのような課題を解決できます。企業がこれらの課題を解決し、より強い組織を築くためには、計画的な組織マネジメントの実践が欠かせません。
必要なスキル

組織を円滑に運営し、成長を促進するためには、単なる管理業務の遂行だけでなく、戦略的なマネジメントスキルが求められます。経営者や人事担当者は、組織の方向性を定め、チームをリードし、環境の変化に適応する能力を備える必要があります。
本コラムでは、組織マネジメントを成功させるために必要なスキルを、以下の6つの視点から解説します。
1.戦略的思考(組織の方向性を見極める)
組織を適切に運営するためには、長期的な視点で戦略を考え、環境の変化に応じて柔軟に軌道修正を行うことが求められます。
戦略的思考が求められる場面
- 企業の目標を設定し、それを達成するための具体的な行動を決める。
- 組織の強みや課題を把握し、最適な人材配置や業務手順を構築する。
- 業界の動向や競合の状況を把握し、自社にとって有利な戦略を策定する。
2.コミュニケーション力(組織をスムーズに動かす)
組織運営において、経営者・管理職と現場社員の間で円滑なコミュニケーションを取ることは非常に重要です。組織のビジョンや目標が適切に伝わらなければ、社員のモチベーションが低下し、生産性も落ちてしまいます。
コミュニケーション力が求められる場面
- 経営方針や目標を明確に伝え、チームの方向性を統一する。
- 部署間の連携を強化し、スムーズな業務進行を促す。
- フィードバックを適切に行い、社員の成長をサポートする。
3.リーダーシップ(チームを牽引し、成果を出す)
組織を運営する上で、単に業務を管理するだけでなく、社員を導き、チームとしての力を最大限に発揮させるリーダーシップが求められます。
リーダーシップが求められる場面
- チームが同じ方向を向くように、ビジョンを示し、モチベーションを高める。
- 社員が主体的に動ける環境を整え、能力を引き出す。
- チームの目標を明確にし、達成に向けて組織を牽引する。
4.問題解決力(課題を特定し、適切な対策を打つ)
組織運営では、日々さまざまな課題が発生します。問題を放置せず、原因を分析し、迅速に解決策を打ち出すスキルが必要です。
問題解決力が求められる場面
- 業務の効率が悪い原因を特定し、改善策を実行する。
- チーム内のトラブルや対立を調整し、円滑な関係を築く。
- 市場の変化に対応し、新しい戦略を考える。
5.意思決定力(迅速かつ適切な判断を下す)
組織の成長には、スピーディーで正確な意思決定が大切です。特に、競争が激しい業界では、判断の遅れが企業の競争力を低下させる要因になります。
意思決定力が求められる場面
- 組織の戦略方針を決定し、迅速に実行する。
- 緊急事態において、最適な解決策を選ぶ。
- 部下やチームの意見を考慮しながら、リーダーとして方向性を決める。
6.育成・評価スキル(社員の成長を支援し、組織全体を強くする)
組織運営では、単に業務を回すだけでなく、社員の成長を促し、適切に評価する仕組みを整えることが不可欠です。
育成・評価スキルが求められる場面
- 社員の強みや課題を把握し、適切な育成計画を作成する。
- 公平で納得感のある評価制度を整備し、社員のモチベーションを維持する。
- 部下のキャリア形成を支援し、組織の成長につなげる。
組織マネジメントに必要なスキルは多岐にわたりますが、戦略的思考、コミュニケーション力、リーダーシップ、問題解決力、意思決定力、育成・評価スキルの6つは特に重要です。これらのスキルを磨くことで、組織全体の生産性が向上し、競争力のある企業へと成長していきます。
役に立つフレームワーク

組織運営において、企業の方向性を定め、戦略を遂行し、チームを効果的に動かすためには、適切なフレームワークを活用することが重要です。本記事では、以下の5つのフレームワークに焦点を当てて解説します。
1.ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)—企業の方向性を明確にする
ミッション(Mission)、ビジョン(Vision)、バリュー(Value)は、企業の理念や価値観を定め、組織全体が一貫した方向性で行動するためのフレームワークです。
| ミッション(使命) | 企業が社会に対して果たすべき役割「私たちは何をする組織なのか?」 |
| ビジョン(理想) | 企業が目指す将来の姿「私たちはどこへ向かっているのか?」 |
| バリュー(価値観) | 社員が意思決定する際に基準とする行動指針「私たちはどのように行動すべきか?」 |
活用方法
- 経営方針や組織文化を統一するための指針として活用する。
- 新入社員の教育や組織文化の浸透に役立てる。
- 従業員が意思決定を行う際の基準とする。
2. OKR(Objectives and Key Results)—目標管理を強化する
OKR(目標と主要な成果)は、組織やチームが目指す目標(Objective)と、それを達成するための主要な成果(Key Results)を設定し、成果を可視化するためのフレームワークです。
| Objective(目標) | 何を達成したいのか、数値ではなく、ビジョンや方向性を示すもの(定性的な目標) |
| Key Results(主要な成果) | 目標を達成するために必要な数値的な指標(定量的な測定基準) |
活用方法
- 全社・チーム・個人の目標を統一し、成果を最大化する。
- 短期間で目標の進捗を確認し、必要に応じて方向修正を行う。
- 従業員のエンゲージメントを向上させ、主体的な行動を促す。
3. マッキンゼーの7S—組織のバランスを整える
マッキンゼーの7Sは、企業の組織運営に影響を与える7つの要素を整理し、バランスを取るためのフレームワークです。
| Strategy(戦略) | 企業の方向性や競争戦略 |
| Structure(組織構造) | 組織の形態や階層構造 |
| Systems(制度) | 業務の流れや評価制度 |
| Skills(スキル) | 社員が持つ専門性や能力 |
| Staff(人材) | 社員の配置や育成 |
| Style(企業文化) | 組織の価値観や行動スタイル |
| Shared Values(共有価値観) | 企業の理念やビジョン |
活用方法
- 組織改革を行う際に、7つの要素がバランスよく機能しているかをチェックする。
- 新しい経営戦略を導入する際に、組織が対応できる状態かを診断する。
- 企業文化や価値観を明確にし、一貫した組織運営を行う。
4.タックマンモデル—チームの成長段階を理解する
タックマンモデルは、チームの成長過程を4つのステージに分け、それぞれの段階で適切なリーダーシップやサポートを提供するためのフレームワークです。
| 1.形成期(Forming) | メンバーが集まり、チームとしての役割を模索する時期。 |
| 2.混乱期(Storming) | 意見の対立や役割の調整が発生する時期。 |
| 3.統一期(Norming) | チームの役割やルールが確立し、協力関係が築かれる時期。 |
| 4.遂行期(Performing) | チームが安定し、高いパフォーマンスを発揮する時期。 |
活用方法
- チームが現在どの段階にあるのかを把握し、適切なサポートを行う。
- リーダーがチームの成長に応じたリーダーシップを発揮する。
- 新しいプロジェクトや組織変更の際に、チームの成長過程をスムーズに進める。
5.フューチャーサーチ—全員参加型の戦略策定
フューチャーサーチは、組織に関わるすべての関係者(社員、顧客、取引先、投資家、地域住民などのステークホルダー)全員が参加し、未来のビジョンを共有しながら戦略を策定する手法です。
活用方法
- 社員、顧客、パートナーなど関係者全員が参加し、組織の方向性を決定する。
- 短期間で全体の合意形成を行い、実行可能な戦略を策定する。
- 組織変革や新規事業の立ち上げの際に活用する。
組織運営には、さまざまなフレームワークが存在します。これらを活用することで、組織の目標設定、意思決定、チームマネジメントを効果的に進めることができます。
組織マネジメントに関する理論
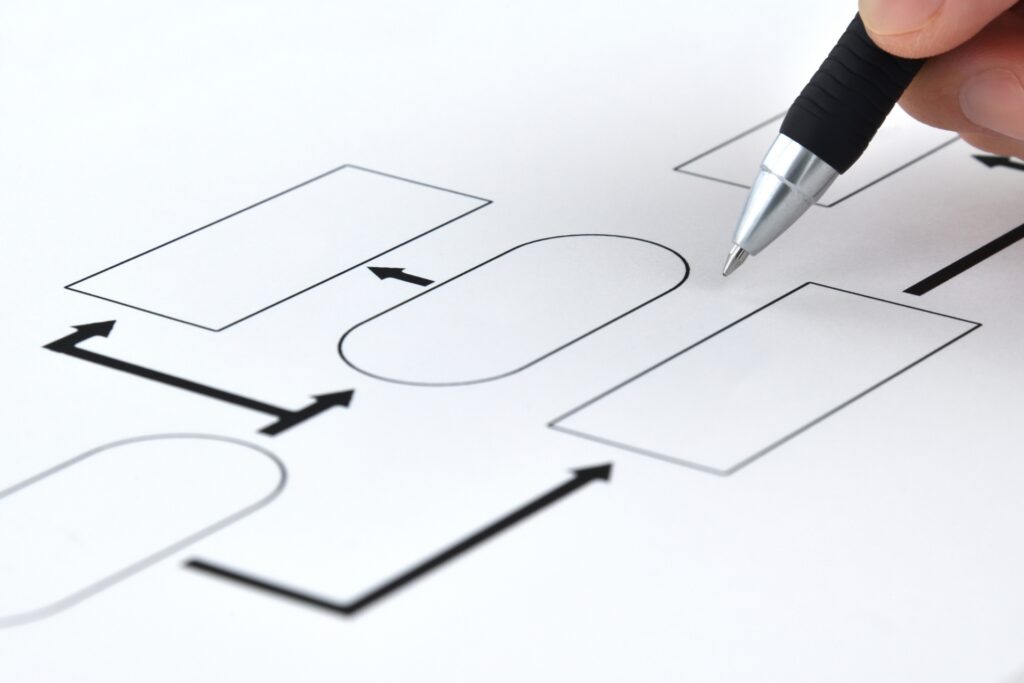
組織運営を成功させるためには、単なる経験則や勘に頼るのではなく、経営学の理論を活用することで、より戦略的な意思決定が可能になります。
本記事では、以下の5人の理論に注目して、組織マネジメントに役立つ考え方を解説します。
1.ドラッカーのマネジメント理論—「成果を生む組織の条件」
ピーター・ドラッカーは「マネジメントの父」と呼ばれ、現代の経営理論の礎を築いた人物です。彼の理論は、組織の成果を最大化するために、マネジメントが果たすべき役割を示しています。
主要な考え方
「マネジメントの3つの役割」
- 組織の目的を定義し、成果を上げること
- 人材をマネジメントし、成長させること
- 組織の社会的責任を果たすこと
「知識労働者の時代」
- 近代の企業は、工場労働ではなく「知識」を活用する組織へと変化。
- 知識労働者が成果を出せる環境を整えることが重要。
実践方法
- 企業の目的を明確にし、成果に直結する業務に人材・資金・時間などの経営資源(リソース)を集中させる。
- 従業員が自律的に動ける環境を整え、能力を最大限に引き出す。
- 組織の価値観やビジョンを社内に浸透させ、社員のモチベーションを高める。
2.チャンドラーの「組織は戦略に従う」理論—組織構造と戦略の関係
アルフレッド・チャンドラーは、「組織の構造は、企業の戦略によって決まる」という考えを提唱しました。企業が成長するにつれ、適切な組織体制が必要になることを示しています。
主要な考え方
企業の成長段階ごとに適した組織構造がある
小規模企業は単純な構造で運営可能だが、事業が拡大すると部門ごとの専門化が必要になる。
戦略の変更に伴い、組織構造も見直す必要がある
新規事業の拡大、グローバル化、DX推進(デジタル技術を活用した業務効率化と新たな価値の創出)などの戦略変更に応じて、組織体制を変えるべき。
実践方法
- 企業戦略を明確にし、それに適した組織構造を設計する。
- 事業規模の拡大に応じて、組織体制を再編成する。
- 戦略の変更が組織の柔軟性を損なわないよう、定期的に見直しを行う。
3.バーナードの組織論—「組織は人の協働によって成り立つ」
チェスター・バーナードは、組織の本質は「協働」にあると考え、組織が成立するための条件を提唱しました。
主要な考え方
組織が成立する3つの要件
1.共通の目的(組織の目標)
2.貢献意欲(社員のモチベーション)
3.コミュニケーション(情報共有の仕組み)
組織の存続には「誘因均衡」が重要
社員が組織に貢献する「インセンティブ(給料や評価)」と、企業が提供できる価値がバランスしていることが必要。
実践方法
- 企業のビジョンを明確にし、社員と共有する。
- フィードバックや評価制度を充実させ、社員の貢献意欲を高める。
- 部門間の連携を強化し、情報共有をスムーズにする。
4.アンゾフの成長マトリクス—企業の成長戦略
イゴール・アンゾフは、企業の成長戦略を「市場」と「製品」の軸で考える「アンゾフの成長マトリクス」を提唱しました。
主要な考え方
4つの成長戦略
| 市場浸透戦略(既存市場 × 既存製品) | シェア拡大、プロモーション強化 |
| 市場開拓戦略(新市場 × 既存製品) | 海外進出、新規顧客の獲得 |
| 製品開発戦略(既存市場 × 新製品) | 商品ラインナップの拡充 |
| 多角化戦略(新市場 × 新製品) | 新規事業の立ち上げ |
実践方法
- 自社がどの成長戦略を採用すべきかを分析する。
- 競争環境を考慮し、適切な市場拡大戦略を選択する。
- 既存顧客の満足度向上と新市場の開拓を並行して進める。
5.ヘンリー・ミンツバーグの「マネジメントの10の役割」—経営者・管理職が果たすべき役割とは?
ヘンリー・ミンツバーグは、マネジメントの実務を分析し、経営者や管理職が担うべき役割を10個に分類しました。彼の理論は、経営者が実際にどのような業務を遂行し、組織を動かすべきかを理解するのに役立ちます。
主要な考え方
ミンツバーグの「マネジメントの10の役割」
彼はマネジメントの役割を、以下の3つのカテゴリに分けています。
1.対人関係の役割(Interpersonal Roles)
| 1.象徴(Figurehead) | 企業の代表としての役割を果たし、社内外のイベントに参加する。 |
| 2.リーダー(Leader) | 社員を指導し、組織の目標達成に導く。 |
| 3.リエゾン(Liaison) | 社内外の関係者とネットワークを築き、情報を得る。 |
2.情報伝達の役割(Informational Roles)
| モニター(Monitor) | 社内外の情報を収集し、組織の意思決定に活かす。 |
| 情報伝達者(Disseminator) | 収集した情報を適切な関係者に共有する。 |
| スポークスパーソン(Spokesperson) | 企業の代表として情報を外部に発信する。 |
3.意思決定の役割(Decisional Roles)
| 起業家(Entrepreneur) | 新しいアイデアを推進し、組織の成長を促す。 |
| トラブルシューター(Disturbance Handler) | 予期せぬ問題に対処し、組織の安定を保つ。 |
| 資源配分者(Resource Allocator) | 予算や人材などのリソースを適切に分配する。 |
| 交渉者(Negotiator) | 組織を代表して、契約や取引の交渉を行う。 |
活用方法
- 経営者や管理職が、自分の役割を明確に理解し、バランスよくマネジメントを行う。
- どの役割に時間を割くべきかを分析し、優先順位をつける。
- 管理職研修に活用し、リーダーの育成に役立てる。
これらの理論を理解し、組織運営に活用することで、戦略的な意思決定、リーダーシップの発揮、組織の持続的な成長が可能になります。経営者や人事担当者は、自社の状況に合わせて、これらの理論を実践に活かしていくことが重要です。
組織マネジメントの成功事例

ここでは、世界的に成功を収めた企業の組織マネジメントの実践事例を紹介します。各企業が直面した課題と、それに対する具体的な取り組み、成果を詳しく解説し、企業経営や人事戦略に活かせるポイントを探っていきます。
1.ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の活用事例:スターバックス
背景と課題
- スターバックスは、急速な店舗拡大により、店舗ごとのサービス品質や企業文化の統一が難しくなっていた。
- 「企業の方向性(MVV)が現場に浸透しない」という課題が発生。
取り組み
MVVを強化
企業理念「人々の心を豊かで活力あるものにする」を全店舗に浸透させるため、研修制度を強化。
バリスタ認定制度の導入
全社員が同じ理念のもとでサービスを提供できるよう、専門性を高める教育を実施。
成果
- サービス品質の統一が実現し、顧客満足度の向上に貢献。
- 従業員エンゲージメントが向上し、離職率が低下。
ポイント
組織の方向性を明確にするMVVの活用が、従業員の行動や組織文化の強化に直結。
2.OKRの導入による成功事例:Google
背景と課題
Googleは急成長する中で、社員が何を優先すべきかが不明確になり、組織の一体感が希薄になっていた。
取り組み
OKR(Objectives and Key Results)の導入
企業、チーム、個人の目標を明確にし、進捗を可視化。
四半期ごとに目標を設定し、定期的に進捗を振り返りながら見直しを行う。
成果
- 社員が企業戦略と自分の業務の関係を理解しやすくなり、目標達成率が向上。
- 透明性の高い評価制度により、社員のモチベーションが向上。
ポイント
目標管理のフレームワーク(OKR)を活用することで、組織の一体感と成果創出を両立。
3.マッキンゼーの7Sを活用した組織改革:P&G
背景と課題
P&Gは、グローバル展開に伴い、組織のバランスが崩れ、意思決定のスピードが遅れる問題を抱えていた。
取り組み
7Sフレームワークを活用し、組織の整合性を強化。
| Strategy(戦略) | 各国市場ごとに最適な戦略を策定。 |
| Structure(組織構造) | グローバル本社と地域拠点の役割を明確化。 |
| Systems(制度) | 社内の情報共有ツールを導入。 |
| Skills(スキル) | マーケティングとデータ分析を強化。 |
| Staff(人材) | 適材適所の人材配置を徹底。 |
| Style(企業文化) | リーダーシップ研修を導入。 |
| Shared Values(共有価値観) | 企業理念を全社員に浸透。 |
成果
- 組織全体の連携が強化され、意思決定のスピードが向上。
- 世界中のマーケットで競争力を維持し、売上が拡大。
ポイント
組織のあらゆる要素をバランスよく調整することが、企業の成長に不可欠。
4.タックマンモデルの活用事例:NASAのアポロ計画
背景と課題
アポロ計画では、異なる専門分野のエンジニアや科学者が集まり、チームとしての機能を早期に確立する必要があった。
取り組み
タックマンモデル(チームの成長段階)を活用
| 形成期(Forming) | 各分野の専門家が集まり、役割分担を決定。 |
| 混乱期(Storming) | 意見の対立が発生し、調整を実施。 |
| 統一期(Norming) | 共通目標を定め、チームワークを強化。 |
| 遂行期(Performing) | 計画の実行と改善を繰り返す。 |
成果
多様な専門家が効果的に連携し、アポロ11号の月面着陸を成功させた。
ポイント
チームの成長の流れを理解することで、効率的な組織運営が可能になる。
5.フューチャーサーチの成功事例:BMWの長期戦略策定
背景と課題
BMWは、未来のモビリティ市場に適応するため、全社的な長期戦略策定が必要だった。
ビリティとは、人や物の移動に関する技術やサービスの総称で、電気自動車や自動運転、シェアリングサービスなど、従来の自動車を超えた新たな移動手段を含む概念のことです。
取り組み
フューチャーサーチ(全員参加型の戦略策定)を実施
- 社員、取引先、顧客、政府関係者などを巻き込み、未来のビジョンを策定。
- 「持続可能なモビリティ」「電動化」「自動運転」などのテーマを議論。
成果
EV(電気自動車)や自動運転技術の開発に注力し、市場での競争力を確立。
ポイント
多様な関係者の意見を取り入れることで、組織の長期的な成長戦略を確立できる。
6.組織マネジメントに関する理論の実践
1.ドラッカーのマネジメント理論 – GE(ゼネラル・エレクトリック)
CEOジャック・ウェルチがドラッカーの「成果を生む組織の条件」に基づき、明確なビジョンと人材育成を強化。その結果、GEは世界的な大企業へ成長。
2.チャンドラーの「組織は戦略に従う」理論 – Amazon
Amazonは「カスタマー・セントリック戦略」に基づき、組織を柔軟に変化させることで、オンライン販売の市場をリードする企業へ。
カスタマー・セントリック戦略とは、顧客のニーズを最優先に考え、サービスや製品を設計・提供する経営方針のこと。Amazonでは、個別の購買データを活用したレコメンド機能や、迅速な配送サービスを通じて顧客満足度を高めている。
3.バーナードの組織論 – 日本航空(JAL)
経営破綻後、組織の共通目的を再定義し、全社員の貢献意欲を高めることで、業績回復に成功。
4.アンゾフの成長マトリクス – Apple
市場開拓戦略(iPhoneの海外展開)や製品開発戦略(iPad、Apple Watch)を活用し、世界的な成長を遂げた。
5.ヘンリー・ミンツバーグの「マネジメントの10の役割」 – トヨタ
「リーダー」「情報伝達者」「意思決定者」などの役割を強化し、トヨタ生産方式(TPS)を確立。
成功事例から学べることは、理論やフレームワークを活用することで、組織の成長が加速するという点です。
経営者や人事担当者は、自社の課題を分析し、最適な手法を取り入れることで、持続的な競争力を獲得できます。
まとめ
本コラムでは、「組織運営」とは何かを明確にし、その重要性、解決できる課題、必要なスキル、活用できるフレームワーク、関連する理論、そして具体的な成功事例までを幅広く解説してきました。
組織運営は、単に業務を管理することではなく、企業の目的を達成するために、人材・組織構造・仕組み・文化を最適な形にしていく取り組みです。企業が持続的に成長し、変化する市場環境に対応していくためには、適切な組織マネジメントが不可欠です。
また、成功する組織運営には、「経営者のビジョン」「社員のエンゲージメント」「柔軟な組織構造」「明確な評価・育成制度」「データに基づく意思決定」といった複数の要素が必要です。
重要なのは、組織運営には「これが正解」という唯一の答えは存在しないということです。企業ごとに課題や目的は異なり、それぞれの状況に応じた取り組みが求められます。そのため、本コラムで紹介したフレームワークや理論を参考にしながら、自社の現状に適した施策を見極め、試行錯誤を重ねながら改善を続けることが大切です。
組織運営は一朝一夕に完成するものではなく、常に進化し続けるべきものです。変化の激しい現代社会においては、組織もまた変化に適応しながら成長する必要があります。これから組織運営を見直そうと考えている経営者や人事担当者の皆さまにとって、本コラムが少しでも参考となり、実践への第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

コメント