人事異動における「内示」は、社員の働き方や意欲に直結する極めて重要なプロセスです。本コラムでは、内示の基本的な定義から、辞令との明確な違い、内示の種類、伝える最適なタイミング、具体的な伝え方、伝える際に注意すべき実務的ポイント、さらに内示後のアフターケアまでを網羅的に解説しています。人事異動は単なる配置換えではなく、社員のキャリア観や業務の継続性、職場全体の信頼関係に深く関わるテーマです。人事担当者やマネージャーが陥りがちな失敗も交えながら、実践的に学べる内容となっています。
< このコラムでわかる3つのポイント >
1.人事異動の内示を、現場対応を踏まえて適切に実施するための方法
2.内示のタイミングや伝え方において注意すべき実務上の留意点
3.社員の不安を軽減し、異動後のパフォーマンスを高めるためのアフターケアの実践法
Contents
人事異動の内示とは
人事異動の「内示」とは、企業が行う人事異動の意思決定を、正式な辞令を出す前に対象社員へ非公式に伝える行為です。これはあくまで“非公式”ではあるものの、社員にとっては今後のキャリアや業務の大きな節目となるため、その重要性は極めて高いといえます。例えば、A部署からB部署へ異動する場合、内示によって本人の了承を得てから辞令を出すという流れが一般的です。
そもそも、なぜ企業は「内示」というプロセスを設けるのでしょうか?主な理由は以下の3点です。
- 社員の心理的準備を促すため
人事異動は業務内容、勤務地、人間関係などが大きく変わる可能性があるため、いきなり辞令を発令してしまうと、社員が戸惑いや反発を覚えるケースも少なくありません。内示を先に行うことで、本人がその変化に備える“心の準備”を整える時間を提供できます。 - 業務引き継ぎを円滑に進めるため
特に現場業務を多く抱える部署においては、異動前後の業務引き継ぎが重要です。内示の段階で対象社員に異動先や異動理由を説明し、引き継ぎに向けた計画を立てることで、業務の混乱を最小限に抑えられます。 - 異動を巡るトラブルを防ぐため
人事異動の内容が本人の希望と大きく異なる場合、感情的な拒否や社内不和につながる恐れもあります。内示を通じて、対話の機会を設けることにより、誤解や不満が深刻化する前に対応できる可能性が高まります。
企業によっては「内示は形式的なものであり、内容は既に確定している」と位置付けている場合もありますが、近年では人材の流動性が高まり、従業員のエンゲージメント向上が人事の課題となっている背景から、「内示=対話の場」として捉える企業が増えてきています。
例えば、あるIT企業では内示を「通知」ではなく「提案」に近いものとして扱い、本人の意思を一定程度汲み取ったうえで最終的な辞令を決定するというプロセスを導入しています。このような運用を行うことで、社員の納得感を高め、自発的な行動を促すことができるのです。
また、内示の実施主体にも注目すべきです。人事部が単独で内示を行う企業もあれば、現場の上司が面談形式で伝える企業もあります。どちらにしても大切なのは、「形式」ではなく、「相手の状況や背景に応じた丁寧な伝え方」を意識することです。
さらに、内示の位置付けは法的にも重要な意味を持ちます。労働契約法上、内示はあくまで「辞令の前段階」に過ぎず、法的効力は持ちません。しかしながら、内示の内容が記録に残り、後に労使トラブルの証拠となる可能性があるため、発言や文書の扱いには注意が必要です。
最後に、人事異動の内示は「制度」ではなく「運用」の領域に位置づけられるため、属人的な対応に陥りやすいという特徴があります。企業が一貫した内示方針を持つことで、社内の公平性や信頼性を高めるとともに、異動対象者の不安軽減にもつながります。
人事異動の内示と辞令の違い

人事異動に関する混乱や誤解の多くは、「内示」と「辞令」の違いが曖昧なまま伝達されてしまうことに起因しています。特に社員本人にとっては、どちらも“異動を知らされる出来事”であるため、その意味の違いを意識せずに受け取ってしまうケースも珍しくありません。しかし、企業の人事担当者としては、この2つの性質を明確に区別し、それぞれの役割に応じた適切な運用を行うことが不可欠です。
まず、「内示」とは非公式な通知です。これは企業が人事異動の意思決定を行った後、正式な発令(辞令)に先立ち、対象社員に対して予定されている異動内容を知らせるものです。法的な拘束力はなく、あくまで事前連絡の性格を持ちます。目的は、社員の心理的準備を促すこと、引き継ぎなどの業務調整を円滑に進めること、必要に応じて本人の意見や懸念をヒアリングすることなどです。企業によっては、内示の段階で異動内容の微調整が可能な場合もあります。
一方で、「辞令」とは公式な人事命令です。辞令は社内での正式な手続きに基づき発令され、法的な効力を持つものと見なされます。社員はこれに基づいて業務や勤務地の変更に応じる義務を負います。また、辞令発令日から新たな部署や役職に就くことが原則であり、企業としても公的な記録や就業規則に則って管理されます。
このように、「内示」は“対話と調整”の機会であり、「辞令」は“決定と執行”のプロセスと位置付けることができます。したがって、両者の間には明確な区分と目的の違いが存在し、その運用を誤ると、以下のような問題が生じるリスクがあります。
- 内示を辞令のように受け止めた社員が、異動を拒否できないと誤解してしまう。
- 辞令を出す前に十分な対話を行わず、社員の不信感を招く。
- 内示と辞令の内容に差異がある場合、トラブルや訴訟に発展する可能性がある。
そのため、企業の人事部門としては、社員に対して内示と辞令の違いを明確に説明する責任があります。例えば、内示時には「これは正式な決定(辞令)ではなく、事前に内容を共有し、必要な準備や意見交換を行うためのものです」といった説明を加えることで、誤解のリスクを軽減できます。
また、実務上の観点でも、内示と辞令の運用は異なります。内示は通常、直属の上司や人事担当者が面談形式で伝え、口頭説明が主となる一方、辞令は文書で発行され、就業規則や人事記録として正式に保管されます。これにより、辞令は労務管理上の証拠にもなりうるため、その発令手続きには慎重な配慮が求められます。
さらに、内示と辞令のタイミングの間には、一定の準備期間が設けられるのが一般的です。多くの企業では、内示から辞令発令までに1〜3週間程度の余裕を持たせ、引き継ぎ業務や関係部署との調整を進める時間としています。こうしたプロセスが適切に設けられているかどうかが、社員の納得感や異動後のパフォーマンスにも直結します。
加えて、近年では「内示後の辞退」や「内示段階での調整」を前提とした柔軟な人事運用を行う企業も増えています。特に専門性の高い職種や、キャリア志向が強い社員に対しては、一方的な内示ではなく、対話的プロセスとして位置づけることが好まれます。このような姿勢は、人的資本経営の視点からも重要な取り組みです。
総じて、人事異動の内示と辞令は似て非なるものであり、それぞれの意味と役割を正確に理解したうえで、企業内で一貫した運用基準を設けることが、組織全体の信頼性と透明性を高める鍵となります。
人事異動の内示の種類
人事異動の「内示」とひとくちに言っても、その運用方法は企業によって大きく異なります。内示の種類を理解しておくことは、異動をスムーズに進めるための前提となり、対象社員への配慮にもつながります。ここでは、企業の実務において実際に用いられている内示の種類を分類し、それぞれの特徴と留意点を整理します。
まず、内示の分類は大きく次のように整理できます。
| 種類 | 特徴 | 使用される場面 |
|---|---|---|
| 個別内示 | 本人と1対1で面談形式で伝える。内容に応じて対話が可能 | 中間管理職以上の異動など重要性が高い場合 |
| 一斉内示 | 対象者複数に対して同時に通知される | 新卒配属、チームの組織再編時など |
| 文書による内示 | 書面やメールで通知。記録が残る一方、対話機会が限定される | 本社⇔支店間異動や大量異動時など |
| 非公式な事前打診 | 人事や上司が非公式に本人へ打診。柔軟な反応が可能 | 人材育成や適性配置の検討段階で活用 |
このように、内示には形式やタイミングに応じて複数の手法が存在します。例えば、個別面談形式の内示は、社員一人ひとりの反応を確認しながら伝えられるため、納得感を得やすいというメリットがあります。一方で、一斉内示はスピーディーに情報を伝達できるものの、個々の事情に配慮しにくい点が課題です。
また、特に注意すべきなのが「文書による内示」です。これはメールや通知書で形式的に伝える方法であり、記録が残るというメリットがある反面、社員の反応や気持ちを確認しづらく、不安や誤解を招くリスクがあります。大量異動が発生するタイミングなどでは有効ですが、内示後の個別フォローが不可欠です。
一方、まだ確定前の段階で行われる「非公式な事前打診」は、社員の希望や状況を踏まえて柔軟に対応できるという点で、人的資本経営の観点から注目されています。特にキャリア志向が強い若手社員や専門性の高い職種に対しては、このような事前調整が有効です。
さらに、これらの内示の種類は「誰が伝えるか」によっても意味合いが変わってきます。
| 実施主体 | 主な特徴 | 留意点 |
|---|---|---|
| 人事部門 | 制度運用としての一貫性がある。企業方針に基づく | 社員個人の状況を十分に把握していない場合も |
| 直属の上司 | 業務状況や本人の能力を把握したうえでの説明が可能 | 感情的な要素が介在しやすい |
| 経営層(役員など) | 組織戦略を直接伝えられる | 社員に威圧感を与えやすい |
| 上司+人事の同席 | フォローと制度説明の両立が可能 | 調整に手間がかかる |
このように、内示の「方法」と「誰が伝えるか」を適切に組み合わせることが、納得感とスムーズな異動を実現するカギになります。例えば、重要ポジションへの異動には、直属の上司と人事部が同席しての面談形式が好まれます。一方、組織再編に伴う部署単位の異動などでは、上層部が主導する一斉内示が選ばれるケースもあります。
加えて、昨今ではオンラインツールを活用した内示(例:Zoomによる面談、Slackによるフォローアップなど)も増えており、場所や時間の制約を越えた柔軟な運用が可能となっています。これらを有効に活用することで、遠隔地勤務やリモートワーク下でも社員への配慮を欠かさない内示が可能です。
まとめると、企業が実施する内示には複数の「型」が存在し、それぞれにメリットとデメリットがあります。重要なのは、「自社の目的」「社員の特性」「異動の文脈」に応じて、最適な方法を選択し、実行することです。形式的に内示を済ませるのではなく、社員との信頼関係を深める機会と捉えることが、これからの人事に求められる姿勢といえるでしょう。
人事異動の内示を知らせるタイミング
人事異動において「内示をいつ伝えるか」は、実務上きわめて重要なポイントです。タイミング次第で、社員のモチベーションや業務への影響、職場全体の雰囲気が大きく変わるため、人事部門としては慎重に検討すべきです。早すぎても混乱を招き、遅すぎても準備が間に合わない。適切な内示タイミングを見極めることが、円滑な異動運用のカギとなります。
まず、内示を伝えるタイミングにはいくつかのパターンがあります。
| タイミング | 特徴・背景 | 主な課題 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上前 | 引き継ぎや異動先準備に十分な時間が取れる | 情報が広がりやすく、混乱の恐れあり |
| 2〜3週間前 | 業務調整と心理的準備のバランスが取れる標準的な時期 | 社員が異動先の不明点に不安を感じやすい |
| 直前(1週間以内) | 情報漏洩リスクは少ないが、準備不足による混乱の恐れあり | 精神的な抵抗や動揺が大きくなる可能性 |
一般的に多くの企業では、異動の2〜3週間前に内示を出すことが推奨されています。この時期であれば、業務の引き継ぎや関係部署との調整にも十分な余裕があり、かつ情報漏洩のリスクもある程度抑えられます。また、社員本人の心理的な準備期間としても適切とされます。
しかし、タイミングを誤ると以下のような問題が起こり得ます。
| 早すぎる内示のリスク | 内示が早すぎると、社員が今の業務に集中できなくなったり、周囲に情報が拡散して職場内に不要な動揺が広がったりする可能性があります。とくにマネジメント層やキーパーソンの異動においては、周囲への影響を慎重に考慮する必要があります。 |
| 遅すぎる内示のリスク | 一方、内示が直前すぎると、引き継ぎや異動先での準備が間に合わず、業務に支障をきたす恐れがあります。また、社員が突然の異動にショックを受けたり、転職を検討するようなケースも散見されます。これらは企業にとっても人的コストの増加につながるため、避けたいリスクです。 |
こうした課題を回避するには、異動の性質や対象社員の状況に応じて柔軟にタイミングを調整することが求められます。例えば、本人のキャリア志向が強く異動を前向きに捉えている社員であれば、早めに内示を出しても問題は少なく、むしろ歓迎される場合もあります。一方で、家庭の事情や職場内での人間関係に配慮が必要なケースでは、伝えるタイミングと手段に特に慎重な配慮が必要です。
また、組織改編や新体制の発足など、大規模な異動を伴う場合には、「組織発表」と「個別内示」の順番と間隔にも注意が必要です。組織図の変更などが社内に公開されてから個別内示を行うと、社員が混乱する場合もあるため、できる限り事前に本人に内示を済ませておくのが理想です。
加えて、以下のような「業務的な観点」からタイミングを逆算する考え方も有効です。
- 現業務の引き継ぎに必要な日数はどれくらいか。
- 異動先での準備や教育のスケジュールはどうなっているか。
- 社内全体での人事発表のタイミング(例:四半期末など)との整合性は取れているか。
人事異動が3月や9月など、期末・期初のタイミングで行われる企業では、内示もそれに合わせて出す必要があります。とくに繁忙期と重なる場合は、引き継ぎ負荷が高まり、社員にとってもプレッシャーが大きくなるため、スケジュール調整が非常に重要です。
近年は、柔軟な働き方やキャリア形成支援の観点から、「社員との話し合いを経て内示タイミングを調整する」企業も増えています。例えば、ライフイベント(出産・介護など)に配慮した時期設定をするなど、個別対応の柔軟性が求められるようになっています。
結論として、「内示のタイミング」は一律に決められるものではなく、業務・社員・組織の状況を総合的に見ながら判断する必要があります。重要なのは、内示のタイミングを「業務連絡」ではなく「人と組織をつなぐ戦略的行為」と捉え、全体最適を意識することです。
人事異動の内示の伝え方の種類

内示は単なる通知行為ではなく、社員の受け止め方や今後のパフォーマンスに直結する「コミュニケーションの場」です。そのため、どのような方法で伝えるか、どんな言葉を選び、誰がどういう態度で臨むかが非常に重要となります。ここでは、実務上よく用いられる内示の伝え方を分類し、それぞれの特徴と活用シーン、注意点を整理します。
内示の伝え方には、主に以下のような形式が存在します。
- 対面による個別面談
最も一般的で推奨される形式です。会議室などプライバシーが保たれた場で、直属の上司や人事担当者が対象社員と1対1で面談を行い、内示内容を伝えます。この方法は相手の反応を直接確認でき、質問や懸念にもその場で対応可能です。信頼関係を築くうえでも非常に効果的です。 - Web会議によるオンライン面談
テレワークが浸透した現代では、ZoomやTeamsなどを活用したオンライン内示も増えています。遠隔地に勤務する社員や在宅勤務中の社員にとって有効な手段です。ただし、通信環境や表情の伝わりづらさなど、対面に比べて細やかな感情のやり取りが難しい場合があるため、表現にはより慎重さが求められます。 - 電話による通知
急ぎの連絡や、他の連絡手段が確保できない場合に使われる形式です。簡易的な方法ですが、誤解が生じやすく、社員側の反応を十分に確認できないデメリットがあります。電話による内示の後は、必ず文書やメールでフォローを行い、記録と再確認の機会を設けることが望まれます。 - メール・文書による通知
通達内容を明確に残すため、メールや通知書による伝達が選ばれることもあります。大量の異動が同時に行われる場合や、制度上の理由から記録を残す必要がある場合には有効です。しかし、感情面への配慮が難しく、一方的な印象を与えがちなため、併せてフォローアップの面談を行うことが推奨されます。
伝え方を選定する際には、以下の要素を考慮することが重要です。
- 異動の重要性やセンシティビティの度合い
例えば、昇進や大きな役割変更を伴う異動であれば、必ず対面もしくはオンラインで丁寧に伝えるべきです。一方、定期的な部署ローテーションであれば、文書と簡単な面談でも問題ないケースがあります。 - 社員の性格・年次・キャリア志向
若手社員や異動経験の少ない社員には、特に配慮が必要です。丁寧に説明し、不安点を聞き取る姿勢が信頼醸成につながります。 - 上司と部下の信頼関係の深さ
既に関係が築かれている場合は柔らかい言葉でも伝わりますが、信頼関係が希薄な場合は、制度的説明や第三者(人事担当)の同席が必要になることもあります。
どの伝え方を選ぶにしても、重要なのは「一方的な通知」で終わらせないことです。人事異動という重要な変化に対し、社員が不安や戸惑いを感じるのは当然のことです。そのため、伝達後のコミュニケーション(フォローアップ)を含めた設計が不可欠です。
また、伝える際の言葉選びも非常に重要です。例えば、「この異動は会社の事情だから」と一方的に伝える、「あなたの能力が評価されている」と過剰に期待を煽る、などの表現は逆効果になることもあります。
ベストなのは、「会社の方針」と「あなたの今後の成長」の両面から異動の意図を説明することです。加えて、異動先の業務内容や期待される役割についても具体的に伝えることで、社員は自らの立ち位置や今後のキャリアをイメージしやすくなります。
最後に、内示の伝え方を単なる「業務手続き」として捉えるのではなく、「関係構築の機会」として位置付けることが人事の本質です。伝え方の質が、社員の信頼や会社へのロイヤリティ、異動後の成果にまで影響を与えることを忘れてはなりません。人事担当者や上司の一言ひとことが、社員のモチベーションに大きく作用することを意識し、誠実で納得感のあるコミュニケーションを心がけることが、最終的な人事施策の成功につながるのです。
人事異動の内示を伝える際に気をつけること
人事異動の内示は、社員にとってキャリアや職場環境が変わる大きな転機です。伝え方次第で社員の受け止め方が変わり、異動後のパフォーマンスにも影響を及ぼすため、伝える際には細やかな配慮が求められます。以下では、実務上注意すべき6つのポイントに分けて解説します。
■ 一方的な通知で終わらせない
- 「会社が決めたことだから」と理由説明を省略しない
- 異動の背景や目的、異動先での期待役割を丁寧に伝える
- 感謝や評価の言葉を添えることで納得感を高める
■ 社員の反応を受け止める姿勢を持つ
- 異動に驚き、不満、不安を抱くのは自然なこと
- 否定せず傾聴し、必要に応じて再面談の場を設定
- 感情的な反応もまずは受け止める姿勢を示す
■ 伝える環境とタイミングに配慮する
- 静かな個室など、プライバシーが保たれる場所を選ぶ
- 朝一や退勤直前など、落ち着いて話せない時間帯は避ける
- 30分程度の面談時間を確保し、急ぎの伝達にならないようにする
■ 周囲への影響を最小限に抑える
- 他の社員に気づかれにくいスケジュールで面談を設定
- 複数名への内示は時間差をつけるなど工夫する
- 異動先の上司や関係者と事前に連携し、情報共有しておく
■ 内容と反応を記録しておく
- 内示日時・場所・伝達者・社員の反応を記録
- 後のトラブルやフォローアップに備える
- 必要に応じて、口頭でのやり取り後に文書で再確認
■ 言葉選びに注意する
避けるべき表現例:
- 「仕方ないけど異動してもらう」
- 「他に人がいないからお願いする」
望ましい表現例:
- 「これまでの経験と強みを活かせるポジション」
- 「キャリアの幅を広げるチャンスとして期待している」
内示は、社員の納得感と信頼を得る絶好の機会でもあります。業務として機械的に行うのではなく、「人事=人との関係を築く行為」であることを意識し、丁寧で誠実な姿勢で臨むことが、異動を成功させる第一歩となるのです。
人事異動の内示を伝えた後のアフターケア
人事異動の内示を適切なタイミング・方法で伝えたとしても、それで完了ではありません。むしろ重要なのはその“後”。社員の不安や疑問に対してフォローを怠ると、納得感が得られず、異動後のパフォーマンスや職場の関係性に悪影響を及ぼすリスクがあります。ここでは、内示後に人事や上司が行うべき「アフターケア」の具体的な取り組みを紹介します。
■ 内示後のリアクションを確認する
内示を受けた直後は、社員の頭の中が整理できていない状態であることがほとんどです。その場では特に問題なさそうに見えても、時間が経つと不安や疑問が湧いてくることがあります。継続的に接点を持つことで、社員が「ちゃんと見てもらえている」と実感でき、信頼感につながります。
- 数日以内に再度コンタクトを取り、率直な気持ちをヒアリングする
- 「聞きたいことがあればいつでも相談して」といった柔らかい声かけをする
- メールや社内チャットでの軽いフォローも効果的
■ 異動に伴う業務の不安を可視化・解消する
内示後、社員が最も不安を感じるのが「引き継ぎの進め方」と「異動先での適応」です。これらを本人任せにせず、業務計画を一緒に立てることが有効です。具体的なサポートは、異動の「不安」を「行動」に変えるきっかけになります。
- 現部署での引き継ぎタスクを一覧化する
- 異動先の上司と面談をセッティングし、業務内容を事前に説明してもらう
- 必要に応じて、現部署のチームメンバーにも状況を共有する
■ 異動先の上司への引き継ぎも重要
アフターケアは内示対象者だけでなく、異動先の受け入れ部署にも必要です。ここを軽視すると、異動者が「放り込まれた」と感じて孤立し、早期の離職リスクが高まります。事前に伝えることで、異動者がスムーズに新しい環境に適応しやすくなります。
- 異動の背景・期待される役割・本人の性格や強みを伝えておく
- 異動初日に歓迎の雰囲気をつくるよう働きかける
- 最初の1〜2週間は業務内容を段階的に引き継ぐ方針を示す
■ 定期的な1on1で変化を見逃さない
異動後は業務や人間関係、評価の仕組みも変わるため、社員にとっては大きな負荷となります。とくに最初の1〜3か月は「様子見期間」として丁寧なサポートが必要です。以下の様な対話が、長期的な定着やパフォーマンス向上につながります。
- 異動1週間後、1か月後など、定期的な1on1ミーティングを設定
- 感情面の変化や業務負荷の偏りを確認し、必要なら調整を提案
- 「頑張っているね」といった声かけを通じて心理的安全性を高める
■ 社員のキャリア全体を視野に入れる
アフターケアを“その場しのぎの対応”で終わらせるのではなく、中長期的なキャリア支援の一環として位置づけることが大切です。内示から異動後まで一貫したメッセージがあれば、社員は「会社にキャリアを応援してもらっている」と実感できます。
- 異動後のキャリアパスや成長機会を共有する
- 本人の意向や将来的な目標と、今回の異動がどう関係するかを説明する
- 必要に応じて人事面談の場を複数回設け、フィードバックを繰り返す
■ アフターケアの仕組み化が信頼をつくる
アフターケアは属人的な取り組みにとどめず、組織としての仕組み化が重要です。下記はその一例です。こうした仕組みがあることで、内示後も「見守られている感覚」を社員が持ちやすくなります。
- 異動後のフォローアップチェックリストを作成
- 異動先上司への対応ガイドを共有
- 1on1の実施状況を人事部がモニタリング
人事異動は、社員の信頼を損ねるリスクと、逆に信頼を深めるチャンスが同時に存在する場面です。内示を伝えるだけでなく、その後のきめ細やかなアフターケアまで丁寧に行うことで、異動を組織成長と人材育成の好機に変えることができるのです。
まとめ
人事異動における内示は、企業の人材マネジメントの中でも特に繊細なプロセスです。単なる人事情報の伝達ではなく、社員の心理、業務の連携、組織全体の信頼感に影響を与える極めて重要な局面であることを、改めて認識すべきです。今回のコラムでは、「人事異動の内示とは何か?」という基本的な定義から、辞令との違い、内示の種類、伝達タイミング、適切な伝え方、そしてその後のアフターケアまでを網羅的に解説してきました。
特に、現場を預かる人事担当者やマネージャーにとって、社員にどのような姿勢で臨むかは内示の成否を分ける要因になります。内示を受けた社員が「自分は会社からきちんと見てもらえている」と実感できるよう、個別性のある丁寧なコミュニケーションが求められます。また、異動先の部署や上司との調整、引き継ぎ計画などを内示時にある程度共有しておくことも、納得感を生む鍵となるでしょう。
今後、人的資本経営や従業員エンゲージメントが重視されるなかで、「内示の質」はますます重要性を増します。属人的な対応に頼るのではなく、組織としての明確な内示方針や実務フローを構築することが、持続可能な人事施策につながります。本コラムの内容が、貴社における内示運用の見直しや改善の一助となれば幸いです。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

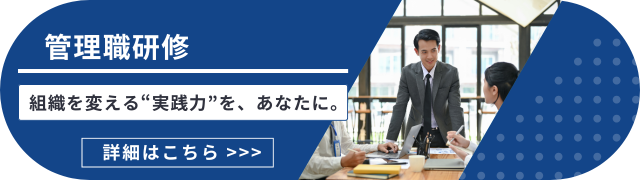


コメント