チームの成果を高めるうえで欠かせないのが「部下のモチベーション管理」です。しかし、「どうすれば部下のやる気を上げられるのか」「何をしても反応が薄い」と悩む上司も多いのが実情です。
本コラムでは、モチベーションの基本的な仕組みから、上下する要因、実際に効果のあった上げ方や失敗事例、さらにはモチベーション以外で生産性を上げる方法までを網羅的に解説します。部下のやる気を引き出し、組織全体の成果に結びつけたい方に役立つ実践的なヒントをお届けします。
< このコラムでわかる3つのポイント >
1.部下のモチベーションを上げる管理方法を実践的に理解できる
2.やる気が出ない部下への関わり方を適切に見直せる
3.モチベーションに依存しない生産性向上策を導入できる
Contents
そもそもモチベーションとは
モチベーションとは、簡単に言えば「行動を起こすための内的なエネルギー」です。仕事の場面においては、目標達成や成長、評価を求める気持ちなどがこれに該当します。上司の立場であれば、部下が主体的に動く状態を作りたいと考えるでしょうが、その背景にあるモチベーションの性質を理解しないままでは、的外れなアプローチに陥る恐れがあります。
モチベーションには、「内発的モチベーション」と「外発的モチベーション」の2種類があります。前者は「自分の成長が楽しい」「やりがいを感じる」など、自分自身の価値観や達成感に基づく動機。一方、後者は「上司に褒められたい」「昇進したい」「報酬がほしい」といった外部の要因によって動くものです。いずれも重要ですが、内発的なモチベーションの方が持続性が高く、創造性や主体性にもつながりやすいとされます。
ビジネスの現場では、外発的な刺激(報酬や罰)に頼るマネジメントも依然として一般的ですが、それだけでは長期的に成果を上げるのは難しくなってきています。社員一人ひとりの価値観が多様化している今、内発的な動機づけをいかに促すかが、上司にとっての重要なテーマとなっているのです。
モチベーションの種類とそれぞれの特徴

モチベーションを分類することで、より効果的なアプローチが可能になります。ここでは、内発的・外発的に加え、動機の深さ・質を分類軸とした「自己決定理論(Self-Determination Theory)」の視点も取り入れて説明します。
| モチベーションの種類 | 具体例 | 持続性 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 内発的動機づけ | 好奇心・成長欲求 | 高い | 楽しさややりがいが源泉となる |
| 同一化的動機づけ | 自らの価値と業務が一致 | 中〜高 | 意義を感じることで自発的になる |
| 外的動機づけ | 報酬・罰則・昇進 | 低〜中 | 環境に依存しやすい |
| 無動機 (アモチベーション) | 無関心・諦め | なし | 行動意欲そのものが欠如 |
このように、一口にモチベーションと言ってもその質や源泉はさまざまです。特に中長期で安定したパフォーマンスを期待する場合には、外的動機づけだけに頼らず、本人の価値観や目的意識と結びつけるような関わり方が求められます。
また、部下によってどのタイプが強く働いているかを見極めることも、マネジメントの第一歩です。たとえば、「この仕事にどういう意味があるのか」「自分はどこに向かっているのか」といった問いに対して関心を持つ部下には、目標設定やキャリアビジョンの共有が有効です。
さらに重要なのは、これらのモチベーションの段階は固定されたものではなく、変化するという点です。新しい業務やプロジェクトに挑戦する際には、最初は外的動機(評価・成果)によって動いていた部下が、経験を重ねるうちに仕事の意味ややりがいを見出し、内発的動機へと移行していくケースも多く見られます。
逆に、成長実感が持てない、評価されない、フィードバックがないといった状況が続くと、モチベーションは後退し、最悪の場合「無動機(アモチベーション)」の状態に陥ってしまうリスクもあります。これは「どうせ何をやっても意味がない」「頑張っても報われない」といった無力感が背景にあり、特に放置してはいけない状態です。
部下のモチベーションが上がらない理由
部下のモチベーションが上がらない背景には、職場環境や上司との関係性、成長機会の欠如など、さまざまな要因が潜んでいます。よくある4つの主要な原因に絞り、上司としてどのように見直すべきかを整理します。
1. 仕事の意義や将来性が見えない
人は「自分の仕事が何に役立っているか」「自分はどこに向かっているのか」が見えなければ、動機を失ってしまいます。とくに近年は、「社会的意義」や「キャリアの方向性」といった抽象度の高い問いを重視する社員が増えており、業務の意味づけを怠ると、早い段階でモチベーション低下につながります。例えば、「この作業は誰に影響を与えるのか」「なぜ今このタスクが必要なのか」といった背景情報を上司が共有していないと、単なる“指示待ち”の仕事として消化されてしまいます。
さらに、自身の将来像が不透明なまま日々の業務に追われていると、部下は「自分がここで何を目指しているのか」がわからなくなり、惰性で仕事をするようになります。キャリアパスの見通しやスキル習得の意味を定期的に言語化し、本人と共有するプロセスが必要です。
2. 公平な評価やフィードバックが得られない
評価制度があっても、納得感のないフィードバックや成果の不透明さがあると、部下のやる気は簡単に削がれてしまいます。特に不満を感じやすいのが、「頑張っても報われない」「どう評価されているのか分からない」という状態です。
この原因の多くは、上司のフィードバックの質や頻度に起因します。結果を伝えるだけではなく、具体的な行動に対する言及や、どのように改善すれば良いかの示唆がなければ、部下は次の行動を起こしにくくなります。
また、メンバー間での評価バランスが不均等だったり、成果主義が過度に強調されていると、内部での競争が激しくなり、チームとしての協働意識が希薄になります。「努力のプロセス」や「改善の取り組み」など、定性的な要素も適切に評価する姿勢が欠かせません。
3. 成長の機会が不足している
どんなに意欲のある部下でも、「学ぶ機会」「挑戦の場」がなければ成長実感は得られず、やがて倦怠感が生まれます。例えば、毎日同じルーティン業務を繰り返している、難易度の高い仕事はベテランに集中しており若手に回ってこない、といった職場では、モチベーションの源である“自分の変化”が感じられません。特に最近の若手社員は、「給与よりも経験」「安定よりも成長」を重視する傾向があります。そのため、適切なOJTやスキルアップ支援、ジョブローテーションなど、少しずつでも“成長の手応え”がある職場設計が必要です。
また、小さな成功体験を積み重ねることも、モチベーションを育てるうえで非常に有効です。「任せる・振り返る・承認する」の流れを習慣化することで、自己効力感が高まり、より主体的に動くようになります。
4. 信頼関係や職場環境にストレスがある
職場での人間関係、特に上司との信頼関係が希薄な状態では、部下は自分の意見や悩みを言えず、ストレスが蓄積します。「否定されるのではないか」「話しても意味がないのでは」と感じていると、チャレンジ精神や協調性が失われていきます。
また、業務量や責任が過多で体力的に疲弊している状態も見逃せません。やる気がないのではなく、物理的・精神的に余裕がないというケースが多く見られます。
信頼関係は、日々のコミュニケーションの積み重ねで築かれます。ちょっとした声かけや感謝の言葉、1on1での傾聴姿勢など、細やかな接点の中で「自分を見てくれている」という安心感を与えることが、モチベーションの土台となります。
部下のモチベーションを効果的に上げる方法
部下のモチベーションを上げるには、「本人の価値観や目的意識とつなげる」「信頼関係を築く」「成長実感を与える」といった人間心理に根ざしたアプローチが不可欠です。単なる報酬や叱咤激励では、一時的な効果にとどまりがちです。上司が日常のマネジメントに取り入れられる、具体的で実践的な方法を5つの切り口を紹介します。どれも小さな工夫でありながら、継続することで部下の自律性とエンゲージメントを高める強力な手段となるでしょう。
1. 1on1ミーティングの活用
定期的な対話の場を設けることで、価値観や悩み、目標を共有できます。雑談の延長ではなく、キャリア観や仕事の意義についても掘り下げましょう。
2. 意味づけと背景の共有
業務指示を出す際は、「なぜそれをやるのか」「誰にどう影響するのか」を必ず伝えるようにします。意義が伝わるだけで、行動が変わります。
3. 公平な評価とフィードバック
日々の行動に対するフィードバックが適切に届くと、承認感が高まり、自発性につながります。
4. 成長の機会を設計する
OJT、ジョブローテーション、学習支援制度などを通じて、自己成長の実感を持たせましょう。達成感はモチベーションの源です。
5. 心理的安全性の確保
「否定されない」「チャレンジを歓迎される」環境づくりも必須。部下が失敗を恐れずに行動できる場を提供することが、上司の役割です。
部下のモチベーションを上げる際に気をつけるべきポイント

部下のモチベーションを高めようとする上司の関わり方には、常に“意図と効果のズレ”が生じるリスクがあります。善意のつもりでも、アプローチの仕方を誤ると、信頼関係を損ねたり、かえって部下のやる気を奪ってしまうことも少なくありません。特に、画一的な指導や過度な干渉は、部下の自律性や主体性を低下させる原因となります。モチベーション向上の取り組みにおいて、陥りやすい注意点やありがちな失敗例を整理し、上司が避けるべきポイントを具体的に解説します。
- 押し付け型の目標設定:上司主導で目標を設定し、納得感がないまま進めると、形だけの達成を目指す状態になります。
- 過度な干渉や管理:細かく指示を出しすぎると、部下の裁量感や自律性が失われ、モチベーションは低下します。
- 承認の偏り:成果だけを褒めると、努力やプロセスが無視されていると感じる部下もいます。プロセスに注目する承認が重要です。
- フィードバックの不足や曖昧さ:曖昧な評価は信頼を損ねます。具体的な言葉と観察に基づいたフィードバックを心がけましょう。
- 一律の関わり方:部下のタイプはさまざまです。全員に同じアプローチをしても効果は限定的です。柔軟性と観察力が求められます。
モチベーション管理に「これをやれば必ず上がる」という万能の解はありません。だからこそ、観察力と試行錯誤の姿勢が鍵となります。
部下のモチベーションを上げようとして失敗する例
部下のモチベーションを高めようとする取り組みが、かえって逆効果になるケースは少なくありません。「良かれと思ってやったこと」が信頼を損ねたり、チームの分断を招いたりすることもあり、上司の関わり方には慎重な配慮が求められます。以下の様な具体例を通じて、表面的な施策の危険性や、相手・状況に応じた柔軟な対応の必要性について理解を深めることが重要になります。
- 褒めすぎて逆効果に:部下の行動すべてに「すごいですね」「さすがです」と反応していた上司。部下は最初こそ喜びましたが、次第に「本気で言ってない」「誰にでも言ってる」と感じるように。結果、信頼を失う結果に。
- 「自由にやっていいよ」が逆に混乱を招いた:裁量を与えるつもりが、目的や評価軸が明確でないまま放任したため、部下は何を期待されているのか分からず、迷走。最終的に成果も出ず、評価にも悪影響が出てしまった。
- 成果主義でチームが分裂:個人の成果ばかりを重視しすぎた結果、メンバー同士が競争関係になり、情報共有や協力体制が失われた。結果としてチーム全体の生産性が低下。
このようなケースでは、「意図は正しくても手法がズレていた」ことが失敗の原因となっています。正しいアプローチであっても、相手や状況によって調整が必要です。
モチベーション以外に部下の生産性を上げる方法
部下の生産性向上と聞くと、まず「やる気」や「モチベーション」が注目されがちですが、それだけでは十分ではありません。実際には、物理的な作業環境や制度設計、スキルと業務のマッチングといった“仕組み”の整備が、パフォーマンスに大きな影響を与えます。どれだけ部下が意欲的でも、ツールや制度が不十分であれば、本来の力を発揮することはできません。モチベーション以外の視点から、以下が部下のパフォーマンスを支える具体的な支援要素となります。
| 要素 | 内容 | 対応策例 |
|---|---|---|
| 業務環境 | IT環境・物理環境の整備 | リモートワーク環境、デバイス支給 |
| 業務設計 | 役割と業務量のバランス | タスクの最適化、分担見直し |
| 働き方 | 柔軟な勤務形態 | フレックス、在宅勤務制度 |
| 健康管理 | 身体的・精神的ケア | メンタルヘルス支援、産業医連携 |
| スキル | スキルと業務の適合性 | リスキリング、ジョブローテーション |
このように、環境や制度が整っていなければ、いくら部下がやる気を出しても成果に結びつきません。モチベーションを高める施策と並行して、制度面からの支援も計画的に行うことが求められます。
まとめ
部下のモチベーションを上げることは、単なる「声かけ」や「評価制度の整備」だけでは実現しません。重要なのは、部下一人ひとりの価値観や成長欲求を理解し、それに応じた方法で関わることです。また、上司自身が自己認識を深め、信頼関係を築く姿勢も求められます。モチベーションには外的要因と内的要因があり、どちらも適切に扱うことで初めて継続的な動機づけが可能となります。
本コラムで紹介したように、効果的なマネジメントには「何をすべきか」以上に「どう向き合うか」が問われます。部下の特性を理解し、組織全体の心理的安全性を高め、失敗を恐れずに挑戦できる風土を整備することが不可欠です。さらに、モチベーションのみに頼らず、仕組みや働き方の見直しによってパフォーマンス向上を支える視点も、今後ますます重要になるでしょう。人と組織の成長を両立させるために、上司として今何ができるのかを、ぜひこの機会に見直してみてください。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

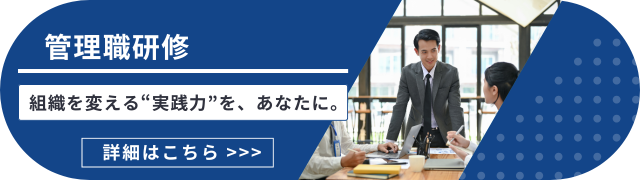


コメント