マネジメントに「向いている人」と「向いていない人」がいるのは事実です。しかし、その違いは生まれつきの才能ではなく、スキルや意識の持ち方で大きく変わります。本記事では、マネジメントに向いている人の特徴や必要なスキル、マネジメント力の高い人と低い人の違いを明確に解説します。
組織運営を担う経営者や人事責任者の方にとって、チームを強くするための実践的なヒントが詰まっています。マネジメントの適性を見極め、組織の生産性を高めるヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。
< このコラムでわかる3つのポイント >
1.マネジメント研修で育てるべきマネージャー像と必要なスキル・能力
2.各タイプのマネージャーに合った育成方針と支援のポイント
3.タイプ別の実践的な研修設計の進め方
Contents
そもそもマネジメントとは
マネジメントの基本的な定義とは
「マネジメント」という言葉は、職場で日常的に使われていますが、その意味を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。マネジメントとは、単なる「管理」ではなく、「組織の目標を達成するために、人・モノ・時間・お金などの経営資源を効果的に活用し、成果を最大化する仕組み」のことです。つまり、マネジメントの目的は「成果を出すこと」にあります。
マネジメントの役割は「人と組織を動かす」こと
マネジメントの最大の対象は「人」です。組織は人によって動き、成果も人によって生み出されます。個々の能力を最大限に引き出し、チームとして協働できるように整えることが、マネージャーに求められる重要な仕事です。単に業務を管理するだけでなく、部下が自発的に動ける環境を整備する力も必要です。
また、人だけでなく「組織そのもの」もマネジメントの対象です。組織全体の戦略やビジョンと、現場の実行をつなげる橋渡し役としての機能も担うため、現場と経営の両方を理解する視点が欠かせません。
「管理型」から「支援型」への変化
かつてのマネジメントは、トップダウンで指示・命令を徹底させる「管理型」が主流でした。しかし、現在の職場環境では、多様な価値観や働き方を受け入れる「支援型」マネジメントへの移行が進んでいます。メンバーの考えを尊重し、自律的に行動できるよう促す姿勢が求められるのです。
そのため、マネージャーには高いコミュニケーション能力、状況判断力、心理的安全性を生み出す力など、人間関係における繊細なスキルが必要とされます。
中小企業におけるマネジメントの重要性
特に中小企業では、限られた人材・資源の中で最大限の成果を出す必要があり、マネジメントの影響は非常に大きくなります。一人のマネージャーの手腕が、部署全体の生産性や離職率に直結するケースも多く見られます。
さらに、プレイングマネージャーが多い中小企業では、実務とマネジメントを両立する難しさもあります。マネジメントの基礎的な知識と実践的なスキルを身につけておくことは、組織全体の安定と成長に直結する重要課題です。
経営者や人事が知っておくべき視点
マネジメントは一部の管理職だけの役割ではなく、組織全体の文化として根付かせる必要があります。経営者や人事責任者は、マネジメントを単なる「職務」ではなく、「成果を出すための組織的機能」として捉え、継続的な育成・評価の仕組みを整えることが求められます。
マネジメントに必要な能力やスキル

優れたマネジメントを実現するには、単に業務知識や経験が豊富であるだけでは不十分です。成果を生み出すためには、状況を見極め、最適な判断と行動を導くスキルや能力が求められます。
ここではマネジメントに不可欠なスキルを、大きく3つのカテゴリに分けて解説します。
1. 人に関するスキル(対人関係能力)
マネジメントの中心にあるのは「人」です。部下やチームメンバーと信頼関係を築き、モチベーションを高めるためには、コミュニケーション能力が何より重要です。具体的には、傾聴力、伝達力、共感力、タイミングを見極めたフィードバック力が挙げられます。また、メンバーの悩みや葛藤を引き出し、適切に導くコーチング力も高く評価されるスキルのひとつです。
2. 業務に関するスキル(業務遂行力)
業務を円滑に進めるためには、目標設定から計画立案、進捗管理、問題解決に至るまで、一連の業務遂行スキルが必要です。特に中小企業では、限られたリソースをどう効率的に配分するかという「資源配分力」や、リスクを想定して事前に備える「リスクマネジメント能力」がマネージャーに求められます。また、メンバーごとの適正やキャパシティを把握し、タスクを最適に割り振る力も欠かせません。
3. 組織に関するスキル(俯瞰的視点)
個々のタスクやメンバーの動きだけでなく、チームや部署、会社全体を見渡す俯瞰的な視野も重要です。組織の方向性に沿って目標を設計し、人員配置や評価制度を調整する「組織設計力」や、「変化への適応力」なども現代マネジメントには不可欠です。企業を取り巻く環境が常に変化している以上、柔軟な判断とスピーディな対応が求められます。
また、これらのスキルを土台から支えるのが「EQ(感情知能)」です。感情のコントロールや、ストレス耐性の高さは、対人関係でトラブルを防ぎ、冷静な意思決定を助けます。総じて言えるのは、マネジメントは一部のエリートが行う特殊な職能ではなく、努力と訓練で誰でも身につけられるスキルの集合体であるということです。
マネジメントに向いている人の特徴

共感力があり、他者視点で考えられる人
マネジメントにおいてもっとも重要な力のひとつが「共感力」です。部下やチームメンバーの立場に立って物事を考えられる人は、信頼関係を築くのが早く、良好な人間関係をベースにしたマネジメントが可能になります。相手の話をしっかり聞く姿勢があり、感情や背景を理解しようと努める人は、自然とメンバーからの信頼を得られやすくなります。信頼があることで指示が通りやすくなり、チームのパフォーマンスも高まります。
自己管理ができ、冷静な判断を下せる人
マネジメントの現場では、日々さまざまなトラブルや意思決定の場面が発生します。その際、感情に流されず冷静に判断できるかどうかがマネージャーの質を左右します。怒りや焦りといった感情を抑え、状況を客観的に分析し、合理的な対応が取れる人は、部下からの安心感と尊敬を得られる傾向があります。さらに、マネージャー自身が安定していることで、チーム全体に落ち着きが生まれ、良好な職場環境の土台となります。
課題解決志向が高く、目的から逆算できる人
日常の業務に流されず、常に「目的は何か」「今やっていることは目的達成にどのようにつながるのか」を考えられる人は、マネジメントに向いています。課題の本質を捉え、的確な改善策を提示できる人材は、組織にとって不可欠な存在です。また、問題発生時に感情的にならず、「どうすれば改善できるか」に目を向ける姿勢は、部下にも前向きな影響を与えます。目的志向・改善志向の高さは、成果に直結する重要な資質です。
聞く力と「任せる力」を持っている人
マネジメントでは「指示する力」以上に「聞く力」が重視されます。部下の声をきちんと聞き、背景や感情も含めて理解しようとする姿勢は、信頼と安心感を生み出します。また、すべてを自分で抱え込まず、メンバーに業務を任せる勇気も必要です。「任せること」は、部下の成長機会をつくるだけでなく、マネージャー自身の時間を戦略的に使うためにも欠かせません。任せることで、部下の主体性と責任感を引き出すことができます。
誠実で一貫性があり、公平な判断ができる人
マネジメントに向いている人の共通点として、「誠実さ」と「一貫性」が挙げられます。言動がブレない、部下によって態度を変えない、ルールを自分にも適用する――こうした姿勢は、部下からの信頼を得る基盤となります。また、評価や指示の内容に納得感があるかどうかは、マネージャーとしての公平性に直結します。一人ひとりをフラットに扱い、適切な対応を取り続けられる人は、長期的に安定したマネジメントが可能です。
マネジメントに向いていない人の特徴
コミュニケーションを避けがちな人
マネジメントでは部下やチームとの密なやり取りが必要ですが、それを避けがちな人はマネジメントに不向きと言えます。特に、会話を必要最小限にとどめたり、対面でのやり取りを避けてメールやチャットのみで済ませようとする傾向が強い人は、チームとの信頼関係を築くのが難しくなります。マネジメントは「人を動かす仕事」であり、円滑なコミュニケーションはその大前提です。
完璧主義で細かすぎる指示を出す人
問題や失敗が起きた際に、原因をすぐに部下や他部門のせいにする人は、マネジメントには向いていません。マネージャーは組織の中での「結果責任」を担う立場です。自分の判断や指示の結果を他人に押しつけてしまう姿勢は、部下からの信頼を一気に損ないます。信頼のないマネジメントは、指示が通らず、チームがまとまらない大きな要因になります。
主体性やビジョンが欠如している人
部下は、マネージャーの姿勢や行動を常に見ています。自分から動かず、上司の指示を待ってばかりの「受け身型マネージャー」では、リーダーシップを発揮することはできません。また、「何のためにこの仕事をしているのか」といった目的意識や、チームとしてのビジョンを持たないマネージャーの下では、部下のモチベーションも維持できません。目標の共有ができないままでは、チーム全体の方向性がブレてしまいます。
フィードバックが苦手、もしくは一方的すぎる人
マネジメントにおいてフィードバックは極めて重要な役割ですが、それがうまくできない人も向いていないといえます。まったくフィードバックを行わない、あるいは批判ばかりして終わるマネージャーでは、部下が成長する機会を失います。適切なタイミングで、相手の人格を否定せずに行動に対して具体的なコメントを伝える力は、マネジメントにおける基本中の基本です。一方的に話すだけで相手の反応を見ない、双方向性を欠いたフィードバックは逆効果になることもあります。
マネジメント力を身につける方法

自己理解を深める
マネジメント力を高める第一歩は、他人を理解する前に「自分自身を理解すること」です。自身の価値観やストレスの傾向、行動特性を把握することで、より効果的なリーダーシップの取り方が見えてきます。例えば、何が苦手でどんなときにイライラしやすいかを知っておくだけで、部下への対応の質が変わります。近年では、性格診断ツールやEQ診断、360度評価などを活用して自己認識を深める企業も増えています。
小さなリーダー経験を積む
マネジメントスキルは実務経験を通じて磨かれる側面が大きいため、いきなり大きなチームを任せる必要はありません。最初は数名のプロジェクトやタスクチームのリーダーとして、進捗管理やメンバーとの調整などを体験することが有効です。このような小さな成功体験の積み重ねが、自信とスキル向上に直結します。また、経験の場を意図的に与えることは、人材育成の一環としても非常に効果的です。
ロールモデルから学ぶ
自分が信頼できる上司や先輩など、身近な「ロールモデル」を見つけて学ぶことも、マネジメント力を伸ばす有効な方法です。「なぜこの人の言葉は部下に響くのか」「なぜこの人のチームは生産性が高いのか」といった観察を通じて、自分のマネジメントスタイルをつくるヒントが得られます。模倣から始まり、自分なりのアレンジを加えることで、自然とマネジメントの引き出しが増えていきます。
継続的な学習と内省
マネジメントは「やって終わり」ではなく、常に変化に対応する柔軟さが求められます。そのためには、継続的な学習と内省が不可欠です。ビジネス書や研修、セミナーに参加することで知識をアップデートし、日々の業務を振り返ることで改善の糸口をつかむことができます。「あの時なぜうまくいかなかったのか」「もっと良い対応はなかったか」と考える習慣が、マネジメントの質を高めるのです。
フィードバックを積極的に活用する
自分のマネジメントに対する他者の反応を知ることも重要です。上司や同僚、部下からのフィードバックを受け入れることで、自分では気づきにくい盲点や改善点を把握できます。最近では、定期的にチーム内で相互フィードバックを行う文化をつくる企業も増えており、マネジメント力の底上げに役立っています。受け身ではなく、フィードバックを「求めにいく」姿勢が、学びを加速させます。
マネジメント能力を証明するための資格

マネジメント力は本来、実務経験や成果によって評価されるべきものですが、それを客観的に証明できる「資格」は、育成や評価制度の基準としても有効です。特に中小企業では、マネージャー候補の育成や登用において、「適性があるか」「知識は十分か」を見極めるツールとして資格取得を活用する企業が増えています。また、資格は自己研鑽の証として社内外にアピールする材料にもなります。
ビジネスマネージャー検定試験(東京商工会議所)
東京商工会議所が主催する「ビジネスマネージャー検定試験」は、マネジメント初心者にも適した国家資格級の知識体系を学べる検定です。組織運営、人材育成、コンプライアンス、リスク管理、業績管理といった幅広い内容をカバーしており、実務に即した学びが得られます。難易度はそこまで高くないため、マネジメント未経験者や若手リーダーの登竜門としておすすめです。
中小企業診断士
より高い専門性と実務知識を証明したい方には、「中小企業診断士」が適しています。経営戦略や人事・労務、財務、マーケティングまでを体系的に学べる国家資格で、マネジメント全体を理解するのに非常に有効です。取得には一定の勉強時間が必要ですが、経営層や管理職としての視座を高めるうえで、非常に価値のある資格です。社外でも高い評価を受けるため、キャリアアップにも有利に働きます。
PMP(Project Management Professional)
プロジェクトマネジメントに特化した「PMP(Project Management Professional)」は、グローバルに通用する資格です。特にIT業界やコンサルティング業界では評価が高く、プロジェクトの進行管理、リスク対応、コミュニケーション設計など、マネジメントスキルの実践力を証明できます。社内プロジェクトのリーダーを任される機会が多い人にとっては、実務に直結する内容となっています。
資格は「きっかけ」に過ぎない
資格取得はあくまでスタートラインです。大切なのは、学んだ知識を現場でどう活かすかという視点です。組織の課題やチームの状況に合わせて応用しながら、継続的にスキルをアップデートすることが、真のマネジメント力につながります。また、資格取得を通じて得たフレームワークや視座を、部下育成や業務改善に活かすことで、周囲からの信頼も高まります。
マネジメントにおけるリーダーシップの役割
マネジメントとリーダーシップの違いとは
「マネジメント」と「リーダーシップ」は混同されがちですが、実際には異なる役割を持っています。マネジメントは「組織や業務を安定的に運営すること」、つまり現状維持や目標達成に向けた計画と管理が主な役割です。一方で、リーダーシップは「人を動かす力」であり、チームを鼓舞し、新しい方向へ導く推進力のことを指します。簡単に言えば、マネジメントは『組織を機能させる力』、リーダーシップは『組織を変革させる力』です。どちらか一方だけでは不十分で、両方を適切に使い分けることが、現代のマネージャーには求められています。
なぜリーダーシップが必要なのか
現代の組織では、単なる「業務管理」だけでは成果が出にくくなっています。市場の変化、テクノロジーの進化、働き方の多様化など、変化に柔軟に対応できる組織が求められているためです。そうした中で、ビジョンを示し、人の心を動かすリーダーシップが、マネジメントの実行力を支える重要な要素になってきています。
また、指示命令型のスタイルでは、部下が受け身になりやすく、主体性が育ちません。リーダーシップの本質は「自ら考えて動きたい」と思わせる空気を作ることにあります。感情面へのアプローチや価値観の共有が、マネジメントの成果を一段高めてくれます。
リーダーシップの主要スキル
効果的なリーダーシップを発揮するためには、次のようなスキルが求められます。
- ビジョン提示力:どこに向かうべきかを明確に示す力。抽象的な理念ではなく、チームが具体的に動けるようなゴールを提示できるかどうかが重要です。
- 影響力・説得力:強制ではなく、自発的に動きたくなるような言葉と行動で周囲を動かす力。信頼と一貫性のある姿勢が基盤になります。
- 心理的安全性の確保:部下が安心して意見を言える環境を作る力。人間関係における安定性が、創造性や挑戦意欲を生み出します。
マネジメントにおける融合的アプローチ
理想的なマネージャーは、「管理者」であり「リーダー」でもあります。たとえば、チームの進捗を数値で管理しながらも、個々の目標に意味づけを行い、メンバーの感情面にも配慮できるバランス感覚が求められます。このように、マネジメントとリーダーシップは分離するものではなく、両輪として融合させて使うことが、現場での成果につながります。
現代のリーダーシップはカリスマ性ではなく、「信頼される姿勢」と「日常の言動」で築かれるものです。つまり誰でも習得可能であり、実践を通じて育まれていくものだといえるでしょう。
マネジメントにおける課題とその対策

マネージャーの役割が曖昧
多くの組織で見られる課題の一つが、「マネージャーの役割が明確に定義されていない」ことです。プレイヤーとしての実務に追われるあまり、マネジメント業務が後回しになってしまうケースが多く見られます。また、評価制度の中でも、マネジメント行動が具体的に何を指すのかが明文化されていないことも問題です。
対策
役割を明確化し、「チームの成果に責任を持つ」「部下育成を担う」などの基準を明示することが必要です。職務定義書や等級制度の見直しを行い、マネージャーが果たすべき責務と期待を言語化することで、迷いのない行動が促されます。
コミュニケーションの質と量の不足
マネジメント不全の原因としてよく挙げられるのが、コミュニケーションの不足です。指示は出すがフォローをしない、部下の状態に無関心、評価のフィードバックを怠る―こうした状況は、部下の不満や不信感を招きます。特にリモートワークが普及した現在、物理的な距離が心理的距離につながるリスクが高まっています。
対策
定期的な1on1ミーティングの実施や、雑談を含めた非公式な対話の機会を増やすことが有効です。また、聞く力を鍛え、相手の意図や感情をくみ取る姿勢を意識することで、信頼関係の基盤が形成されます。
部下育成への時間・スキル不足
現場では、「人を育てる時間がない」「育て方がわからない」といった悩みも多く聞かれます。結果として、指示命令型に偏ったマネジメントになり、部下の成長を妨げてしまうのです。また、教育を人事任せにしてしまい、現場の上司が育成に無関心というケースもあります。
対策
育成は現場マネージャーの重要な責任であると認識を共有し、業務の一部として時間を確保する必要があります。OJTの手法やフィードバックの技術を習得できる研修を提供し、現場でも実践できるようサポートする仕組みを整えることが求められます。
評価の不透明さと納得感の欠如
評価制度が不明瞭であったり、上司の主観で判断されていると感じられると、部下のモチベーションは下がります。努力が正当に認められていないという印象は、不満や離職につながる深刻なリスクを含んでいます。
対策
行動評価やコンピテンシー評価などの客観的な指標を導入し、評価基準の透明性を高めることが重要です。また、評価結果について説明責任を果たす場を設けることで、納得感と信頼性が向上します。
まとめ
マネジメントは、単なる業務の管理にとどまらず、組織全体の方向性を示し、メンバーの力を最大化する重要な役割です。マネジメントに向いている人の特徴を理解することで、適材適所の配置や育成に活かすことができ、結果として組織の生産性や士気の向上にもつながります。
また、マネジメントに必要なスキルや能力は、特別な才能ではなく、経験や学習、継続的なフィードバックを通じて誰でも習得可能です。現場で実践する中で、自身のマネジメントスタイルを確立していくことが重要です。
一方で、マネジメントに向いていない傾向が見られる人も、課題に気づき、改善に取り組むことで成長のチャンスを得ることができます。経営者や人事責任者は、個人の特性だけで判断するのではなく、教育機会や環境づくりを通じて、マネジメント力を高める組織づくりを目指すことが求められます。
本記事を参考に、自社にとって理想的なマネジメントのあり方を見直すきっかけとしていただければ幸いです。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

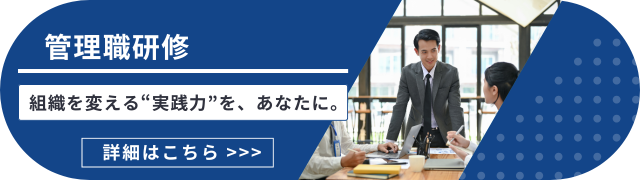


コメント