部下のモチベーションを高め、維持することは、現代の組織マネジメントにおいて極めて重要なテーマです。やる気のある社員は、業務効率や生産性を高めるだけでなく、組織全体の活性化にも寄与します。しかし実際には、どのようにモチベーションを管理すればよいのか、悩んでいる管理職も多いのが現実です。
本コラムでは、モチベーション管理の基本から、外発的・内発的動機づけの違い、部下のやる気を引き出すための具体的な方法まで、理論と実践を交えてわかりやすく解説していきます。
< このコラムでわかる3つのポイント >
1.部下のやる気を引き出すために管理職がとるべき具体的アプローチ
2.外発的・内発的モチベーションの違いと活用方法の整理
3.モチベーションを継続的に高めるための職場づくりの要点
Contents
モチベーション管理とは
モチベーション管理とは、組織や管理職が従業員の「やる気」や「働く意欲」を維持・向上させるために行うマネジメント施策や行動全般を指します。単に報酬を与えたり、褒めたりするだけでなく、仕事への意味付けや自分自身の成長実感、心理的安全性など多面的な要因が関係しています。
現代のビジネス環境において、社員の価値観や働く動機は多様化しています。「お金のために働く」だけでなく、「社会貢献をしたい」「成長したい」「仲間と協力して成果を出したい」といった内面的な欲求が仕事への動機になっていることも珍しくありません。そのため、従来の一律的な管理手法では対応しきれないのが実情です。
また、人的資本経営が注目される中で、「人のやる気」や「働きがい」といった定性的な要素をいかに可視化・分析し、組織の成果に結びつけるかという視点も重要になっています。企業が人材に投資する際、その投資がどのような効果を生み出すのかを把握するには、モチベーションの状態を把握し、適切に管理することが欠かせません。
ここで重要なのは、「管理」という言葉の捉え方です。「コントロール」ではなく「サポート」というスタンスが求められます。管理職は、部下を動かす存在ではなく、部下が自分の意志で動きたくなる環境を整える支援者であるべきです。つまり、上司は「何をすべきか」を指示するのではなく、「どうすればその人がやる気になるか」を考える視点が求められます。
また、モチベーションの管理は短期的な成果を追うものではなく、継続的に取り組むべきテーマです。モチベーションは目に見えないものであるため、「調子が悪そうだな」と感じたときには、すでに問題が進行していることもあります。日頃から部下の表情や口数、姿勢などに目を配り、早期に変化を察知することもマネージャーの重要な役割といえるでしょう。
部下のモチベーションを管理する方法

部下のモチベーションを効果的に管理するためには、管理職としての基本的なスタンスと具体的なアプローチの両方が必要です。まず第一に大切なのは、「部下一人ひとりの価値観や目標を理解すること」です。人によってモチベーションの源泉は異なります。キャリアアップを望む人もいれば、ワークライフバランスを重視する人もいます。上司がその違いを理解し、対応を変えることが重要です。
次に、部下と定期的な1on1ミーティングを行い、信頼関係を築くことも有効です。定期的な対話を通じて、部下が感じている不満や悩み、成長への意欲を把握することができれば、必要なサポートや評価も適切に行えるようになります。このようなコミュニケーションは、心理的安全性の向上にもつながります。
さらに、目標設定とフィードバックの運用もモチベーション管理の基本です。目標は「達成可能だがチャレンジング」であることが望ましく、個人の成長実感を促す内容であるべきです。また、評価においては、プロセスも含めた多面的な視点が重要です。結果だけを見るのではなく、努力や行動も評価することで、部下は「見てもらえている」という実感を得ることができます。
以下のような要素を押さえることで、より実践的なモチベーション管理が可能になります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 個別対応 | 部下の価値観や目標に応じたアプローチ |
| 定期的対話 | 1on1ミーティングやフィードバックの実施 |
| 公正な評価 | プロセスや成長も含めた評価システム |
| 達成可能な目標 | チャレンジと現実性のバランスがとれた目標設定 |
| 承認と感謝 | 成果だけでなく努力や挑戦への感謝を伝える姿勢 |
モチベーションの管理には万能な手法はありませんが、「人を理解しようとする姿勢」そのものが、部下にとってのモチベーションとなり得るのです。
外発的動機づけとは
外発的動機づけとは、報酬や評価、昇進、他者からの承認といった外部から与えられる要因によって人が行動を起こす動機づけのことを指します。企業においては、「目標達成でボーナスが出る」「営業成績に応じて昇進できる」「上司から褒められる」といった例が典型的です。こうした外的な刺激によって、部下が仕事に対するやる気を一時的に高めることはよくあります。
この外発的動機づけの最大の利点は、即効性が高い点にあります。特に成果主義の文化においては、短期的に成果を上げる必要がある場面で効果を発揮します。また、数値目標が明確に設定されている部署では、業績と報酬が連動する仕組みは部下の行動を促進する手段として機能しやすいのも事実です。
しかし、外発的動機づけには限界も存在します。その最大の課題は「持続性」にあります。報酬や評価といった外的な刺激がなくなると、モチベーションも下がってしまう可能性が高いからです。例えば、キャンペーンのインセンティブ期間が終了すると売上が急激に落ち込む、といった現象はこの典型です。また、報酬が高くなればなるほど、それが「当たり前」になり、さらなる動機づけには新たな刺激が必要となるため、管理コストが膨らんでいく傾向にあります。
さらに、外発的動機づけは、長期的な内面的満足や自律性の育成にはつながりにくい点も問題です。部下が「評価されたいから頑張る」「怒られたくないから動く」といった姿勢に偏ると、主体性や創造性が失われやすくなります。これでは、変化が激しい現代のビジネス環境に適応する柔軟な人材育成には限界があります。
とはいえ、外発的動機づけそのものを否定する必要はありません。重要なのは、「使いどころ」と「バランス」です。例えば、新人や若手社員にとっては、行動の方向性を明確に示し、成功体験を積む上で有効な手段です。また、短期的なプロジェクトや業務集中期において、集中力を高める目的でインセンティブを設定するのは非常に効果的です。
管理職としては、外発的動機づけに依存するのではなく、これをきっかけにして、徐々に内発的動機づけにつなげていくステップを設計することが望ましいです。例えば、最初は報酬で動いていた部下が、徐々に「この仕事の意味」や「自分の成長」に価値を見出すように導くような関わりが理想です。
まとめると、外発的動機づけは短期的な行動喚起には非常に有効である一方で、それだけに頼ると部下の自律性や内面の成長を阻害するリスクもあります。だからこそ、外的な刺激をうまく活用しつつ、同時に部下自身が「自分の意志で行動する」内発的な力を育てていくことが、持続可能なモチベーション管理の鍵となるのです。
内発的動機づけとは
内発的動機づけとは、人が外部からの報酬や圧力ではなく、自分の内側から湧き上がる欲求や関心によって行動する状態を指します。つまり、「やらされる」ではなく「やりたいからやる」という心の動きに基づいたモチベーションです。これは、部下の長期的な成長や組織への貢献に大きく影響する重要な要素です。
内発的動機づけの例としては、「自分のスキルを高めたい」「仕事そのものが面白い」「お客様の役に立ちたい」といった、自律的で深い満足感を伴う動機が挙げられます。例えば、報酬が出なくても休日に専門書を読む社員や、自ら新しいアイデアを提案してくる部下などは、内発的動機づけが強い状態といえるでしょう。
心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによる「自己決定理論(Self-Determination Theory)」では、内発的動機づけの基盤として以下の3つの基本的欲求が重要であるとされています。
| 基本的欲求 | 内容 |
|---|---|
| 有能感 | 自分には能力がある、成長していると感じられること |
| 関係性 | 他者とのつながりや信頼関係が感じられること |
| 自律性 | 自分の意志で選択・行動しているという感覚 |
上司や組織がこの3つの要素を支援することで、部下の内発的モチベーションは自然と高まりやすくなります。例えば、難しいプロジェクトに挑戦させて成功体験を得させる(有能感)、チーム内での連携や貢献を実感できる機会をつくる(関係性)、業務の進め方や目標を自ら決められる余地を与える(自律性)といった支援が考えられます。
内発的動機づけのメリットは多く、持続性が高いこと、柔軟な発想が生まれやすいこと、仕事への主体的な取り組みが増えることが挙げられます。特に変化の多い現代においては、上司からの指示を待つのではなく、自ら課題を見つけて解決に動ける社員の存在は、組織の競争力そのものと言っても過言ではありません。
一方で、内発的動機づけを高めるには、時間と信頼関係の構築が必要です。外発的動機づけのように「これをやればインセンティブが出る」といった即効性は期待できません。そのため、管理職には「短期の成果」だけでなく「長期的な人材育成」という視点が求められます。
また、職場環境が過度に管理的であったり、上司からの信頼や裁量がまったくない場合、内発的モチベーションは容易に失われます。たとえ部下がやる気に満ちていても、それを発揮できる「場」や「自由度」がなければ、本来の力を発揮することは難しいのです。
だからこそ、上司は「部下の自律性をどう育てるか」を常に意識して関わる必要があります。そのためには、仕事の意味づけを伝える、裁量のある業務を任せる、成果ではなくプロセスや工夫を認めるなど、信頼と成長を支える働きかけが求められます。
内発的動機づけの高い部下は、外的なプレッシャーがなくても自ら進んで動き、困難な状況でも粘り強く取り組む傾向があります。こうした力を持つ人材を育てることが、組織にとって最大の人的資本投資であると言えるでしょう。
部下のモチベーションが下がる理由

部下のモチベーションが下がる要因を理解することは、効果的な管理の第一歩です。いくら動機づけを行っても、根本的な問題に気づかず放置すれば、成果にはつながりません。むしろ、対策が裏目に出て、さらなる離職やパフォーマンス低下を引き起こす可能性すらあります。ここでは、部下のやる気が失われる代表的な理由を体系的に整理して解説します。
まず最も多い理由は、「評価や報酬が不透明・不公平であること」です。頑張っても評価されない、あるいは評価基準が曖昧で、何を頑張ればよいかわからないという状態は、モチベーションを著しく低下させます。これは、部下が努力と成果の因果関係を実感できないことによるものです。管理職が公平な評価軸と定期的なフィードバックを行わない場合、この不満は加速度的に広がります。
次に挙げられるのが、「仕事の意義が見えない」という問題です。特に若手社員やZ世代にとっては、「なぜこの業務をやっているのか」「誰の役に立っているのか」が見えることが重要なモチベーション源になっています。ただ作業をこなすだけの業務では、意義を感じられず、やる気が続きません。逆に、「この仕事は顧客の課題を解決している」「このデータ分析は経営判断に貢献している」といった意味づけがなされれば、モチベーションは高まりやすくなります。
また、「上司との信頼関係が築けていない」ことも深刻な要因です。1on1の機会がない、相談しても聞き流される、承認されない、過度に管理される――こういった経験が積み重なると、部下は「この人には期待されていない」と感じ、業務への熱意を失っていきます。モチベーション管理は、技術というよりもまず関係性の土台が重要であり、心理的安全性がなければどんな制度も機能しません。
さらに、「成長実感が持てない」という点も要注意です。人は本質的に、自分が成長していると感じるときに最もやる気を出します。日々の業務がルーチン化しており、挑戦機会が与えられず、成果を出しても次のステップがない状態では、部下は「このままでいいのか?」と不安になり、やがて惰性で働くようになります。特に20代〜30代前半の若手社員にとっては、「成長実感」はキャリア継続の鍵でもあるため、管理職が意識して支援する必要があります。
最後に、「過度なストレスや疲労の蓄積」もモチベーションを損なう大きな原因です。過重労働、人間関係の悪化、タスクの優先順位不明瞭などが重なると、エネルギーが奪われ、やる気を持つ余裕すらなくなります。このような環境では、モチベーション以前に、健康やメンタルの問題が表面化してくるため、早期発見と対応が不可欠です。
以下の表に、モチベーションが低下する主な理由と、それに対する管理職の対策例を整理します。
| モチベーション低下の要因 | 管理職に求められる対応例 |
|---|---|
| 評価・報酬の不透明さ | 評価基準の明示、定期的なフィードバック |
| 仕事の意義が感じられない | 業務の目的や影響範囲を説明 |
| 信頼関係の欠如 | 1on1の実施、傾聴姿勢、承認・感謝の言葉を伝える |
| 成長の停滞 | 新たな挑戦の機会、キャリアの方向性についての対話 |
| ストレスや疲労 | 業務量の調整、メンタルヘルスケアの導入 |
モチベーションの低下は、本人の問題だけでなく、組織側の環境要因が影響しているケースが大半です。だからこそ、上司には「何が起きているかを把握しようとする姿勢」と「実際に改善するためのアクション」の両方が求められるのです。
モチベーションが高い部下を保つためには
一度高まった部下のモチベーションを継続的に維持することは、管理職にとって極めて重要な課題です。短期的な動機づけに成功しても、放置すればやる気は徐々に低下してしまいます。モチベーションを「上げる」ことと「保つ」ことは別のスキルであり、特に長期的な組織成長を見据えるなら、後者に焦点を当てる必要があります。
まず大前提として、モチベーションの維持には継続的な関心と対話が不可欠です。「一度褒めたから十分」「一度成果を出したから放っておいても大丈夫」という考えは危険です。部下は常に変化しています。キャリアのステージ、プライベートの状況、職場の人間関係などによって、やる気の源泉は変わるものです。その変化に気づき、対応することが、モチベーション維持の鍵となります。
次に、「承認」と「成長」の両立も重要な要素です。モチベーションが高い部下は、成果を出しやすいため、つい「任せきり」になってしまうことがあります。しかし、成果が出ていても、それが当たり前と扱われれば、やがてその部下は「自分は評価されていない」と感じるようになります。だからこそ、「結果を出して当然」と思わず、小さな貢献でもきちんと認め、感謝の言葉をかけることが重要です。
また、モチベーションが高い部下ほど、「次のステップ」を明確に提示することが求められます。「この調子で頑張って」と抽象的に伝えるのではなく、「このスキルを磨けば、次はこのプロジェクトを任せたい」といった具体的な期待を示すことで、部下は自身の成長イメージを描きやすくなります。成長実感は、やる気を継続させる最強のエネルギーです。
さらに、意外と見落とされがちなのが、「モチベーションの高い部下にも限界はある」という視点です。責任感が強く、自ら仕事を引き受けるタイプの部下ほど、過重労働やメンタル不調のリスクを抱えがちです。上司としては、その頑張りを前向きに受け止めると同時に、仕事量や負荷のバランスを調整し、適切なサポートを行うことも忘れてはなりません。
以下のような習慣を取り入れることで、モチベーションの高い部下を維持し、さらに育てることが可能です。
| 習慣 | 具体的な行動例 |
|---|---|
| 定期的なフィードバック | 成果・姿勢の双方に対する具体的なコメントを伝える |
| 意義の再確認 | プロジェクトの目的や社会的意義をチームに共有する |
| 次のステップの提示 | スキル習得→役割拡大などのキャリアパスを示す |
| 適切なリソース配分 | 業務量を適正化し、疲弊や燃え尽きの予防を図る |
| チーム内での承認文化の醸成 | 上司だけでなく、仲間同士で感謝を伝える文化を育てる |
最終的に、モチベーションの維持は「環境づくり」に帰結します。つまり、部下が「ここで働くことに価値を感じる」「このチームで成長できる」と思えるような組織文化を醸成することが、最も強力な動機づけになります。人は感情の生き物です。制度や評価だけでなく、「自分はここで認められている」「理解されている」という感覚が、働き続けたいという気持ちを支えるのです。
管理職や人事担当者が、部下の個性を尊重しながら、その人らしく活躍できる環境を整える―それが、モチベーションを高く保つ最大の秘訣です。
まとめ
モチベーションは、部下が自律的に行動し、成果を出すための原動力です。その管理は、単に評価制度や目標設定だけにとどまらず、上司がどのように関わり、どのように部下の内面に働きかけるかという「人を理解する力」にも深く関わっています。外発的動機づけと内発的動機づけのバランスを意識しながら、それぞれの部下に適した対応が求められます。また、モチベーションが低下する背景には、環境や心理的要因があることも多く、マネジメント層にはその変化を察知し、早期に対応する力が問われます。
本コラムでご紹介したモチベーション管理の基本や具体的な方法を、現場のマネジメントに活かすことで、チームの活性化や人材の定着率向上にもつながるはずです。組織づくりにおいて「人の気持ちに目を向ける」視点を強化したいと考えている方は、ぜひ一度、貴社の管理体制やコミュニケーションのあり方を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

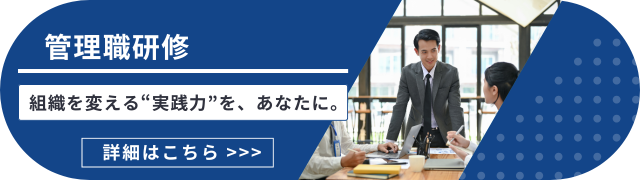


コメント