近年、企業の持続的成長には「管理職」の育成が欠かせません。しかし、現場では育成がうまくいかず、リーダー層が機能しないまま組織全体に悪影響を及ぼすケースも。管理職が直面する課題や求められる役割とは何か?本コラムでは、育成に失敗しないための研修や対策のポイントを具体的に解説します。
< このコラムでわかる3つのポイント >
1.管理職育成で陥りやすい典型的な失敗パターン
2.育成において失敗を防ぐために事前に整えるべき設計と準備
3.実効性ある育成施策に必要な人事と現場の連携体制
Contents
管理職の定義とは
近年、多くの企業が「管理職育成」に対して強い危機感を抱くようになっています。急激な社会変化や働き方の多様化、労働市場の流動化などを背景に、管理職に求められる役割やスキルは複雑化し続けており、それに対応するための育成体制の強化が急務となっているのです。
かつては、「優秀な現場のプレイヤーがそのまま管理職になる」ことが一般的でした。一定の年次や成果に応じて昇進し、「見よう見まねでマネジメントを覚える」というスタイルでも組織は回っていました。しかし、今は違います。管理職が担うべき責任や役割が高度化し、曖昧な状態のままでは通用しない時代に突入しています。
なぜ今、管理職育成が重要なのか?
多くの企業が直面している共通課題の一つに、「組織の中核が機能していない」という問題があります。現場でトラブルが多発したり、チームの離職率が高かったり、社員満足度が低迷していたりする場合、その原因は表層ではなく、“ミドル層”である管理職に潜んでいることが非常に多いのです。
管理職は、上位層の意図を現場に伝え、現場の声を上層部に届ける“媒介者”であり、さらに部下の成長を支援し、チームのパフォーマンスを最大化する“支援者”でもあります。これらの役割を果たせなければ、どれだけ優れた戦略を描いても現場に落とし込むことができず、結果として組織力の低下を招いてしまいます。
その意味で、管理職育成は単なる人材開発の一環ではなく、「経営戦略の実行力」を担保する根幹の投資と言っても過言ではありません。
管理職が果たすべき役割とは
管理職には「管理」や「監督」という言葉のイメージがありますが、現代においてはそれ以上に「支援」や「伴走」といった要素が求められています。つまり、部下の能力や力を引き出し、チームとして成果を出すための“環境づくり”こそが管理職の中心的な仕事なのです。
ここで誤解してはならないのが、「指示を出すだけの役割」では不十分という点です。現場の一人ひとりの価値観や働き方に配慮しつつ、自発性と協調性を促すリーダーシップが必要です。これは、単なる技術ではなく、考え方や姿勢=マインドセットの育成が欠かせない要素になります。
また、テクノロジーや働き方改革の影響により、チーム運営の在り方も日々進化しています。リモートワークが定着した今、対面での直接的なマネジメントが難しい状況下でも、信頼関係を築き、目標に向けて組織をリードする力が必要とされています。
管理職育成の「基本設計」がなぜ重要なのか
多くの企業では、管理職の育成に関して「属人的」な対応がされているのが実情です。例えば、「上司のやり方を見て学ぶ」「必要になったら研修に参加する」といった形式です。これは、“場当たり的”であると同時に、“成果が再現されにくい”という課題があります。
また、管理職育成は単発の研修だけでは成立しません。戦略的に設計された「育成プロセス」によって、はじめて実効性のある人材開発が可能となります。そこで重要になるのが、「管理職育成の全体設計(アーキテクチャ)」です。これは、以下のようなステップを明確に設計することを指します。
- どのようなスキル・マインドが求められるのかを定義
- いつ・どのタイミングで・どのような方法で育成するのかを体系化
- 成果や成長度をどう測定・評価するのかを可視化
管理職育成の成果は企業全体に波及する
質の高い管理職は、チームの成果を高めるだけではなく、組織文化そのものにも良い影響を及ぼします。具体的には、以下のような成果が期待できます。
- 若手社員の定着率向上
- 部下の自律性・創造性の促進
- 組織全体の心理的安全性の向上
- イノベーション創出の加速
逆に言えば、管理職がうまく機能していないと、どれだけ優秀な人材がいても組織としての成長は止まってしまいます。だからこそ、企業にとっての「未来への投資」として、管理職育成に真剣に取り組む必要があるのです。育成とは、企業の持続的成長と組織力向上の“基盤整備”に他なりません。
管理職が直面する一般的な課題

管理職に任命された人材の多くが、ある時期から「想像していた以上に難しい」と感じるのがマネジメント業務の実態です。これは、個人の資質や努力だけでは解決できない問題が、日々押し寄せてくるポジションであることを示しています。
この章では、管理職が一般的に直面しやすい課題を、3つの観点に分類して解説します。
1. 役割と期待のギャップに苦しむ
まず最も根本的な課題として、「自分が何を求められているのか分からない」という声が挙がります。現場で高い成果を出したプレイヤーが、明確な定義や研修もなく突然「管理職」に昇進するケースでは特に顕著です。こうした管理職は、以下のような悩みを抱えがちです。
- プレイヤー業務とマネジメント業務のバランスが取れない
- 数字責任は重いのに、人材育成のノウハウが分からない
- 自分でやった方が早いと感じ、任せることができない
いわゆる「プレイングマネージャー」の課題は、こうした背景から生まれます。自分も動きながら、部下を見て、成果を出し、方針も作る。こうした多重タスクに疲弊し、業務の優先順位が崩壊してしまうことも珍しくありません。
2. 人間関係の構築と調整に苦戦する
管理職に求められるのは「成果」だけではありません。「人を動かすこと」こそ、マネジメントの本質です。しかし、実際には以下のような部下との人間関係の課題が頻出します。特に近年では、Z世代を中心に「対話型」「納得感重視」のマネジメントが求められています。旧来型の「上司=命令する人」という感覚では、関係がうまく構築できず、信頼も得られません。
- 部下のモチベーションが分からない
- 注意すると「パワハラ」と受け取られるのではと不安
- 若手世代との価値観の違いに戸惑う
一方で、自身の上司からは「数字を出せ」「部下をうまく動かせ」とプレッシャーがかかります。その中で、経営層の意図と現場のリアルの間に挟まれ、「板挟み状態」に苦しむ管理職が多くいます。このような状況では、心理的ストレスが高まり、メンタル不調や早期離職のリスクも高まるのです。
3. マネジメントスキルが不足している
多くの管理職は、昇進後に「突然」マネジメントを求められることが多く、その準備が不足しています。特に不足しがちなスキルには、以下のようなものがあります。
これらのスキルは、知識だけでなく実践と振り返りの中で身につける必要があります。しかし、企業側が適切な育成機会を提供していないと、現場で「迷いながら」「失敗しながら」覚えていくしかなくなり、チームの生産性は大きく損なわれます。
- 目標設定と進捗管理:チームとして成果を出す仕組みをつくれない。
- フィードバックと育成:部下をどう指導すべきか分からない。
- タイムマネジメント:自分の時間が部下対応で奪われ、余裕がなくなる。
- 問題解決力:感情で対応してしまい、冷静に整理・判断できない。
組織的な育成不在が、問題の本質
ここまで述べてきた課題は、実は「本人の資質」や「個人の努力不足」ではありません。問題の本質は、企業が管理職任命と同時に十分な育成設計を用意していないことにあります。多くの企業で見られるのが、「育成は現場任せ」「困ったら研修を受けさせる」といった場当たり的な対応です。これは、役割とスキルのミスマッチを生み、結果として管理職本人もチームも苦しむことになります。任命だけで終わらせるのではなく、「この役割にはこうしたスキルと知識が必要である」と示し、体系的に育成支援することが、企業の責任です。
時代の流れで最近増えるようになった管理職の新たな課題

近年、新たに管理職の間で顕在化してきた課題として、以下が挙げられます。
世代間ギャップの拡大
ミレニアル世代・Z世代との価値観の違いに戸惑う管理職が増えています。上司から見れば「指示通りに動かない」、部下から見れば「時代遅れ」となる。このようなコミュニケーションのズレは深刻です。
ハラスメントへの過剰な警戒
「何を言ってもパワハラと受け取られるのではないか?」という不安から、適切な指導を避ける傾向が見受けられます。これが放任につながり、部下の成長機会を奪う結果となります。
多様性マネジメントの必要性
性別、国籍、働き方の多様化により、「一律の指導」では通用しません。個人に合わせた柔軟な対応力が、管理職に強く求められています。
これらの「新しい課題」に対応できるスキルと意識の育成は、これまで以上に重要です。
管理職が求められる役割の種類

管理職の仕事は「部下を管理すること」だと、未だに誤解されがちです。しかし、現代において管理職に求められる役割は、単なる管理や統率にとどまりません。むしろ、「いかに部下を導き、成果と成長を両立させるか」という戦略的かつ人的側面を強く帯びた職責であると言えます。
本章では、現代の管理職に求められる基本的な3つの役割について解説するとともに、それぞれの意味や重要性を掘り下げていきます。
1. ビジネスリーダー:成果を上げる責任者としての役割
ビジネスリーダーとは、「組織として成果を出すこと」に責任を持つ存在です。
これは数字の達成にとどまらず、戦略を理解し、それを現場で実行する橋渡し役も担います。例えば、営業部門の管理職であれば、個々の営業担当の成績管理だけでなく、チーム全体として目標を達成するための戦略を描き、施策を計画し、必要に応じて軌道修正するという一連のプロセスが求められます。この役割が不在だと、現場は動いているように見えても、バラバラの方向を向いており、組織としての成果に結びつきません。
「全体最適を考え、戦略的にリードできる存在」として、ビジネスリーダーの視点は極めて重要です。
2. ピープルマネージャー:人を動かす関係構築者
部下の能力を最大限に引き出し、チームとしての力を高めるには、信頼関係に基づいたコミュニケーションとマネジメントが不可欠です。ここで求められるのが、「ピープルマネージャー」としての役割です。
ピープルマネージャーは、部下一人ひとりの価値観や強みを理解し、その人に合った成長支援を行う存在です。ただ指示を出すのではなく、対話を通じて自発的な行動を促す“コーチ”としての機能も担います。例えば、1on1ミーティングを通じて部下の内面にアプローチしたり、心理的安全性の高いチームをつくることは、この役割に深く関係します。特にZ世代などの若手社員は、「納得感」や「共感」を重視する傾向があり、従来の“トップダウン型”だけでは成果が出ません。
このように、ピープルマネージャーは組織の人的資源を最大限に活かすための“土台”をつくる、非常に重要な存在です。
3. チェンジエージェント:変化を推進する改革者
ビジネス環境が目まぐるしく変化する中で、管理職は「現状を守る」だけではなく、「変化を起こす」ことも求められます。チェンジエージェントとしての役割とは、まさにその変革を推進する存在です。
新たなITツールの導入、業務プロセスの見直し、柔軟な働き方への対応など、現代の職場には絶え間ない変化があります。しかし、多くの現場では「変化への抵抗」が自然に発生します。人は本能的に変化を嫌う傾向があるからです。
ここで必要なのが、「変化の必要性を伝え、納得感を持たせ、具体的な行動に導く」力です。チェンジエージェントは、現場の声に耳を傾けながらも、未来に向けた視点を持ち、現状を打破する旗振り役を担うのです。この役割が果たせない管理職は、組織の変革を阻む“ボトルネック”となりかねません。逆に、変化に前向きな管理職は、組織全体を前進させる大きな推進力となります。
なぜ3つの役割を意識すべきなのか?
これら3つの役割は、相互に補完しあう関係にあります。ビジネスリーダーとしての成果追求だけに偏れば、部下との関係性が壊れ、チームは機械的にしか動きません。ピープルマネージャーとして部下との関係性だけを重視すれば、戦略的成果が犠牲になる恐れがあります。変化への対応もせず、現状維持に甘んじていれば、時代に取り残されてしまいます。
だからこそ、3つの視点をバランスよく持ち、場面ごとに使い分けることが管理職には求められるのです。
管理職に必要なスキル

管理職にはさまざまな期待が寄せられますが、その土台となるのが「スキル」です。役割を理解し、組織の中でリーダーとして機能するためには、感覚や経験だけに頼るのではなく、体系的にスキルを磨くことが必要です。
ここでは、現代の管理職にとって特に重要とされる6つのスキルを取り上げ、それぞれの意味や現場での活用シーンを紹介します。
1. コミュニケーション力
すべてのマネジメントの起点とも言えるのが、コミュニケーション力です。
これは単に「話す」「伝える」だけでなく、「聞く」「引き出す」「共感する」など、双方向の関係性を構築する力を指します。現代の職場では、部下との1on1ミーティング、他部署との調整、経営層への報告など、さまざまな関係性の中で意思疎通を図る機会があります。ここで齟齬が生まれると、組織の意思決定や行動にズレが生じ、生産性が低下します。また、Z世代の若手社員は「納得感」や「対話姿勢」を重視する傾向があり、従来の一方的な指示・命令では信頼を築くことが困難です。
だからこそ、管理職は“伝え方”だけでなく、“聴き方”のスキルも高める必要があります。
2. 意思決定力
次に求められるのが、意思決定力です。
現場では、常に「どう判断するか」が問われます。情報が不足していたり、関係者の利害が一致しなかったりする中でも、管理職は決断し、組織を前に進めなければなりません。曖昧な態度や優柔不断な判断は、部下に不信感を与え、組織の推進力を弱める要因となります。また、意思決定におけるスピード感やタイミングも成果に直結します。
重要なのは、「自分の判断軸」を持ちつつも、独断にならないこと。関係者の声を聞き、必要な情報を整理し、責任をもって意思を示すスキルが、信頼されるリーダーには不可欠です。
3. コーチング・フィードバック力
部下の成長を支援するには、コーチングやフィードバックのスキルが欠かせません。
多くの管理職が苦手とする分野ですが、ここにこそ育成の鍵があります。フィードバックには、評価の伝達だけでなく、「行動改善のための具体的なアドバイス」や「モチベーションを高める声かけ」など、さまざまな側面があります。また、コーチングでは、部下が自ら考え、主体的に行動することを促す“問いかけ”の力が問われます。教えるのではなく、引き出す。これが現代のマネジメントにおける重要なアプローチです。
日々の面談や1on1を活用しながら、部下との信頼関係を深め、成長につながる働きかけができるかどうかは、管理職としての力量を大きく左右します。
4. タイムマネジメント能力
プレイングマネージャーにとって大きな課題の一つが、時間の使い方です。
業務とマネジメントを両立するには、計画的かつ戦略的に時間を使うスキルが不可欠です。会議に追われ、本来注力すべき業務が後回しになる。部下の相談対応に時間を取られ、自分の業務が深夜までずれ込む。こうした状況は、結果的にパフォーマンスも健康も損ないます。
タイムマネジメントには、業務の「優先順位付け」、時間の「可視化」、チーム内での「タスク分散」などが含まれます。個人で抱え込まず、チームとして成果を出す時間配分を考えることが、管理職の重要な役割です。
5. チームビルディング力
成果は個人ではなく、チームとして出すもの。そのためには、管理職には「チームビルディング」のスキルが必要です。
メンバー同士の相互理解を深め、心理的安全性の高い関係性を築くこと。強みや特性を活かして役割を分担すること。共通の目標に向けて、エンゲージメントを高めること。これらはすべて、管理職の手腕にかかっています。多様な価値観を持つメンバーが集まる現代の職場においては、単なる仲良しグループではなく、“成果を出すための協働体制”を構築する力が問われます。
リーダーが明確なビジョンを提示し、チームが一体感を持って進める環境をつくること。それが、管理職としての真の価値です。
6. メンタルヘルスマネジメント
最後に、近年ますます重要性が高まっているのが、メンタルヘルスマネジメントです。
部下の心の不調をいち早く察知し、適切に対応するスキルは、今の管理職にとって“必須条件”と言えます。これは、医療的な対応をすることではなく、「日常の変化に気づく」「話を聴く」「必要に応じて専門機関と連携する」など、マネジメントの延長線上にある実践です。また、自分自身のストレスコントロールも重要です。管理職は、業務・人・組織の板挟みになりやすく、誰よりも強いプレッシャーを感じる立場でもあります。
セルフケアを含め、メンタルに対するリテラシーを高めておくことが、長期的なパフォーマンス維持につながります。
スキルは「点」ではなく「線」で育てる
これら6つのスキルは、それぞれが独立しているわけではなく、相互に関係しています。
例えば、良質なフィードバックにはコミュニケーション力が必要であり、チームビルディングには意思決定力や時間管理が影響します。
管理職育成においては、「どのスキルを、どのような順番で、どう伸ばしていくか」という設計が極めて重要です。単発的な研修だけではなく、現場での実践とフィードバックを通じてスキルを“線”として育てていくことが求められます。
管理職の課題への具体的な対処法

管理職が直面する課題を放置すれば、個人のモチベーション低下や組織全体の生産性低下、さらには優秀な人材の離職へとつながります。
ここでは、管理職の課題に対する実践的な対処法を紹介します。これらの手法を組み合わせ、管理職個々の課題に応じて柔軟に対応することが求められます。
定期的な1on1ミーティングの導入
部下とのコミュニケーション機会を定期的に設けることで、信頼関係の構築と課題の早期発見が可能になります。「話を聴く」ことに重きを置くことで、部下のモチベーションも向上します。
フィードバック文化の醸成
日常的にポジティブ/建設的なフィードバックを行うことで、指導への抵抗感を減らし、育成の質を高めることができます。
メンター制度の活用
新任管理職には、経験豊富な管理職を「メンター」としてつける制度が効果的です。実践知の伝承が進み、自信と安定感を持って役割を果たせるようになります。
タレントマネジメントとの連動
人事評価制度やキャリア開発と、管理職の育成を連動させることで、個人に応じた課題解決と組織の人材最適配置が実現します。
管理職の課題を減らすためにあらかじめ対策を打つ
育成や対処だけでなく、「事前の設計」こそが成功の鍵を握ります。管理職が過剰に悩む状況を減らすための、事前対策の重要性を解説します。
明確な役割定義と期待値の共有
昇進後に「何を求められているか分からない」という状態が最も危険です。ジョブディスクリプションや行動指針など、具体的な期待値の明文化が不可欠です。
スキルマップとアセスメントの活用
管理職に必要なスキルセットを明文化し、定期的なアセスメントを行うことで、「何が足りないのか」「どこを強化すべきか」が可視化され、研修施策もより的確になります。
育成ロードマップの策定
昇進前・昇進直後・定着フェーズといった段階に応じて、育成施策を段階的に配置することで、無理なくスキルとマインドを獲得していくことができます。事前設計と制度の整備により、管理職が安心して挑戦できる環境を整えることが、結果的に企業全体のパフォーマンス向上につながります。
管理職育成の際のポイント

育成を成功させるには、戦略と現場のリアルを両立させたプログラム設計が必要です。以下のポイントを押さえた育成施策が特に効果的です。
研修だけで終わらせない仕組み
「研修→実践→フィードバック→再学習」のPDCAを組み込んだ設計が望ましいです。特にOJTとの連動や、上司からの継続支援が不可欠です。育成は一度きりで終わるものではなく、企業文化として根付かせる意識が求められます。
マインドとスキルの両立
知識やテクニックだけでなく、「なぜそれをするのか?」というマインドセットへのアプローチが育成効果を高めます。
組織全体で育成を支える文化
育成を“個人任せ”にせず、組織として支える風土が大切です。評価制度や上司の関与度合いなど、制度面からも支援体制を構築しましょう。
経営層の巻き込み
育成の位置づけを「企業戦略」として明確に示し、経営層が本気で関与することで、現場も本気になります。
管理職の育成でやってはいけないこと
最後に、管理職育成の場面でありがちな「失敗例」と、避けるべき行動について紹介します。これらのポイントを避けることで、管理職育成の失敗リスクを大幅に軽減することが可能です。
優秀なプレイヤーを急に管理職にする
成果を出したからといって、そのままマネジメントができるわけではありません。準備期間もなく昇進させることは、本人にとってもチームにとってもリスクです。
研修だけで終わらせる
一方通行の座学研修だけでは、実務に活かせません。実践機会の提供と、フィードバックのサイクルがなければ、意味のない「自己満足研修」になりがちです。
育成を本人任せにする
「管理職になったんだから自分で何とかして」という姿勢では、育成は進みません。上司や人事が積極的に関与し、共に成長を支援する姿勢が求められます。
まとめ
管理職育成は、企業の未来を左右する重要な経営課題のひとつです。プレイヤーとして優秀だった人材も、マネジメントにおいては全く異なる役割とスキルが求められます。そのギャップを理解せずに「任命だけで育成なし」としてしまえば、本人も組織も疲弊し、せっかくの人材資源を活かしきれなくなるでしょう。
本コラムでは、管理職が直面する一般的な課題や、時代とともに変化している新たな悩み、さらには現代の管理職に求められる役割・スキル・マインドセットを網羅的に整理しました。また、育成に失敗しないためのポイントや防止策、そしてよくある失敗例まで具体的に解説しています。
これらを通して浮かび上がるのは、「管理職育成には場当たり的な対応ではなく、戦略的な設計と仕組みが必要だ」ということです。言い換えれば、管理職を“育てる仕組み”がある企業こそが、激しい時代の変化の中でも柔軟に対応し、持続的に成長していける企業だと言えます。
管理職の不調は、チーム全体のパフォーマンス低下や部下の離職に直結します。逆に、良質なマネージャーは、部下の成長を促進し、組織の力を底上げします。だからこそ、今このタイミングで「管理職育成」に本気で取り組む価値があるのです。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方

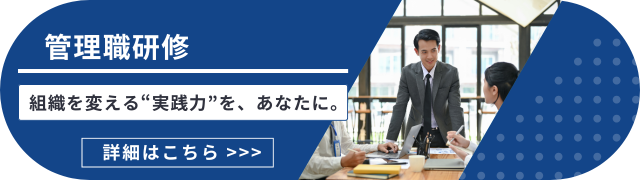


コメント