企業が持続的に成長していくためには、従業員の状態を正しく把握し、組織課題を早期に発見・改善することが不可欠です。そこで注目されているのが「組織サーベイ」です。従業員の本音を可視化し、組織の健康状態を診断できるこの調査手法は、近年、多くの人事担当者に活用されています。
このコラムでは、組織サーベイの目的や種類、メリット・デメリット、実施の流れや成功のポイントまでを詳しく解説します。
< このコラムでわかる3つのポイント >
1.組織サーベイの定義と導入目的、メリット・デメリットの理解
2.組織課題に応じたサーベイの種類と選び方
3.サーベイの実施から活用までの具体的な手順と進め方
Contents
組織サーベイとは?
企業が抱える多くの課題は、目に見えにくい組織内の状態から生まれます。職場の空気や人間関係、マネジメントの不全など、表面には出てこない「見えない課題」は、従業員の声を通してしか掴めないことも少なくありません。こうした組織の状態を診断し、課題の可視化に役立つのが「組織サーベイ」です。
組織サーベイの定義と役割
組織サーベイとは、従業員を対象に職場環境や働き方、上司との関係性、業務満足度などの項目について調査を行い、組織の状態や課題を可視化する手法です。一般的にはアンケート形式で行われ、数値やコメントを通じて従業員の本音をデータ化します。
このサーベイの最大の目的は、経営層や人事担当者が見落としがちな現場の実情を浮き彫りにすることです。表面的な数値では見えない組織の「温度感」を把握し、的確な改善施策につなげる基礎情報として活用できます。
どんな内容が調査されるのか
組織サーベイの調査項目は、目的に応じてカスタマイズされますが、主に以下のような領域が対象になります。これらの項目を通して、従業員が日常的に感じていることを定量的に把握できるようになります。最近では、組織における「心理的安全性」や「心理的疲弊度」といった、感情や精神的負荷に関する測定も取り入れられつつあります。
- エンゲージメント(会社への愛着・貢献意欲)
- 職場環境(設備・働きやすさ・安全性など)
- 人間関係(上司・同僚との信頼関係)
- 業務の納得感や役割理解
- 組織文化や企業理念の浸透度
「感覚」ではなく「データ」で組織を見る
これまでの企業運営では、管理職や人事担当の「経験則」や「現場の勘」に頼って組織運営が行われる場面が多く見られました。しかし、組織が大きくなるほど、属人的な判断ではカバーしきれなくなります。組織サーベイを使うことで、主観ではなく客観的なデータに基づく判断が可能になります。
例えば、離職者が続出している部署に対し、「なぜ人が辞めるのか」を感覚で推測するのではなく、実際に従業員が感じているストレス要因や満足度の低下要因を明らかにすることができます。これにより、再発防止や組織改善のための施策が、より精緻で効果的になります。
組織の信頼関係構築にもつながる
サーベイの活用は、従業員との信頼関係を築く上でも重要です。調査を通して「会社が自分たちの声に耳を傾けている」と感じてもらうことは、エンゲージメントの向上に直結します。ただし、結果を収集するだけで終わってしまうと逆効果になることもあるため、サーベイの実施後は必ずフィードバックと改善策の共有が求められます。
また、匿名性を確保することで、従業員が本音で回答しやすくなる環境をつくることも欠かせません。このように、組織サーベイは「聞くだけ」ではなく「聞いたうえでどう行動するか」までを含めて初めて効果を発揮します。
企業の成長戦略としての位置づけ
組織サーベイは単なる人事施策にとどまりません。企業全体の戦略と密接に関わる「経営インフラ」として位置づけられることも増えてきました。とくに人的資本経営が注目される現在においては、従業員データの取得と分析は重要な経営資源となりつつあります。実際に、調査結果を経営判断に活用し、社内の配置転換や評価制度の見直しなどに反映する企業も多く見られます。
このように、組織サーベイは人事やマネジメントの枠を超えて、企業全体に影響を与えるツールとして浸透してきているのです。
組織サーベイを行う目的

組織サーベイは「従業員の本音を把握するための調査」として広く認知されつつありますが、目的が曖昧なまま実施しても、期待した成果を得ることはできません。では、企業はどのような目的で組織サーベイを行うべきなのでしょうか。
この章では、組織サーベイを実施する主な目的について、具体的に解説していきます。
組織の現状を客観的に把握する
組織サーベイの最も基本的な目的は、「組織の現状を正確に把握すること」です。経営陣や人事が抱く組織像と、現場の従業員が感じているリアルな状況には、往々にしてギャップがあります。その差を明らかにし、組織としてどのような状態にあるのかを客観的に捉えることが第一歩となります。
サーベイの結果によって、「どの部署でストレスが高まっているか」「どの層でエンゲージメントが低下しているか」など、可視化される情報は多岐にわたります。これにより、人事やマネジメント層は感覚ではなくデータに基づいた判断が可能になります。
組織課題の特定と優先順位づけ
サーベイの結果は、現場に潜む課題を特定するのに非常に有効です。表面的には問題がなさそうに見えても、実際には「評価に不満を抱いている」「上司との信頼関係が希薄」「理念が浸透していない」など、深層的な問題が存在するケースがあります。
これらの課題を特定することで、改善に向けたアクションの優先順位を決めやすくなります。特にリソースが限られる中小企業にとっては、優先的に手を打つべきポイントを見極める材料として活用することが重要です。
従業員エンゲージメントの向上
近年、多くの企業が注目しているのが「従業員エンゲージメントの向上」です。エンゲージメントとは、従業員が企業に対して持つ愛着や信頼、貢献意欲のことを指します。エンゲージメントが高いほど、離職率が低く、生産性も高い傾向があるとされ、経営指標としての注目も集まっています。
組織サーベイは、こうしたエンゲージメントの実態を数値化するために非常に有効です。従業員が会社に対してどのような感情を抱いているのかを可視化し、その変化を時系列で追うことができるため、改善施策の効果検証にも役立ちます。
離職防止と定着率の向上
人材不足が深刻化する中、従業員の離職防止も重要な目的の一つです。従業員が会社を辞める決断をする前には、何らかの不満やストレスが存在します。しかし、それは普段の業務の中では表面化しにくく、サーベイのような仕組みを通じて初めて見えてくるケースが少なくありません。
特に、若手や中途採用者など、比較的組織との接点が浅い層においては、オンボーディングの一環としてサーベイを導入することで、早期離職を防ぐ効果が期待できます。これにより、採用コストや教育コストの削減にもつながります。
組織文化や理念の浸透度を測る
企業として掲げている理念やビジョンが、実際に現場にまで浸透しているかどうかは、日常業務だけでは測りづらいものです。サーベイでは、こうした「理念の共感度」「価値観の共有度」といった抽象的な要素も数値化することが可能です。
例えば、「この会社の理念に共感しているか」「組織の方向性に納得しているか」といった設問を設けることで、従業員の意識とのズレを確認できます。理念浸透は組織文化の一体感を高め、強い組織づくりに直結するため、定期的な把握が必要です。
以上のように、組織サーベイの目的は単なる調査にとどまらず、組織改善の出発点として幅広く機能します。次章では、こうしたサーベイがどのような種類に分かれているのか、それぞれの特徴とともに見ていきましょう。
組織サーベイの種類とそれぞれの特徴
組織サーベイと一口に言っても、その種類は目的や調査対象によって多岐にわたります。それぞれの特徴を理解し、自社の課題に最適なサーベイを選定することが、効果的な運用の第一歩です。
この章では、代表的な組織サーベイの種類とその特性について詳しく解説していきます。
エンゲージメントサーベイ
従業員のエンゲージメント、つまり企業に対する信頼・愛着・貢献意欲などを数値化するためのサーベイです。従業員が仕事に対して前向きな気持ちで取り組んでいるか、組織に対する信頼感を持っているかといった点に焦点を当てて調査が行われます。
近年、エンゲージメントの高低が業績や離職率に強く関連することが明らかになっており、多くの企業がKPIとして設定しています。年に1回など定期的に実施し、トレンドの変化を追いかけるのが一般的です。
従業員満足度調査(ES調査)
従業員が給与、福利厚生、職場環境、人間関係などに対してどの程度満足しているかを測定する調査です。エンゲージメントと似ていますが、「満足度」はより静的な指標であり、日常業務への満足感や不満点を明らかにすることが主目的です。
従業員のモチベーションを把握し、社内制度や労働条件の見直しにつなげる材料として有効です。一方で、満足度が高くてもエンゲージメントが低いケースもあるため、他のサーベイと組み合わせて分析することが推奨されます。
パルスサーベイ
数問程度の簡易的な設問で、週次・月次など高い頻度で実施される短期サイクル型のサーベイです。変化の兆候を早期に捉えることを目的としており、現場の「空気感」や感情の動きを素早く把握するのに向いています。
リアルタイムでの課題抽出や、改善の即時対応を可能にするため、マネージャー層の現場対応力が問われる仕組みでもあります。従業員の負担が少なく継続性も高いため、ツールによる自動化が進んでいます。
オンボーディングサーベイ
新入社員や中途採用者に対して、入社直後から数か月間の期間にわたって実施されるサーベイです。組織との適応状況、業務の理解度、人間関係の構築度合いなどを確認し、早期離職の防止や定着支援を目的としています。
このサーベイの結果をもとに、OJT体制やメンター制度の改善につなげる企業も増えています。入社後のフォロー体制を整える上で欠かせないサーベイの一つです。
360度評価サーベイ(多面評価)
特定の社員を評価対象とし、上司、同僚、部下など複数の視点からフィードバックを集める多面的な調査です。対象者のマネジメント力やコミュニケーション能力、業務推進力など、行動特性を立体的に把握することができます。
マネージャー層の育成や、評価制度の透明性向上、人材開発の基盤として活用されるケースが多くあります。フィードバックが直接本人に届くため、運用には注意が必要です。
サーベイツールによる柔軟な組み合わせも可能に
近年では、SaaS型の組織サーベイツールが登場し、これらの複数サーベイを組み合わせて設計できるようになりました。例えば、年1回のエンゲージメントサーベイに加えて、月次でパルスサーベイを実施することで、マクロとミクロ両面からの分析が可能になります。
また、ツールを用いれば設問のカスタマイズ、回答状況のリアルタイム把握、結果の自動集計・可視化がスムーズに行えるため、従来に比べて運用負荷が大幅に軽減されています。
各サーベイの特性を理解し、目的やタイミングに応じて適切に使い分けることで、より質の高い組織診断が可能になります。次章では、こうした組織サーベイを通じて得られるメリットについて詳しく見ていきましょう。
組織サーベイのメリット

組織サーベイの導入には一定の工数や準備が伴いますが、それを上回る多くのメリットがあります。従業員の声を定量的に可視化することで、感覚に頼らない意思決定や組織改善の道筋を描くことが可能になります。
この章では、組織サーベイを実施することで得られる主な利点を解説します。
組織の状態を客観的に把握できる
最も大きなメリットの一つは、組織の状態を感覚ではなく、データとして客観的に把握できる点です。経営者や管理職が認識している課題と、従業員が感じている現実との間には、大きな乖離があることも少なくありません。
組織サーベイによって、従業員のエンゲージメント、満足度、心理的安全性、上司との関係などを項目別に把握できるようになります。これにより、課題の傾向や偏りを明確にし、根拠に基づいた対応が取れるようになります。
課題の優先順位が明確になる
組織の改善は限られたリソースの中で行わなければならないため、「何を優先的に改善すべきか」を判断する必要があります。サーベイ結果を分析することで、どの部署で、どのような課題が深刻なのかが明らかになり、対策の優先順位づけが可能になります。
例えば、ある部署で「上司との信頼関係」に関する項目のスコアが著しく低い場合、マネジメントスキルの強化や1on1の導入など、的確なアクションを選択できるようになります。
エンゲージメント向上につながる
組織サーベイの実施自体が、従業員への「関心の表れ」として機能します。「自分たちの声を聞いてくれている」「改善しようとしている」というメッセージが伝わることで、組織への信頼感が増し、エンゲージメントの向上につながります。
また、調査後のフィードバックや改善アクションを適切に行うことで、従業員の「声が組織を動かしている」という実感が醸成され、自発的な行動や貢献意欲を引き出すことにもつながります。
離職リスクの早期発見と対応が可能になる
従業員の不満やストレスが表面化する前に、定期的なサーベイを通じて兆候をキャッチすることが可能になります。これにより、離職予備軍に対するピンポイントのアプローチや、職場環境の見直しなど、早期の対応が取れるようになります。
特に、若手社員や中途採用者など、組織への適応途中にある層に対しては、オンボーディングサーベイと組み合わせることで、定着率の向上にも寄与します。
人事施策や制度の改善に活かせる
サーベイで得たデータは、人事制度や組織設計の見直しにも役立ちます。例えば、評価制度への不満が多く見られる場合には、評価基準の透明性やフィードバック体制の改善に着手する根拠となります。
また、マネジメント層に対する育成プログラムや、コミュニケーションの活性化施策の検討材料としても有効です。属人的な感覚ではなく、実態に基づく施策立案が可能になります。
組織改善の進捗を継続的に測定できる
一度きりではなく、定期的に実施することで、組織改善施策の効果を検証する手段としても機能します。施策を講じた後に「どう変化したか」をデータで追えるため、改善の手応えを確認しながら次の一手を考えることができます。
加えて、結果を可視化するダッシュボードやレポートツールを活用すれば、経営層や現場の管理職との情報共有もスムーズになり、全社的な改善への一体感も高まります。
ここまで、組織サーベイによって得られる具体的なメリットを見てきました。次章では、逆に組織サーベイのデメリットや注意点について整理し、実施時に陥りがちな失敗を防ぐための視点を紹介します。
組織サーベイのデメリット
組織サーベイは多くのメリットをもたらす一方で、運用方法や設計によっては逆効果となるケースもあります。適切に設計・実施されなければ、従業員の信頼を損なったり、誤った判断を招く恐れもあるため、事前に注意すべきポイントを把握しておくことが重要です。
この章では、組織サーベイに伴う代表的なデメリットやリスクについて解説します。
調査目的が不明確だと活用できない
サーベイを導入する際に最も多い失敗例が、「とりあえず実施したが、結果をどう活用してよいかわからない」というケースです。目的が曖昧なまま実施されたサーベイは、収集したデータが断片的で分析しにくく、組織改善に活かすことが難しくなります。加えて、従業員からも「何のための調査かわからない」と思われてしまい、回答のモチベーションが下がる恐れもあります。これは結果の信頼性を大きく損なう要因です。
回答の質がバラつく可能性がある
設問の設計が不十分だと、従業員による解釈の違いや誤解が生じやすく、正確なデータが得られません。また、質問が曖昧であったり、意図が伝わりにくい場合には、回答が感覚的・場当たり的になってしまい、分析の精度も低下します。さらに、サーベイの頻度が高すぎると「サーベイ疲れ」が起こり、形式的な回答や空欄回答が増加するリスクもあります。
結果の扱い方を誤ると逆効果になる
サーベイの結果を活かせない、または活かさないままで放置すると、従業員の不信感を招きます。特に、調査後に何のアクションも起きなかった場合、「形だけのパフォーマンスだった」という印象を与えてしまい、次回以降の協力も得にくくなります。結果を公開しない、または一部の都合の良い部分だけを取り上げるといった対応も、透明性を欠く姿勢として従業員の反感を買いやすくなります。
誤った分析で判断ミスが起きる可能性
集まったデータをどう分析するかも重要な論点です。専門的な知見がないまま分析を進めると、統計的な偏りやサンプル数の不備に気づかず、誤った解釈につながる可能性があります。
例えば、一時的な社内イベントや外部要因(異動、リストラ、トラブルなど)が影響して一部のスコアが大きく上下している場合、その背景を理解せずに単純比較すると誤った判断材料になりかねません。
組織の分断を助長するリスク
サーベイ結果が明確に可視化されることで、「できている部署」「できていない部署」が数値として表れ、比較対象となってしまうことがあります。これは、マネジメント層の間で過度なプレッシャーを生んだり、他部署との関係性を悪化させる原因にもなりかねません。
また、結果に過度に依存しすぎると、数字だけを追いかける短期的な対応に陥る可能性もあります。サーベイはあくまで一つの指標であることを念頭に置き、背景の理解や定性的な意見との併用が不可欠です。
これらのリスクを理解し、適切に対処することで、サーベイの効果を最大限に引き出すことが可能になります。次章では、実際に組織サーベイを導入・実施する流れについて、具体的な手順とともに紹介していきます。
組織サーベイを実施する流れ
組織サーベイを成功させるためには、ただ調査を行うだけでなく、目的設計から分析、改善アクションまでを一貫して計画的に進める必要があります。
この章では、サーベイを実施するための基本的なステップを6つの段階に分けて解説します。
1. 実施目的と調査範囲の明確化
最初に行うべきは、なぜ組織サーベイを行うのかという目的の明確化です。例えば「エンゲージメントの低下要因を知りたい」「離職の前兆を捉えたい」「部門ごとの課題を比較したい」など、何を知りたいのかを具体的に定めます。
目的が明確になれば、調査する対象や範囲、適切な調査項目も自ずと定まってきます。全社規模で行うか、特定の部門に絞るかといった調査対象の範囲もここで検討します。
2. 設問の設計とツールの選定
次に必要なのが、調査項目(設問)の設計です。目的に合った設問を設定することで、必要な情報を確実に引き出すことができます。例えば「職場の心理的安全性」「上司への信頼」「業務量への満足度」など、定量と定性のバランスを意識して設計することが重要です。
また、設問数が多すぎると回答の負担となり、逆に少なすぎると情報量が不足してしまいます。回答時間は10〜15分程度に収まる構成が理想とされます。あわせて、実施方法(紙・Excel・Webフォーム・専用ツールなど)を決める必要があります。特に中小企業では、サーベイツールを活用することで集計や可視化の効率が大幅に向上します。
3. 従業員への告知と目的の共有
調査の前には、従業員に対して「なぜこの調査を行うのか」「結果はどのように使われるのか」「個人が特定されることはない」などを丁寧に説明することが重要です。告知が不十分だと、回答率が下がったり、内容に対する不信感が生まれる可能性があります。経営層や部門長からのメッセージを通じて、サーベイの意義をしっかりと伝えることで、信頼を得ることができます。
4. 調査の実施と回答回収
告知が済んだら、実際に調査を実施します。ツールを活用してWeb上で行う場合は、スマートフォンからでも回答できる設計にすると、回答率が上がりやすくなります。期間は1〜2週間程度が一般的で、回収状況を随時チェックしながら、未回答者にはリマインドを送ることも必要です。ここで大切なのは、「回答を強制しない」こと。自発的な回答を重視する姿勢が信頼関係の構築につながります。
5. 結果の集計と分析
回収が終わったら、次は結果の集計と分析です。全体傾向に加え、部門別・職種別・勤続年数別などでクロス集計を行い、特徴的な傾向を読み取ります。特に注目すべきは、「極端に低い項目」「部署間のスコア差」「時系列での変化」などです。グラフやヒートマップなどを活用すれば、可視化された結果を関係者に共有しやすくなります。
この分析フェーズでは、数値だけでなく自由記述欄の内容も重要です。そこに従業員の本音が現れていることが多く、数値には表れない課題や期待を読み取る手がかりになります。
6. フィードバックと改善アクション
最後に、サーベイの結果を従業員にフィードバックし、それを踏まえた改善アクションを実行します。重要なのは、「調査して終わり」にしないことです。例えば、「エンゲージメントが低かった部門で1on1ミーティングを導入」「働き方に関する不満が多かった部署で制度を見直す」といった具体的な施策につなげましょう。
改善に取り組んでいる姿勢を見せることが、次回以降のサーベイに対する信頼にもつながります。また、改善結果を次回の調査で測定すれば、取り組みの効果検証にも役立ちます。
このように、組織サーベイの実施には明確なステップと準備が必要です。次章では、サーベイをより効果的に活用し、実際に成果を上げるための成功ポイントについて紹介していきます。
組織サーベイを成功させるポイント
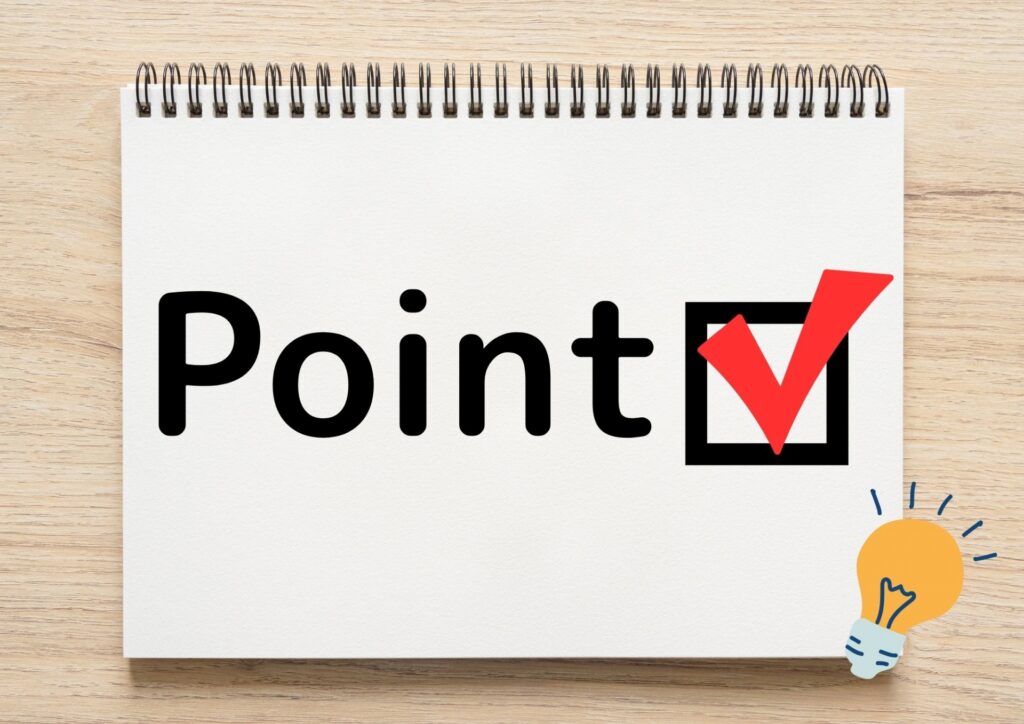
組織サーベイは実施するだけで効果が出るものではありません。目的に合った設計、運用、分析、フィードバックまでの一連のプロセスを丁寧に行うことが、成功の鍵となります。
この章では、組織サーベイを有効活用し、成果を最大化するための実践的なポイントを紹介します。
サーベイの目的を明確にする
最初にすべきことは、「なぜこのサーベイを実施するのか」という目的を明文化することです。エンゲージメントを高めたいのか、離職防止なのか、それともマネジメントの質を把握したいのか。目的によって設問設計も分析方針も大きく変わるため、ここが曖昧だとサーベイ全体が機能しなくなります。
また、目的が明確であれば、従業員にも「この調査は何のために行われるのか」をしっかり伝えることができ、協力も得やすくなります。
シンプルでわかりやすい設問を設計する
調査項目は、専門用語やあいまいな表現を避け、誰が読んでも理解できる内容にすることが重要です。設問数が多すぎると途中離脱や適当な回答が増え、少なすぎると分析が難しくなります。設問数は10〜20問程度に収めるのが一般的です。特に注目すべきは、「測定したいことが本当にその設問で測れているか」という視点です。例えば「上司と信頼関係が築けているか」という設問に対しては、その信頼の定義や背景を想定しておく必要があります。
回答率を高める工夫をする
せっかく設問を用意しても、回答率が低ければ正確な分析ができません。高い回答率を得るためには、「匿名性の担保」「目的の丁寧な説明」「結果の活用方針の共有」など、従業員の不安を払拭する工夫が必要です。
また、経営層や部門長など、影響力のある人からのメッセージがあると、回答の意義が伝わりやすくなります。ツールを使ってスマホから手軽に回答できるようにするなど、利便性も重要なポイントです。
結果をオープンにし、フィードバックする
サーベイの結果は、分析者だけでなく、できる限り従業員にフィードバックすることが望ましいです。全体の傾向や改善の方向性を共有することで、「自分たちの声が活かされている」という実感が生まれ、組織への信頼感が向上します。フィードバックの際は、「良かった点」だけでなく「改善が必要な点」も正直に伝えることが大切です。ネガティブな結果も、組織の成長に必要な材料として前向きに扱う姿勢を示しましょう。
改善アクションとPDCAサイクルの実行
サーベイの本質は、調査ではなく「その後の行動」にあります。調査結果をもとに、実際に改善アクションを実行することが、サーベイの価値を生み出します。例えば、心理的安全性が低い部署に対して1on1を導入したり、コミュニケーション量の見直しを図るなど、課題に応じた施策を打ちましょう。
また、施策の効果を次回のサーベイで測定することで、PDCAサイクルが回ります。継続的に実施・検証する仕組みをつくることで、組織改善の質が向上します。
管理職の巻き込みと責任分担
現場での実行力を高めるには、管理職の協力が不可欠です。サーベイ結果をマネージャーに共有し、自部署の強みや課題を自分事として捉えてもらうことが重要です。加えて、人事部門と現場の間で改善責任を分担し、共にアクションを考える体制を整えると効果的です。管理職へのサーベイ研修や、数値の読み解き方を伝えるガイドラインを用意すると、結果に基づいた行動を促進できます。
組織サーベイを成功に導くためには、丁寧な設計と実行、そして行動につなげる仕組みが不可欠です。次章では、サーベイを行う際に特に注意すべきポイントや、失敗を防ぐための工夫について詳しく解説していきます。
組織サーベイを行う際に気をつけるべきポイント
組織サーベイは、実施方法や伝え方を誤ると、かえって従業員の不信感を招いたり、組織内の温度差を広げてしまうリスクがあります。
この章では、サーベイを行う際にあらかじめ注意すべきポイントを整理し、信頼性と効果性の高い運用を目指すためのヒントを紹介します。
匿名性と信頼性の確保
従業員が本音で回答するためには、安心して意見を伝えられる環境が必要です。特に重要なのが、回答が「誰のものか特定されない」という匿名性の担保です。これが曖昧だと、従業員は無難な答えに終始したり、質問そのものを避けてしまう可能性があります。匿名性を守るためには、第三者ツールの導入や、個人が特定できない属性設計(年齢・性別・部署などの選択肢設定)も有効です。また、情報の取り扱いについて明確なポリシーを提示し、「人事や上司が個人を特定することはない」としっかり説明することも必要です。
サーベイ疲れを避ける
頻繁すぎるサーベイは、従業員の負担やストレスにつながるだけでなく、「またか」といった倦怠感や無関心を引き起こします。このような状態を「サーベイ疲れ」と呼び、回答精度の低下や形式的な参加につながってしまいます。解決策としては、実施頻度を最適化すること、設問数を厳選して短時間で回答できるようにすること、そして毎回の調査に目的やテーマの変化を設けることが挙げられます。
回答の強要をしない
従業員に対して回答を強制するような姿勢は避けるべきです。「全員が回答しないと評価が下がる」「未回答者には個別に催促する」といった対応は、逆に従業員の信頼を損ねる原因となります。あくまでも自発的な回答を促すことを基本とし、「参加することで組織に貢献できる」という前向きなメッセージを伝えることが効果的です。強制ではなく納得の上で参加してもらう姿勢が、信頼あるデータを得るための前提となります。
結果の扱い方に注意する
サーベイの結果は、慎重に扱うべき組織資産です。分析結果をそのまま公開することが逆効果になる場合もあり、特にスコアが極端に低い部署などに対しては配慮が必要です。「悪い数値=責任がある」という認識が広がると、今後のサーベイへの信頼や協力が損なわれる可能性があります。結果を単に「良い・悪い」で判断するのではなく、組織改善の材料として前向きに扱う姿勢が求められます。
部署ごとのバラつきに配慮する
部署によって、文化や役割、雰囲気は大きく異なるため、結果にも当然バラつきが生まれます。しかしこの差を「比較対象」として扱いすぎると、現場に不要な緊張感を与えたり、対立意識を生むリスクがあります。重要なのは、数値の比較ではなく「変化や傾向」を見ることです。前回との比較や、部門ごとの改善ポイントを確認することで、建設的な改善アクションにつながります。
結果を放置しない
サーベイの実施後に何の動きもなければ、「どうせ変わらない」という諦めが組織に蔓延します。これが繰り返されると、次回以降の回答率は下がり、組織としての信頼性も損なわれてしまいます。調査後は、スピード感を持って結果を共有し、短期的・中長期的な改善アクションを発表することが求められます。小さな施策でも「取り組んでいる」姿勢を示すことが、信頼構築の第一歩です。
このような注意点を理解し、丁寧な設計と配慮ある運用を行うことで、組織サーベイは従業員との信頼関係を深める強力なツールとなります。次章では、サーベイの実施・運用を支援する便利なツールやサービスについて紹介していきます。
組織サーベイに便利なツール
組織サーベイを効果的かつ効率的に実施するためには、専用ツールの活用が非常に有効です。設問作成や配信、回答収集、分析、レポート作成といった一連の流れを自動化・簡素化することで、人事や経営層の負担を軽減しながら、より正確でスピーディーな対応が可能になります。
この章では、代表的な組織サーベイツールの特徴と選定時のポイントを紹介します。
組織サーベイツールの主な機能
最近の組織サーベイツールは、単なるアンケート作成機能だけでなく、調査結果のリアルタイム分析やダッシュボードによる可視化機能、他ツールとの連携機能まで備えており、非常に高機能化しています。主な機能としては以下のようなものがあります。これらの機能により、調査から改善アクションへのプロセスを迅速に進めることができ、組織内の意思決定スピードも向上します。
代表的なツールの一例
以下は、国内で導入事例が多く、使い勝手にも定評のある主要なツールの一例です。
- HRBrain(エイチアールブレイン)
エンゲージメント診断や人事評価システムと連携でき、組織改善に必要な分析機能が豊富。テンプレートも多く、はじめての企業にも扱いやすい設計です。 - jinjer(ジンジャー)組織サーベイ
従業員の状態を可視化する機能に加え、人事情報との連携が可能。UIが直感的で、リアルタイム分析や部署別ダッシュボードが強みです。 - カオナビ
人材管理基盤として評価が高く、エンゲージメントサーベイとの統合がスムーズ。360度評価との組み合わせにも適しています。 - ラフールサーベイ
メンタルヘルスやストレスチェックを重視したサーベイが可能で、従業員の心理的安全性に焦点を当てた分析を強化したい企業に適しています。
ツール選定時のポイント
ツールを選ぶ際には、自社の目的とリソースに合った機能が備わっているかを見極める必要があります。以下の観点から評価するとよいでしょう。これらの条件をもとに、単なるコストや知名度だけではなく、「自社で長期的に使い続けられるか」という視点で選定することが大切です。
- 導入のしやすさ:操作が直感的で、特別なIT知識が不要か
- カスタマイズ性:設問や属性、分析軸を柔軟に変更できるか
- 結果の活用度:データの可視化やレポート作成が簡単にできるか
- 従業員の回答しやすさ:スマホ対応やUIの工夫があるか
- サポート体制:初期設定や分析サポートが充実しているか
- セキュリティと匿名性:個人情報保護が担保されているか
ツール活用による業務効率の向上
専用ツールを使うことで、Excelや紙アンケートによる煩雑な集計作業をなくすことができ、人事部門の業務負担が大幅に軽減されます。また、リアルタイムで組織の状態を把握できるため、マネージャーによる迅速な対応が可能となり、結果的に施策の実行スピードも上がります。
さらに、分析結果を経営会議や部門会議などで活用しやすくなるため、組織全体が「データに基づいて動く文化」を醸成するきっかけにもなります。
まとめ
このコラムでは、組織サーベイの基本から、その目的、種類、メリット・デメリット、実施フロー、成功のポイントまでを幅広く解説してきました。従業員の本音を可視化し、組織の状態を客観的に診断することは、企業が持続的に成長するための第一歩です。特に、目に見えにくい職場環境の課題やマネジメントの問題、価値観のズレなどを早期に把握できる点は、サーベイならではの強みです。
ただし、サーベイを行うだけで組織が変わるわけではありません。調査の目的を明確にし、設問の設計、回答の促し方、そして結果の共有・改善アクションまで一貫して行うことが求められます。従業員にとって「ただ聞かれただけ」で終わらないようにするには、調査結果をしっかり分析し、信頼あるフィードバックを提供することが大切です。
また、組織の規模や課題に応じて、適切なサーベイの種類を選び、ツールを活用して運用の負担を軽減することも成功への鍵となります。自社にとって必要な情報をどう引き出し、どう活かすか—そこにサーベイ活用の真価があります。自社の課題解決や組織改善を実現する一歩として、戦略的に組織サーベイを取り入れてみてはいかがでしょうか。
監修者

- 株式会社秀實社 代表取締役
- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。
最新の投稿
 1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説
1 組織戦略・マネジメント2025年9月12日組織マネジメントとは?活用すべきフレームワークを解説 6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説!
6 AI人事・その他2025年9月11日ウェルビーイングとは?企業が注目する理由と実践方法を専門家がわかりやすく解説! 6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは
6 AI人事・その他2025年9月11日人手不足の原因は?企業が取るべき解決と対策とは 6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方
6 AI人事・その他2025年9月11日ノンコア業務とは?コア業務との違いと業務効率化の進め方



コメント